7月のカレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 休み | 2日 休み | 3日 ◯ | 4日 ◯ | 5日 ◯ | 6日 ◯ | |
| 7日 ◯ | 8日 ◯ | 9日 休み | 10日 休み | 11日 ◯ | 12日 ◯ | 13日 ◯ |
| 14日 ◯ | 15日 ◯ | 16日 休み | 17日 ◯ | 18日 休み | 19日 ◯ | 20日 ◯ |
| 21日 休み | 22日 ◯ | 23日 休み | 24日 ◯ | 25日 ◯ | 26日 ◯ | 27日 ◯ |
| 28日 ◯ | 29日 ◯ | 30日 休み | 31日 ◯ |

おしらせ
今日のブログ
朝の通勤電車で毎日耳にするお決まりのアナウンスがある。
「お客様にお願いいたします。携帯電話での通話はご遠慮ください。」
皆さんも必ず聞いたことがあるはずだ。
私はこのアナウンスを聞くたび、頭の中で疑問がぐるぐる回る。
なんで電車の中で電話をしてはいけないんだろう?
もし、子供に「ねぇ、なんで電車で電話はダメなの?」
と、聞かれたら、なんと答えるだろうか。
「それはマナー違反だからだよ。電車の中では電話を使っていけないと言うルールなんだ。」
と答えるか?
では、もし純粋な子どもが、さらにこんな質問をしてきたらどうだろうか。
「じゃあ、なんで電車で電話はダメで、友達とおしゃべりするのはいいの?あそこの人たちもずっと話してるよ?」

確かにそうだ。
会話をするという点では、隣にいる友達と話すのも、電話の向こうの人と話すのも同じように見える。
相手が目の前にいる「人」なのか、それとも電話という「機械」を通した会話なのかで、こんなにもルールが変わるのはなぜだろう?
なぜ人と話すのはオッケーで、機械と話すのはマナー違反なのか。
これを子供にどう説明するか。
読者の皆さんにもぜひ考えていただきたい。
画面を下にスクロールする前に、自分なりの答えを出して欲しい。

もちろん、電車内での携帯電話の通話はマナー違反。大人ならそれは知っていて当然である。
では、もし小さな声で電話をしていたらどうだろう?
隣で友達と楽しそうに話している人たちの声と、大して音量は変わらないんじゃないか?
むしろ、友達同士で普通に話している人たちの方が、はるかに声が大きいこともあるような気がする。
「それでもマナー違反だからよ」と答えるのが簡単かもしれない。
でも、それって本当に答えになっているのか?
今日は、もし我が子にこの質問をされたときにどう答えるか、その備忘録として考えてみたいと思う。
マナーってなんだろう?
そもそも「マナー」とは何だろう?
私は、「自分以外の人に対する配慮」だと思う。
じゃあ、この「配慮」という視点から、なぜ友達との会話はOKで、電話での会話はNGなのかを考えてみよう。
なぜ「電話の声」だけ気になるの?〜より高度な配慮が必要な理由〜
大声で話すことは電話であろうが何だろうが、それがマナー違反だということは子供でも理解できる。
しかし、今回のようなケースは、「目に見えない不快感」がポイントになってくる。
これを理解するには、「より高度な配慮」が必要となる。
実際に電車内で通話をしている人を見かけると、 話す音量の大小にかかわらず「この人はマナーが悪いな」と反射的に思ってしまう。
でも、よくよく考えてみると、実際に自分に直接的な迷惑がかかっているかといえば、そうではない。
電話をしている人の中には、口元に手を当てて、小声で話している人もいる。
つまり当事者も「迷惑にならないように」っていう意識はある。
それでもなぜ、私たちは不快と感じてしまうんだろうか?
その理由は、単に「音量の大小」だけでは測れない、人の心理や公共空間での「共同体意識」が関係していると私は思う。
1. 一方的な音声と情報量の違い
友達同士の会話は、お互いが対面しているから、声のトーンや表情、ジェスチャーなんかの視覚的な情報も加わって、会話全体を理解しやすいという特徴がある。
電車内で聞くときも、私たちの脳は「ああ、あの人たちが話しているな」って自然に認識して、その音声を処理しやすい傾向にある。
まるで、背景で流れるBGMみたいに、意識せずに聞き流せるのだ。
ところが、携帯電話での通話は、片側の声しか聞こえない。
会話の文脈が見えないから、耳に飛び込んでくるのは一方的で断片的な音声だ。
脳は、意味の分からない、途切れ途切れの情報を無意識のうちに処理しようとするから、余計な集中を要して、心理的な負担を感じやすいと言われている。
同じ音量でも、電話の声の方が不快に感じられるのは、この「脳の疲れ」が原因かもしれない。
2. 「共同体意識」と暗黙の了解
電車内は、たくさんの人が一時的に共有する「公共の場」だ。
そこには、みんなが快適に過ごすための暗黙のルールや「共同体意識」が存在する。
携帯電話の通話は、その「共同体」から一時的に意識が離れて、別の個人的な空間に没入する行為だと見なされがち。
これにより、「この人は周りのことを気にしていない」っていう印象を与えて、マナー違反だと感じられることにつながる。
まとめ:子どもにどう伝えるか?
これらの点を踏まえると、子どもへの説明はこうなるかな。
「電車で電話がダメなのは、音が大きいからだけじゃないんだよ。お友達と話すのは、相手が目の前にいるから、周りの人も『あ、お話してるな』ってわかるよね。でも、電話は片方の声しか聞こえないから、周りの人にとっては『何の話してるんだろう?』って気になっちゃって、頭が疲れちゃうんだ。それに、電車の中は、いろんな人が静かに過ごしたいと思っている場所だから、みんなが気持ちよくいられるように、周りの人を特別に気遣う気持ちが大切なんだよ。」
「ルールだから」「マナーだから」で終わらせず、その背景にある「他者への配慮」や「公共空間での心理」、さらには人間の脳の特性を理解することで、子どもたちの「なんで?」にきちんと応えて、彼らの「より高い配慮」や「共同体意識」を育むきっかけになると幸いだ。
あなたのお子さんだったら、この説明で納得してくれると思う?
みんなの意見をぜひコメント欄にお願いします。
1日1問(挑戦してね)
問題 半夏厚朴湯の構成生薬はでないのはどれか。
1.半夏
2.厚朴
3.白朮
4.茯苓
回答→3
【解説】
半夏厚朴湯の効能は行気散結・降逆化痰で、痰気互結による梅核気の治療に用いる。
【 辨证要点 】咽中如有物阻,苔白腻,脉弦滑
【症状】
1⃣津液输布失常,痰气搏结咽喉
・咽喉异物感,是无形痰气交结于咽喉所致
・咯之不出
・吞之不下
・苔白滑,脉弦→有痰,苔白腻,白厚或白滑,肝气郁结脉弦
2⃣肺胃失于宣降,胸中气机不畅
・胸中满闷,善太息,肝气向上犯肺(木火刑金),肝气横逆犯胃(木乘土)
・或咳或呕,以早晨干呕为主(咳き込むこともあれば、吐くこともあるが、主な症状は早朝のからえずき(胃内容物のない嘔吐動作)である。)
半夏厚朴湯(行気剤)
君薬:半夏
臣薬:厚朴、茯苓
佐使薬:生姜、蘇葉
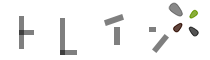






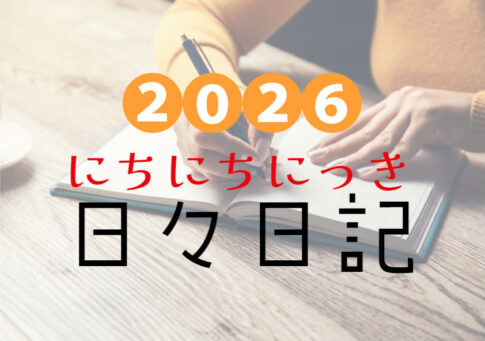
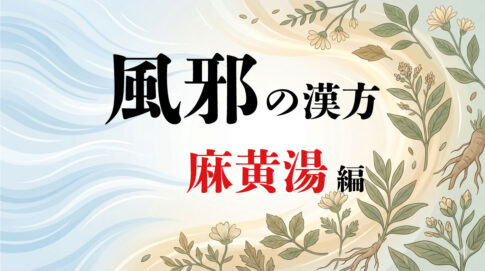

読んだら拍手ボタンを押してね٩( ᐛ )و