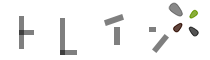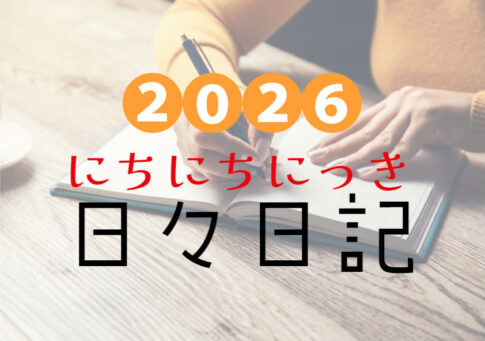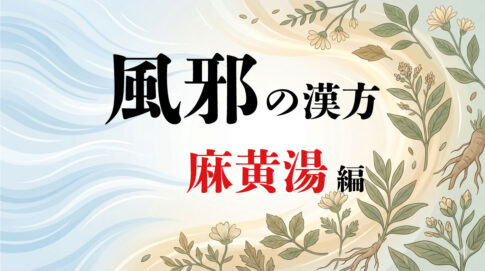問題 下記の中では、痢疾に対する治法でないものはどれか?
1.湿盛なら分利の方法で対応すべきである
2.初の痢に通の治法で対応すべきである
3.久痢に渋の治法で対応すべきである
4.便に赤が多いなら血薬を用いるべきである
5.便に白が多いなら気薬が多く用いるべきである
回答→1
【解説】
痢疾は、腹痛・裏急後重(排便後も便意が残る感覚)・赤白の膿血を伴う下痢を特徴とする病証です。その病理は、腸内に邪気(湿熱、疫毒など)が停滞し、気血を阻滞させて、腐敗したものが膿血として排出されることです。
1.湿盛なら分利の方法で対応すべきである
「分利」は、利尿と利便を同時に行うことで、体内の余分な湿を取り除く治法です。この方法は、主に泄瀉(単なる下痢)の湿盛タイプに用いられ、痢疾のような膿血を伴う病態には適していません。したがって、これが痢疾に対する治法ではありません。
2.初の痢に通の治法で対応すべきである
痢疾の初期は、邪気が盛んで気血が強く阻滞しているため、通法(調気活血)を用いて邪気を速やかに排出し、気の巡りや血の流れを良くすることが重要です。これにより、病邪がさらに深く侵入するのを防ぎます。
3.久痢に渋の治法で対応すべきである
痢疾が長引くと、体の正気が消耗し、肛門を固める力が失われます。この状態を久痢といい、この場合は渋法(収斂固渋)を用いて、下痢を止めることが必要です。
4.便に赤が多いなら血薬を用いるべきである
痢疾の便に「赤(膿血)」が多い場合は、血分が傷つけられていることを示しています。このため、和血の薬を多く用いて血脈を保護し、出血を止める必要があります。
5.便に白が多いなら気薬が多く用いるべきである
痢疾の便に「白(粘液)」が多い場合は、湿熱による気滞が腸内の脂絡を損傷している状態を反映しています。このため、調気(気の巡りを整える)の薬を多く用いて、気の流れを改善する必要があります。
痢疾の病理は湿熱や疫毒などが気血と搏結(結合)し、腸内の脂絡を傷つけることによって起こります。治療は、初期には通法、慢性期には渋法、そして赤白(膿血)の程度に応じて気薬や血薬を使い分けることが基本です。一方、「分利」は、湿邪が中心で膿血を伴わない泄瀉の治法であり、痢疾の治法としては不適切です。
問題 腹痛綿々、時作時止、喜温喜按、飢餓或いは疲労後に痛みが酷くなり、食事或いは休憩で痛みが緩和する。神疲、気短、怯寒、溏便、舌淡苔白、沈細脈を伴う。その治療方剤はどれか?
1.理中丸
2.良附丸
3.香蘇散
4.小建中湯
5.四君子湯
回答→4
【解説】
病名診断:腹痛
「腹痛綿々」が主症状であることから、病名診断は腹痛です。
証候診断:中虚臓寒
⚫︎虚証の証拠:
・腹痛綿々: 痛みが激しいのではなく、弱々しく続く(綿々)のは虚証の特徴です。
・喜按: 押さえると痛みが和らぐ(喜按)のも虚証の典型です。
・飢餓或いは疲労後に痛みが酷くなる: 虚弱な状態(飢餓、疲労)で痛みが悪化します。
・神疲、気短: 精神が疲れ、息が切れるのは、気が不足している(気虚)ことを示します。
⚫︎寒証の証拠:
・喜温: 温めると痛みが和らぐ(喜温)のは寒邪の特徴です。
・怯寒、溏便: 寒がりで、便がゆるい(溏便)のは、体内の陽気が不足していることを示します。
・舌淡苔白、沈細脈: 舌が淡く、苔が白く、脈が深く(沈)細いのは、虚と寒の典型的な舌脈です。
1.理中丸
脾胃虚寒による嘔吐や胃痛に用いる方剤です。小建中湯も脾胃を温めますが、小建中湯はより虚弱を補い、急な痛みを緩和する作用に優れています。
2.良附丸
寒邪客胃による実証の胃痛に用いる方剤です。本症例のような虚証の病態には適しません。
3.香蘇散
寒邪客胃による胃痛で、表証(風邪)を伴う場合に用います。
4.小建中湯
小建中湯は、中焦を温め、虚弱を補い、腹部の痙攣や痛みを和らげる作用に優れた方剤です。特に、甘味で痛みを緩和する膠飴が君薬として多量に配合されているのが特徴です。この方剤は、本症例の「腹痛綿々」「喜温喜按」などの症状に最も適しています。
5.四君子湯
脾気虚の虚弱を補う基本的な方剤です。温中作用や緩急作用は小建中湯に劣ります。
ポイント
⚫︎理中丸との使い分け
・理中丸は脾胃の陽虚による嘔吐や下痢が主の場合に用いられるのに対し、小建中湯は虚弱による腹痛が主症状である場合に用いられます。
問題 寒湿泄瀉で湿邪が重い者の治療に、まず選ぶべき方剤はどれか?
1.葛根芩連湯
2.藿香正気散
3.芍薬湯
4.胃苓湯
5.白頭翁湯
回答→4
【解説】
1.葛根芩連湯
湿熱泄瀉や湿熱痢疾の治療方剤です。本症例の寒湿の病態には適しません。
2.藿香正気散
湿邪も治療できますが、主に外邪感受の寒湿泄瀉に用いられます。本症例は「湿邪が重い」ため、より強力な袪湿作用を持つ胃苓湯がより適しています。
3.芍薬湯
湿熱痢の治療方剤です。寒湿の病態には適しません。
4.胃苓湯
胃苓湯は、五苓散と平胃散を組み合わせた合方です。五苓散は利水滲湿作用が強く、平胃散は燥湿健脾の働きを持ちます。この二つを合わせることで、湿邪を体外に排出し、同時に脾胃の運化機能を回復させるため、湿邪が重い寒湿泄瀉に最も適しています。また、痢疾の虚寒痢にも用いられます。
5.白頭翁湯
疫毒痢疾の治療方剤です。
※寒湿泄瀉の治療は軽症であれば藿香正気散で、表邪を解き、湿を化す治療を行います。
問題 患者、49歳。腹満して時に痛む、喜温喜按、体倦、大便溏稀、舌淡、苔薄白、脈細弱。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.大建中湯
2.柴胡疏肝散
3.小建中湯
4.良附丸
5.呉茱萸丸
回答→3
【解説】
病名診断:腹痛
証候診断:中虚臓寒
1.大建中湯
中虚臓寒の腹痛を治療する方剤ですが、小建中湯よりもさらに重篤な病態に用いられます。嘔吐・四肢の冷え・脈微など、陰寒内盛の症状がある場合に選択されます。本症例はそこまで重篤ではないため、不適切です。
2.柴胡疏肝散
肝気鬱結による腹痛に用いる方剤です。本症例のような虚寒の病態には適しません。
3.小建中湯ー温中補虚、和裏緩急
小建中湯は、中虚臓寒の腹痛に最も適した方剤です。虚弱を補い、腹部の痙攣や痛みを緩和する作用に優れています。多量に配合された膠飴(飴)が、甘味で急な痛みを緩和する役割を果たします。
4.良附丸
寒邪が胃に侵入した実証の腹痛に用います。虚証の病態である本症例には不適切です。
5.呉茱萸丸
寒邪が肝経を侵す風寒頭痛の治療に用います。腹痛が主症状である本症例には適しません。
ポイント
⚫︎小建中湯と大建中湯の使い分け
・小建中湯: 虚弱が主で、腹痛が持続的だが比較的穏やかな場合に用います。
・大建中湯: 虚弱が進み、腹痛が激しく、嘔吐や四肢の冷えといったより重篤な症状を伴う場合に用います。
問題 患者、40歳。暴飲暴食により腹痛を誘発、噯腐呑酸、おならが出ると痛みは軽減、大便不暢、苔厚膩、脈滑。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.良附丸
2.保和丸
3.大承気湯
4.小建中湯
5.以上どれも当てはまらない
回答→2
【解説】
病名診断:腹痛
「暴飲暴食により腹痛を誘発」が主症状であるため、病名診断は腹痛です。
証候診断:飲食停滞
患者の症状は、暴飲暴食によって飲食物が胃腸に停滞し、気の巡りを阻害している飲食停滞の病態を示しています。
⚫︎飲食停滞の証拠
・噯腐呑酸: げっぷが腐敗臭を帯び、酸っぱいものがこみ上げてくるのは、飲食物が消化されずに腐敗している特徴です。
・おならが出ると痛みは軽減: 気が鬱滞して腹痛が生じ、おならとして気が排出されると痛みが和らぐことから、気の鬱滞による腹痛であることがわかります。
・大便不暢: 便がスムーズに出ないのは、飲食物の停滞が腸の伝導機能を阻害していることを示します。
⚫︎舌脈
・苔厚膩: 舌苔が厚く、油っぽいのは、宿食や湿濁が停滞していることを示します。
・脈滑: 脈が滑らかで勢いがあるのは、飲食物が停滞していることを反映する脈です。
1.良附丸
寒邪客胃による胃痛に用いる方剤です。本症例は飲食が原因であり、寒邪による病態ではありません。
2.保和丸ー消食導滞和胃
保和丸は、飲食停滞による軽度から中程度の腹痛や胃痛、消化不良に用いる代表的な方剤です。本症例の腹痛は、「おならが出ると痛みが軽減」することから、比較的軽度な気の鬱滞が主であり、激しい痛みや便秘・下痢がないため、保和丸が適しています。
3.大承気湯
飲食停滞が重く、便秘がひどい場合(食積が化熱して燥となり、舌苔黄燥、拒按など)に用いる方剤です。本症例はそこまで重篤ではないため、不適切です。
4.小建中湯
中虚臓寒による腹痛に用いる方剤です。本症例は実証であり、虚証の病態には適しません。
ポイント
⚫︎飲食停滞の軽重鑑別
・軽症: 腹痛がそれほど激しくなく、便秘や下痢がない場合は、保和丸が適します。保和丸には、飲食物を消化する山楂子や、湿熱を清める連翹などが含まれています。
・重症: 腹痛が激しく、便秘や下痢を伴う場合は、枳実導滞丸などが検討されます。
問題 痢疾の初期に用いるべきでない薬はどれか?
1.疏散表邪の品
2.清熱涼血の品
3.調気行血の品
4.理気化滞の品
5.收斂止瀉の品
回答→5
【解説】
痢疾は、腹痛・裏急後重・赤白の膿血を伴う下痢を特徴とする病証です。特に発病初期は、邪気が盛んで、腸内に湿熱や疫毒などが停滞している実証と熱証が中心となります。
初期の治療の基本原則は、清熱化湿解毒を主とし、さらに調気行血導滞を併用して、速やかに邪気を体外に排出することです。
問題 痢疾の初期で表証を伴う。表邪未解だが、裏熱がすでに盛んでいる。腹痛、裏急後重、痢下赤白、肛門灼熱、身熱汗出、小便短赤、舌苔黄膩、脈滑数。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.芍薬湯
2.藿香正気散
3.葛根黄芩連湯
4.白頭翁湯
5.人参敗毒散
回答→3
【解説】
病名診断:痢疾
証候診断:湿熱痢疾兼表証
1.芍薬湯
湿熱痢の治療方剤ですが、表邪を解く作用はありません。
2.藿香正気散
外邪犯胃の嘔吐や寒湿泄瀉に用いる方剤です。本症例のような裏熱盛の病態には適しません。
3.葛根黄芩連湯
この方剤は、表邪が残る湿熱痢疾に最も適しています。君薬である葛根は、表邪を解きながらも、脾胃の清陽の気を昇発させて下痢を止めます。黄芩と黄連は強力な清熱燥湿作用を持ち、腸内の湿熱を取り除きます。これらの生薬の組み合わせにより、表裏両方の病態を同時に治療することが可能です。
4.白頭翁湯
疫毒痢疾の治療方剤です。本症例には疫毒の特徴的な症状(壮熱、神昏など)が見られません。
5.人参敗毒散
湿熱痢疾の初期で、発熱悪寒や頭身重痛などの表証を伴う場合に用いる方剤です。本症例は「身熱汗出」という表証であり、人参敗毒散の適応症とは異なります。
問題 患者、65歳。今日の午前に突然壮熱口渇、頭痛煩躁が現れ、その後昏迷し、腹痛、裏急後重、鮮紫膿血を下痢する、舌質紅絳、苔黄燥、脈滑数。診断すべきはどれか?
1.湿熱痢
2.寒湿痢
3.噤口痢
4.疫毒痢
5.どれも違う
回答→4
【解説】
⚫︎痢疾の共通症状: 「腹痛、裏急後重、鮮紫膿血を下痢する」は、下痢に膿血が混じり、腹痛や便意が残る感覚を伴う、痢疾の基本的な症状です。
⚫︎疫毒痢に特有の症状:
・発病の急激さ: 「今日の午前に突然」という発病の急驟さは、疫毒という強い邪気による発病を示唆します。
・全身の重篤な熱症状: 「壮熱口渇、頭痛煩躁」は、疫毒が体内に侵入し、清竅(頭部の感覚器官)を攻撃したり、心や血分を乱したりしている病理状態を反映しています。
・神志(精神)の異常: 「その後昏迷し」は、熱毒が心神を覆い、意識障害を引き起こしている重篤な状態です。
・舌脈: 「舌質紅絳、苔黄燥、脈滑数」は、体内の熱毒が非常に盛んであることを示す典型的な舌脈です。
・便の性状: 「鮮紫膿血」は、毒邪が腸道を強く灼傷し、気血を損傷していることを反映しています。
これらの特徴から、疫毒痢と診断できます。疫毒痢は、湿熱痢よりも発病が急で、全身症状が重篤であり、神志への影響が見られる点が異なります。
問題 腹痛が急に酷く現れる、得温痛減、遇寒更甚、口和不渇、溲清便溏、舌苔白膩、脈象沈緊。治療するために選ぶべき方剤はどれか?
1.附子理中丸
2.小建中湯
3.良附丸
4.良附丸合正気天香散
5.どれも違う
回答→4
【解説】
病名診断:腹痛
証候診断:寒邪内阻
患者の症状は、寒邪が体内に侵入して気の流れを阻害している寒邪内阻の病態を示しています。
⚫︎寒邪の証拠
・腹痛が急に酷く現れる: 急激な痛みは、寒邪による気の凝滞が原因であることが多いです。
・得温痛減、遇寒更甚: 温めると痛みが和らぎ、冷えると悪化するのは、寒邪の凝滞による典型的な症状です。
・口和不渇、溲清便溏: 口渇がなく、尿が澄んでいて、便がゆるいのは、体内に寒邪が盛んで、熱がないことを示します。
・舌苔白膩、脈象沈緊: 舌苔が白く膩(べったり)としており、脈が深く(沈)引き締まっている(緊)のは、寒凝と気の停滞を反映する典型的な舌脈です。
1.附子理中丸
脾腎陽虚による腹痛や虚寒痢に用いる方剤です。本症例のような急激な実証の腹痛には適しません。
2.小建中湯
中虚臓寒による虚証の腹痛に用いる方剤です。本症例は虚証ではなく実証です。
3.良附丸
寒邪による胃痛に用いる方剤ですが、単独では気の凝滞を改善する力が不十分な場合があります。
4.良附丸合正気天香散
寒邪による気の凝滞が腹痛の原因であるため、寒を散らす良附丸と、気を巡らせて痛みを止める正気天香散を組み合わせることで、病態に最も適した治療が可能です。
問題 泄瀉の初期における治療で適当でないものはどれか?
1.分利
2.消導
3.疏利
4.清化
5.固渋
回答→5
問題 一貫煎で脇痛を治療する効能はどれか?
1.疏肝理気
2.袪瘀通絡
3.清熱利湿
4.行気活血
5.養陰柔肝
回答→5
【解説】
一貫煎が適応する脇痛は、肝陰不足によるものです。
⚫︎病理: 肝の陰液が不足すると、肝を滋養することができなくなり、肝の機能が失調します。その結果、気の巡りも悪くなり、脇に痛みを引き起こします。
⚫︎特徴的な症状:
・陰虚の症状: 口や喉の乾燥、めまい、目がかすむ、舌が赤く苔が少ない、脈が細く速い(細弦数)といった症状を伴います。
・脇肋隠痛: 脇の痛みが激しいものではなく、シクシクと続く鈍い痛みです。
・疲労で痛みが悪化: 陰液不足による虚弱な状態のため、疲れると痛みがひどくなります。
⚫︎一貫煎の効能ー滋陰肝腎、疏肝理気
れは、肝の陰液を養い、肝の働きをなめらかにする養陰柔肝という治法に相当します。
問題 身目倶黄、黄色晦黯、食欲不振、精神疲労、畏寒、口渇はない、大便は堅くない、舌淡苔膩、脈濡緩。その治療方剤はどれか?
1.茵蔯蒿湯
2.茵蔯五苓散
3.茵蔯朮附湯
4.麻黄連翹赤小豆湯
5.梔子柏皮湯
回答→3
【解説】
病名診断:黄疸
「身目倶黄」という症状から、病名診断は黄疸です。
証候診断:陰黄
黄疸の弁証では、まず陽黄と陰黄を鑑別することが重要です。患者の症状は陰黄の特徴を多く示しています。
⚫︎陰黄の証拠
・黄色晦黯: 黄疸の色が鮮やかではなく、くすんで暗い色をしています。これは陰黄の最も特徴的な症状です。
・畏寒、口渇はない、大便は堅くない: これらは体内に寒湿が盛んで、熱がないことを示しています。
・食欲不振、精神疲労: 寒湿が脾胃を阻滞し、脾胃の運化機能が低下していることを示唆します。
・舌淡苔膩、脈濡緩: 舌が淡く、苔が膩(べったり)としており、脈が濡(じゅ、浮いて柔らかい)で緩いのは、寒湿内盛の典型的な舌脈です。
これらの症状を総合すると、陰黄と診断できます。陰黄の病理は、寒湿が脾胃を阻滞し、陽気の宣降(せんだい)を失調させることで、胆汁が体表に溢れ出ることにあります。
1.茵蔯蒿湯
熱が湿よりも重い熱重於湿の陽黄の治療方剤です。本症例のような寒湿の病態には適しません。
2.茵蔯五苓散
湿が熱よりも重い湿重於熱の陽黄の治療方剤です。本症例の陰黄には不適切です。
3.茵蔯朮附湯ー温陽健脾、利湿退黄
茵蔯朮附湯は、陰黄の治療に特化した方剤です。附子、乾姜、肉桂で陽気を温め、白朮で脾を健やかにし湿を取り除き、茵蔯蒿で黄疸を退散させます。これらの生薬の組み合わせにより、寒湿内盛による黄疸を根本から治療します。
4.麻黄連翹赤小豆湯
陽黄の初期で、表証を伴う場合に用いる方剤です。
5.梔子柏皮湯
陽黄の初期で、清熱利湿作用を強めるために用いる方剤です。
問題 患者、男、54歳。目黄身黄、その色は鮮明、発熱口渇し、心中が悶乱して不寧(心中懊憹)、悪心嘔吐、小便短少で黄、大便秘結、舌苔黄膩、脈弦数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.茵陳五苓散
2.茵陳蒿湯
3.甘露消毒丹
4.犀角散
5.大柴胡湯
回答→2
【解説】
病名診断:黄疸
「目黄身黄」という症状から、病名診断は黄疸です。
証候診断:陽黄・熱重於湿
患者の症状は、湿熱が体内に停滞する陽黄の中でも、特に熱が湿よりも盛ん(熱重於湿)な病態を示しています。
⚫︎陽黄の証拠
・黄色鮮明: 黄疸の色がくすんでおらず、鮮やかです。
・発熱口渇: 体内の熱が盛んであることを示します。
・大便秘結: 熱が津液を消耗させ、腸の働きを阻害しているためです。
・小便短少で黄: 湿熱が膀胱の気化を妨げ、水分代謝を悪化させています。
・舌苔黄膩、脈弦数: 舌苔が黄色く膩(べったり)としており、脈が速いのは、湿熱が盛んであることを示す典型的な舌脈です。
⚫︎熱重於湿の鑑別
陽黄には「熱重於湿」と「湿重於熱」があります。本症例では、「発熱口渇」「大便秘結」といった熱の症状が顕著であるため、熱重於湿と判断できます。一方、湿が重い場合は、頭が重く体がだるい、下痢や便が軟便であるといった症状が多く見られます。
1.茵陳五苓散
湿が熱よりも重い湿重於熱の陽黄に用いる方剤です。本症例の熱が重い病態には適しません。
2.茵陳蒿湯
茵陳蒿湯は、熱重於湿の陽黄に特化した代表的な方剤です。君薬の茵陳蒿で黄疸を退散させ、山梔子で熱を清め、大黄で便通を改善して熱と湿を体外へ排出します。これにより、体内の湿熱を根本から取り除きます。
3.甘露消毒丹
湿重於熱の陽黄に、茵陳五苓散と併用して用いることがあります。
4.犀角散
急黄(黄疸が急激に発症し、重篤な熱症状を伴う)や熱毒が血分に侵入した病態に用いる方剤です。
5.大柴胡湯
胆石など、胆道が塞がれたことによる病態に用いることがあります。
問題 身目倶黄、黄色鮮明、発熱口渇、口乾苦、脘腹脹満、悪心嘔吐、小便短少、色は赤黄で、大便秘結、舌苔黄膩、脈弦数。その治療方剤はどれか?
1.茵蔯蒿湯
2.茵蔯五苓散
3.茵蔯朮附湯
4.麻黄連翹赤小豆湯
5.梔子柏皮湯
回答→1
【解説】
1.茵蔯蒿湯
熱重於湿の陽黄に最も適した方剤です。
2.茵蔯五苓散
湿が熱よりも重い湿重於熱の陽黄に用いる方剤です。本症例の熱が重い病態には適しません。
3.茵蔯朮附湯
陽黄とは対照的な陰黄の治療方剤です。
4.麻黄連翹赤小豆湯
陽黄の初期で、表証を伴う場合に用いる方剤です。
5.梔子柏皮湯
陽黄の初期で、清熱利湿作用を強めるために用いる方剤です。
問題 脇肋の隠痛が長々と続く、痛みは疲れると悪化する、口乾咽燥、心中煩熱、頭暈目眩、舌紅少苔、脈細弦数。選ぶべき方剤はどれか?
1.旋覆花湯
2.柴胡疏肝散
3.一貫煎
4.帰脾湯
5.復元活血湯
回答→3
【解説】
病名診断:脇痛
証候診断:肝陰不足
患者の症状は、肝の陰液が不足している肝陰不足の病態を示しています。
⚫︎脇痛の特徴
・「隠痛が長々と続く」という、弱々しく持続的な痛みは虚証の特徴です。「痛みは疲れると悪化する」というのも、肝陰が不足して虚弱な状態であることを示唆します。
⚫︎陰虚の症状
・口乾咽燥、心中煩熱: 陰液の不足により、口や喉が乾燥し、体内の虚熱が原因で胸が煩わしく熱感を覚えます。
・頭暈目眩: 肝陰が不足して肝血が虚弱になると、頭や目を滋養できなくなり、めまいや目のかすみが生じます。
・舌紅少苔、脈細弦数: 舌が赤く、苔が少ないのは陰虚の典型的な舌象です。脈が細く(虚)、弦(肝の病)、速い(熱)のも、肝陰不足による虚熱を示しています。
1.旋覆花湯
瘀血停着による脇痛の治療方剤です。本症例の症状とは異なります。
2.柴胡疏肝散
肝気鬱結による脇痛の治療方剤です。痛みは脹痛が主で、情緒変動で悪化します。
3.一貫煎
肝陰不足による脇痛に最も適した方剤です。一貫煎は、大量の補陰薬(生地黄、枸杞子、沙参、麦門冬、当帰)に少量の疏肝理気薬(川楝子)を配合することで、陰液を補いながらも気の鬱滞を取り除くという特徴的な作用を持ちます。
4.帰脾湯
気血虧虚による心悸や不眠、脾不統血など、脾や心の病態を治療する方剤です。
5.復元活血湯
瘀血停着による脇痛で、痛みが激しい場合に用いる方剤です。
問題 下記の中で、陽黄と陰黄との鑑別要点でないものはどれか?
1.病程は比較的に長いか短いか
2.黄色が鮮明か晦暗か
3.小便が黄色か黄色ではないか
4.熱証か寒証か
5.虚証か実証か
回答→3
【解説】
陽黄と陰黄を鑑別する際には、黄疸の色の鮮やかさ、病程の長短、そして付随する熱症状(陽黄)と寒症状(陰黄)の有無を判断することが重要です。小便が黄色くなることは両者に共通する症状であるため、鑑別要点にはなりません。
問題 患者、脇肋が脹満して痛む、痛処不定、怒ると悪化、胸悶し善太息、噯気が頻発、苔薄白、脈弦。この治療で選用すべき治法はどれか?
1.疏肝理気
2.袪瘀通絡
3.清熱利湿
4.清熱利胆
5.養陰柔肝
回答→1
【解説】
患者の症状は、肝の気の流れが滞っている肝気鬱結の病態を示しています。
問題 外傷による血瘀による脇痛の治療に、選ぶべき方剤はどれか?
1.桃紅四物湯
2.血府逐瘀湯
3.復元活血湯
4.身痛逐瘀湯
5.補陽還五湯
回答→3
【解説】
1.桃紅四物湯
内科学では使用されていない方剤
2.血府逐瘀湯
心血瘀阻の胸痺、瘀血による発熱などに用いる方剤です。
3.復元活血湯
外傷による激しい脇痛、すなわち瘀血停着の脇痛に最も適した方剤です。内科学では瘀血停着の脇痛が酷い場合の治療方剤で、方剤学では打撲損傷で瘀血が脇下に溜り我慢できないほど脇痛を治療する方剤である
4.身痛逐瘀湯
瘀血停着による腰痛の治療方剤です。
5.補陽還五湯
中風の後遺症による半身不随など、気虚と血瘀が原因の病態に用いる方剤です。
問題 患者、女、39歳。身目どちらも発黄し、身体全体が不調、頭重四肢がだるい、口淡不渇、腹脹納呆、小便不利、便溏、舌苔厚膩、脈弦滑。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.王氏連朴飲
2.五味消毒飲
3.甘露消毒丹
4.茵陳朮附湯
5.茵陳五苓散
回答→5
【解説】
病名診断:黄疸
「身目どちらも発黄し」という症状から、病名診断は黄疸です。
証候診断:陽黄・湿重於熱
この症例は、黄疸の中でも陽黄に属し、特に湿邪が熱邪よりも重い(湿重於熱)病態を示しています。
1.王氏連朴飲
内科学では使用されていません。
2.五味消毒飲
陽水の湿毒や、熱毒による皮膚疾患(瘡瘍、癰疽)に用いる方剤です。
3.甘露消毒丹
湿重於熱の陽黄の治療に、茵陳五苓散と併用して用いられる方剤です。
4.茵陳朮附湯
陰黄の治療方剤です。本症例の陽黄には不適切です。
5.茵陳五苓散
茵陳五苓散は、湿重於熱の陽黄に特化した方剤です。茵陳蒿で黄疸を退散させ、五苓散で利水作用を高めることで、体内の湿邪を強力に排出します。
問題 脇肋の隠痛が長々と続く、痛みは疲れると悪化する、口乾咽燥、心中煩熱、頭暈目眩、舌紅少苔、脈細弦数。選ぶべき方剤はどれか?
1.旋覆花湯
2.柴胡疏肝散
3.一貫煎
4.帰脾湯
5.復元活血湯
回答→3
【解説】
病名診断:脇痛
証候診断:肝陰不足
1.旋覆花湯
瘀血停着による脇痛の治療方剤です。本症例の虚証の症状とは異なります。
2.柴胡疏肝散
肝気鬱結による脇痛の治療方剤です。痛みは張ったような痛みで、情緒変動で悪化します。
3.一貫煎
肝陰不足による脇痛に最も適した方剤です。
4.帰脾湯
気血不足による心脾両虚の病態に用いる方剤です。
5.復元活血湯
瘀血停着による激しい脇痛の治療方剤です。
問題 患者李様、男、76歳。眩暈耳鳴、頭痛且脹、煩労やカッとするたびに頭暈、頭痛が悪化し、時に顔面が紅潮し、急躁易怒となり、少寝多夢、口苦、舌質紅苔黄、脈弦。この治療で最も適切な方剤はどれか?
1.芎芷石膏湯
2.天麻鈎藤飲
3.大補元煎
4.半夏白朮天麻湯
5.竜胆瀉肝湯
回答→2
【解説】
病名診断:眩暈
「眩暈耳鳴、頭痛且脹」が主症状であることから、病名診断は眩暈です。
証候診断:肝陽上亢
患者の症状は、肝陽が頭部にまで上昇し、気を乱している肝陽上亢の病態を示しています。
⚫︎肝陽上亢の証拠
・眩暈耳鳴、頭痛且脹: 肝陽が上昇することで、頭部を突き上げ、めまい、耳鳴り、頭部の膨張感のある痛みを引き起こします。
・煩労やカッとするたびに悪化: ストレスや感情の変動(怒りなど)が肝陽をさらに上昇させるため、症状が悪化します。これは肝陽上亢の非常に特徴的な症状です。
・顔面紅潮、急躁易怒: 肝陽が上昇して頭部に集まるため、顔が赤くなり、イライラして怒りっぽくなります。
・少寝多夢、口苦: 肝陽の乱れが心神に影響し、不眠や多夢を引き起こします。また、肝胆の熱が上逆して口が苦くなります。
⚫︎舌脈
・舌質紅苔黄、脈弦: 舌が赤く、苔が黄色いのは熱証を、脈が弦を張っているのは肝の病変を反映しており、肝陽上亢の典型的な舌脈です。
1.芎芷石膏湯
風熱頭痛の治療方剤です。本症例は風熱ではなく肝陽上亢が主です。
2.天麻鈎藤飲ー平肝熄風、清熱活血、補益肝腎
天麻鈎藤飲は、肝陽上亢による眩暈や頭痛に最も適した方剤です。君薬である天麻、鈎藤、石決明が強力に肝陽を鎮め、内風を鎮めます。さらに、山梔子や黄芩で肝経の熱を清め、杜仲や桑寄生などで肝腎を補益することで、根本原因を治療します。
3.大補元煎
腎虚による頭痛の治療方剤です。本症例の肝陽上亢の病態には適しません。
4.半夏白朮天麻湯
痰濁が原因の頭痛や眩暈に用いる方剤です。本症例のような肝陽上亢の熱症状とは異なります。
5.竜胆瀉肝湯
肝胆の湿熱や火盛を治療する方剤です。肝陽上亢の症状も一部見られますが、竜胆瀉肝湯はより湿熱や火邪が盛んな場合に適します。本症例は肝陽上亢が主体です。
問題 六淫外襲で、上犯巓頂、清陽の気が受阻により起こる頭痛の中でどの外邪が一番多いか?
1.風邪
2.寒邪
3.暑邪
4.湿邪
5.熱邪
回答→1
問題 下記の中で、眩暈の病機に属さないのはどれか?
1.肝陽上亢
2.気血虧虚
3.腎精不足
4.痰濁中阻
5.外邪阻竅
回答→5
【解説】
眩暈は内傷が主たる病因であり、体内の機能失調によって引き起こされることが多いため、外邪阻竅は眩暈の病機に属しません。一方、頭痛は外感と内傷の両方が病因となり、外邪(特に風邪)が頭部を侵すことで起こることが多いため、両者の鑑別が重要になります。
問題 患者、眩暈耳鳴、頭脹痛、煩労或いは脳怒によって頭暈・頭痛が悪化する。面色は紅潮し、急躁易怒、少寝多夢、口苦、舌質紅、苔黄、脈弦。この治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.天麻鈎藤飲
2.杞菊地黄丸
3.半夏白朮天麻湯
4.大補元煎
5.右帰丸
回答→1
【解説】
病名診断:眩暈
証候診断:肝陽上亢
1.天麻鈎藤飲ー平肝熄風、清熱活血、補益肝腎
天麻鈎藤飲は、肝陽上亢による眩暈や頭痛に最も適した方剤です。天麻、鈎藤、石決明が肝陽を鎮めて内風を鎮め、山梔子や黄芩で肝経の熱を清めます。また、牛膝は佐使薬として、上昇しすぎた血液を下方へ導く「引血下行」作用があり、肝陽上亢の病態に非常に効果的です。
2.杞菊地黄丸
肝陽上亢が改善した後に、腎陰を補い治療効果を安定させるために用いる方剤です。
3.半夏白朮天麻湯
痰濁が原因の眩暈や頭痛に用いる方剤です。
4.大補元煎
腎虚による頭痛の治療補剤です。
5.右帰丸
腎陽虚による眩暈や頭痛の治療方剤です。本症例の熱症状とは異なります。
問題 患者、女、45歳。このところ気候が急に冷えたにも拘らず、養生を怠ったため、悪風畏寒、時に頭痛、痛みは項背まで連なる、風に当たるとなおさら痛む、不渇などが現れ、苔薄白、脈浮緊。弁証すべきのはどれか?
1.風熱頭痛
2.風湿頭痛
3.風寒頭痛
4.痰濁頭痛
5.腎虚頭痛
回答→3
【解説】
⚫︎「頭痛の弁証」は、まず、外感と内傷を鑑別することが重要です。
・外感: 発病が急で、悪寒発熱といった表証を伴います。
・内傷: 虚証(腎虚)や虚実混雑(痰濁、肝陽)があり、病程が長いのが特徴です。
問題 患者、男、64歳。眩暈して頭が重くボーっとする、胸悶悪心、少食多寝、舌苔白膩、脈象濡滑。この治療で最も適切な方剤はどれか?
1.小半夏加茯苓湯
2.二陳湯
3.温胆湯
4.天麻鈎藤飲
5.半夏白朮天麻湯
回答→5
【解説】
病名診断:眩暈
証候診断:痰濁中阻
患者の症状は、脾の機能失調により生じた痰濁が中焦に停滞し、清陽の気が頭部に昇るのを阻害している痰濁中阻の病態を示しています。
1.小半夏加茯苓湯
脾陽虚弱による痰飲の治療方剤です。本症例の痰濁中阻とは病態が異なります。
2.二陳湯
痰湿を化する基本的な方剤ですが、眩暈に対する専門的な作用は強くありません。
3.温胆湯
痰熱による不眠や耳鳴に用いる方剤です。本症例の寒湿の病態には適しません。
4.天麻鈎藤飲
肝陽上亢による眩暈の治療方剤です。発熱やイライラといった熱証が主で、本症例の痰濁による症状とは異なります。
5.半夏白朮天麻湯ー燥湿化痰、平肝熄風
半夏白朮天麻湯は、痰濁による眩暈や頭痛に最も適した方剤です。君薬の半夏と天麻が痰濁を化し、風を鎮めてめまいを止めます。臣薬の白朮は脾の働きを助け、湿を取り除くことで痰の生成を抑えます。さらに、茯苓や橘紅などが痰湿を化し、気の巡りを改善します。
問題 眩暈で頭重、ぼうっとする、頭目脹痛、心煩口苦、渇不欲飲、舌苔黄膩、脈弦滑。属する証はどれか?
1.痰熱中阻
2.痰濁中阻
3.肝陽上亢
4.腎陰虧虚
5.瘀血化熱
回答→1
【解説】
1.痰熱中阻
眩暈、頭目脹痛、心煩口苦、舌苔黄膩、脈弦滑といった症状と一致します。
2.痰濁中阻
眩暈、頭重頭痛、白膩苔、滑脈といった症状が特徴ですが、本症例にある黄膩苔や頭目脹痛、心煩口苦などの熱症状が見られません。
3.肝陽上亢
眩暈、頭目脹痛、脈弦といった症状は共通しますが、本症例にある黄膩苔や「頭重、ぼうっとする」といった痰湿の症状が見られません。
4.腎陰虧虚
眩暈、めまい、腰膝酸軟、耳鳴といった虚証の症状が主であり、黄膩苔や弦数脈は見られません。
5.瘀血化熱
眩暈の病理には属しません。固定痛や刺痛と共に発熱などの症状を呈します。
⚫︎痰熱中阻と痰濁中阻の鑑別:
・共通点: どちらも痰濁が原因であるため、「眩暈、頭重、ぼうっとする、膩苔」といった症状が共通して見られます。
・相違点: 痰熱中阻は痰濁が熱化したもので、熱症状(頭目脹痛、心煩口苦、黄膩苔)が顕著です。一方、痰濁中阻は熱症状がなく、白膩苔や頭重頭痛が主症状です。
・痰熱中阻: 温胆湯(黄連、黄芩を加えて)などで、熱を清め、痰を化します。
・痰濁中阻: 半夏白朮天麻湯などで、湿を燥かし、痰を化し、脾を健やかにします。
問題 眩暈、労累即発、面色晄白、唇甲不華、失眠健忘、食少納呆、舌質淡、脈細弱。その治法として採用すべきはどれか?
1.補脾益気、和胃化湿
2.補脾益腎、益気和営
3.補養気血、健運脾胃
4.益気養陰、健脾和胃
5.補中益気、昇清挙陥
回答→3
【解説】
病名診断:眩暈
証候診断:気血虧虚
・「労累即発」: この症状は、気血虧虚による眩暈の最も重要な鑑別点です。疲れると症状が悪化する場合は、気血不足を疑うべきです。
※労累即発とは、疲れるとすぐに症状が現れる、または悪化するという意味です。
・眩暈の鑑別: 眩暈は、気血虧虚のほかに、肝陽上亢、痰濁中阻、腎精不足など、様々な原因で引き起こされます。症状を正確に鑑別することが重要です。
・気血虧虚の治療: 気血を補うだけでなく、その生成源である脾胃の働きを改善することが根本治療となります。いただいた解説にある通り、帰脾湯は脾の働きを助け、気血を補うことでこの病態を治療する代表的な方剤です。
問題 患者、男、62歳。2年前から高血圧。最近意にそぐわない事があった後から頭痛目弦、心煩易怒、失眠、面紅口苦が現れる。苔薄黄、脈弦有力。この場合の治法はどれか?
1.疏散風熱
2.平肝潜陽
3.養陰補腎
4.化痰降逆
5.清熱化痰
回答→2
【解説】
病名診断:頭痛
証候診断:肝陽頭痛
・頭痛の鑑別: 頭痛の弁証では、外感と内傷を鑑別することが重要です。この症例は、高血圧や精神的なストレスといった内部の病因が引き金となっているため、内傷と判断できます。
・肝陽頭痛の特徴: 肝陽頭痛の場合、頭痛と眩暈が同時に見られることが多く、感情の変化によって症状が誘発・悪化する点が特徴です。脈弦も重要な診断基準となります。
・内傷の頭痛には実証、虚証、虚実混雑のタイプがあり、肝陽頭痛は虚実混雑の頭痛に属します。
問題 患者、頭痛且空。眩暈、腰痛痠軟、面白、畏寒、四肢不温を伴う、舌淡、脈沈細。この治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.天麻鈎藤飲
2.杞菊地黄丸
3.半夏白朮天麻湯
4.大補元煎
5.右帰丸
回答→5
【解説】
病名診断:頭痛
症状の記述で「頭痛」が最初に挙げられていることから、病名診断は頭痛とします。
証候診断:腎虚頭痛・腎陽虚
患者の症状は、腎の精気、特に腎陽が不足している腎虚頭痛・腎陽虚の病態を示しています。
・「頭痛且空」: 頭痛が空虚感や脱力感を伴うのは、腎精が不足して脳(髄海)を養えないことが原因です。これは腎虚頭痛の最も特徴的な症状です。
・「眩暈、腰痛痠軟」: 腎は腰を主るため、腎が虚弱になると腰がだるく、力がなくなります。また、腎精が不足するとめまいも引き起こされます。
・「面白、畏寒、四肢不温」: 顔色が悪く、寒がり、手足が冷たいのは、腎陽の不足により体全体が温まらないことを示します。
・「舌淡、脈沈細」: 舌の色が薄いのは陽虚と血虚を示し、脈が深く(沈)、細いのは、腎陽の虚弱を反映する典型的な舌脈です。
治法と方剤
・病理: 腎陽虚が根本にあり、腎の温煦作用が低下して腎精がうまく生成・補充されないため、脳を養えず頭痛やめまいが発生します。
・治法: 腎精を補い、同時に腎陽を温めることが重要です。
・代表方剤:腎虚頭痛の一般的な治療には大補元煎が用いられますが、この症例では寒症状(畏寒、四肢不温)が顕著であるため、温陽作用の強い右帰丸がより適しています。
1.天麻鈎藤飲
肝陽上亢による頭痛や眩暈に用いる方剤です。本症例のような虚証・寒証の病態には適しません。
2.杞菊地黄丸
肝腎陰虚に用いる方剤で、陽虚には不適切です。
3.半夏白朮天麻湯
痰濁による頭痛や眩暈に用いる方剤です。本症例の虚証とは異なります。
4.大補元煎
腎虚頭痛の治療補剤ですが、腎陽を温める力は弱いです。
5.右帰丸
腎精を補いながら、腎陽を温める力が非常に強いため、本症例の腎陽虚が顕著な頭痛に最も適しています。熟地黄、山薬、山茱萸などで腎精を補うとともに、肉桂、炮附子といった温陽薬を配合することで、腎陽虚の治療に特化しています。
問題 腎陽衰微の水腫の主な症状はどれか?
1.遍身浮腫、皮膚は光沢があり、胸脘痞悶、尿が赤く便が堅い
2.全身水腫、按ずると陥没する、身体困重、舌苔白膩
3.全身水腫、小便不利、悪寒発熱、四肢関節痠楚
4.腰より下の浮腫が甚だしい、脘腹脹満、食少便溏、面色萎黄、神疲肢冷、舌淡苔白膩、脈沈緩
5.腰より下の浮腫が甚だしい、心悸気促、腰部冷痛痠重、寒さに怯えて精神疲労し、舌質淡胖、苔白、脈沈細
回答→5
【解説】
水腫とは、体内の水分代謝失調により、水分が組織間に停留して浮腫を生じる病態です。中医学では、その病因や症状の性質から主に陽水と陰水に分けられます。腎陽衰微による水腫は、陰水に属します。
1.遍身浮腫、皮膚は光沢があり、胸脘痞悶、尿が赤く便が堅い
湿熱が原因の陽水(熱証)の症状です。
2.全身水腫、按ずると陥没する、身体困重、舌苔白膩
水湿が原因の陽水(実証)の症状です。
3.全身水腫、小便不利、悪寒発熱、四肢関節痠楚
風水が原因の陽水(表証)の症状です。
4.腰より下の浮腫が甚だしい、脘腹脹満、食少便溏、面色萎黄、神疲肢冷、舌淡苔白膩、脈沈緩
脾陽不足による陰水の症状です。
5.腰より下の浮腫が甚だしい、心悸気促、腰部冷痛痠重、寒さに怯えて精神疲労し、舌質淡胖、苔白、脈沈細
腎陽衰微による陰水の症状で、腎陽不足の典型的な症状が揃っています。
治法と方剤
・病理: 腎陽が衰微し、腎の気化作用が低下して膀胱の水分代謝が失調し、水湿が停滞します。
・治法: 温補腎陽、利水消腫。腎の陽気を温め、水分代謝を促進します。
・代表方剤:済生腎気丸、真武湯
・済生腎気丸: 補陽剤として腎陽を温め、利水消腫の効能があります。
・真武湯: 温化水湿剤として陽気を温めて利水作用を促進します。
問題 患者、全身の浮腫、皮膚の色が光亮、胸腹痞悶し、煩悶口渇、小便短赤、大便乾結、苔黄膩、脈沈数。その治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.疏鑿飲子
2.実脾散
3.真武湯
4.五皮飲合胃苓湯
5.参苓白朮散
回答→1
【解説】
病名診断:水腫・陽水
・「全身の浮腫」という症状から、病名診断は水腫です。
・「神疲・畏寒など」といった陰水の特徴的な症状が見られないことから、陽水と判断できます。
証候診断:湿熱壅盛
・「全身の浮腫、皮膚の色が光亮」: 湿熱が肌膚に停滞し、全身に浮腫が生じ、皮膚にツヤが出てきます。これは湿熱壅盛による陽水の特徴です。
・「胸腹痞悶し、煩悶口渇」: 湿熱が中焦(胸腹部)に停滞し、気の流れを阻害するため、胸や腹が重苦しく、熱が原因で口渇や胸の不快感が生じます。
・「小便短赤、大便乾結」: 湿熱が膀胱や大腸に停滞するため、尿の量が少なく色が濃くなり、便は乾燥して出にくくなります。
・苔黄膩: 舌苔が黄色く油っぽいのは、湿と熱が結びついている典型的な舌象です。
・脈沈数: 脈が深く(沈)速い(数)のは、体内に熱邪が盛んであることを反映しています。
1.疏鑿飲子
陽水の湿熱壅盛の治療方剤です。君薬の商陸が瀉下作用で水湿を排出し、羌活・秦艽などが疏風発表作用で体表の水湿を排泄します。本症例の病態に最も適しています。
2.実脾散
陰水の脾陽虚衰の治療方剤です。本症例のような熱証には適しません。
3.真武湯
陰水の腎気衰微の治療方剤です。陽虚水氾の病態に用いるため、本症例の熱証には不適切です。
4.五皮飲合胃苓湯
陽水の水湿浸漬の治療方剤です。湿邪が主で熱邪が顕著でない場合に用います。
5.参苓白朮散
脾胃虚弱による浮腫の治療方剤であり、本症例の湿熱の実証とは異なります。
問題 患者、男、27歳。2日前に汗をかき風に当たり、頭身酸痛、悪寒発熱、咽痛が現れ、さらに顔面及び両下肢に水腫が見られるようになった、尿少黄赤、舌暗紅、苔薄黄、脈浮滑数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.真武湯
2.生脈散
3.五皮飲
4.越婢加朮湯
5.麻黄連翹赤小豆湯
回答→4
【解説】
病名診断:水腫・陽水
・「顔面及び両下肢に水腫」という症状から、病名診断は水腫です。
・「悪寒発熱」という表証を伴うため、陽水と判断できます。
証候診断:風水氾濫
患者の症状は、外感の風邪が体表を襲い、肺の宣発・粛降機能を阻害したため、水分代謝が失調して水腫が生じた風水氾濫の病態を示しています。
⚫︎病因: 「汗をかき風に当たり」という情報から、外部の風邪が原因であることがわかります。
⚫︎風水氾濫の証拠:
・「頭身酸痛、悪寒発熱」: 風邪が体表を襲ったことによる、風邪の表証です。
・「顔面及び両下肢に水腫」: 風邪によって肺の通調水道機能が失調し、水分が停滞して水腫が発生します。
⚫︎熱症状:
・「咽痛が現れ、尿少黄赤」: 風邪が熱化し、咽喉に熱がこもり、尿が少なく赤くなります。
・「舌暗紅、苔薄黄、脈浮滑数」: 舌が暗紅色なのは熱や瘀血、苔が薄黄色なのは熱邪を反映し、脈が浅く速い(浮数)のは、表証と熱邪が同時に存在することを示しています。
この病態の治療は、発越水気、兼清裏熱です。水気を発散させ、同時に内部の熱も清めることが重要です。
1.真武湯
陰水の腎気衰微に用いる温陽利水の方剤です。本症例のような表証や熱証には適しません。
2.生脈散
気陰両虚の症状に用いる方剤であり、水腫の治療には使用しません。
3.五皮飲
水湿浸漬の陽水に用いる方剤で、表証が顕著でない場合に適しています。本症例のような風邪の表証と熱証には対応できません。
4.越婢加朮湯
風水氾濫による水腫の代表的な方剤です。君薬の麻黄が発汗利水作用で体表の水湿を排泄し、石膏が清熱作用で内部の熱を清めます。
5.麻黄連翹赤小豆湯
陽黄の初期や湿毒侵淫による病態に用いる方剤であり、本症例の病態には適しません。
ポイント
・水腫の鑑別: 悪寒発熱といった表証を伴う水腫は、風邪が原因の風水氾濫と診断します。
問題 患者、全身の水腫、小便短少で、身体重困、胸悶納呆、泛悪、苔白膩、脈沈弦。その治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.疏鑿飲子
2.実脾散
3.真武湯
4.五皮飲合胃苓湯
5.参苓白朮散
回答→4
【解説】
病名診断:水腫・陽水
・「全身の水腫」と「小便短少」という症状から、病名診断は水腫です。
・「神疲・畏寒など」の陰水の特徴的な症状が見られないことから、陽水と判断できます。
証候診断:水湿浸漬
・「身体重困、胸悶納呆、泛悪」: これらは水湿浸漬の典型的な症状です。湿邪が重く停滞する性質(重困)と、中焦に阻滞して気の流れを妨げる症状(胸悶、食欲不振、吐き気)を反映しています。
・苔白膩: 舌苔が白く油っぽいのは、水湿が体内に停滞していることを示す典型的な舌象です。
・脈沈弦: 脈が深く(沈)弦(気の鬱滞や肝の病)を張っているのは、水湿による気の流れの阻害を反映しています。
治法
この病態の治療は、理気利湿、行気消腫です。気の流れを整え、湿邪を排出することが重要です。
1.疏鑿飲子
陽水の湿熱壅盛に用いる方剤です。本症例のような熱症状(煩悶、口渇、黄膩苔など)がないため不適切です。
2.実脾散
陰水の脾陽虚衰に用いる方剤です。本症例のような陽水には適しません。
3.真武湯
陰水の腎気衰微に用いる方剤です。温陽作用が主であり、本症例の病態には適しません。
4.五皮飲合胃苓湯
・陽水の水湿浸漬に最も適した方剤です。五皮飲で皮膚からの水湿排出を促し、胃苓湯で脾胃の機能を整え、水湿の根本原因を治療します。
・五皮飲: 茯苓皮、陳皮、生姜皮、大腹皮、桑白皮といった、皮の利水作用を持つ生薬で構成され、皮膚からの水湿排出を助けます。
5.参苓白朮散
脾胃虚弱による浮腫の治療方剤です。本症例の湿濁が盛んな実証とは異なります。
問題 患者、男、28歳。朝起床時に頭面部の浮腫が現れてから1年、甚だしいと下肢も腫脹する、神疲乏力、納呆便溏、舌は淡胖で歯痕があり、苔薄膩、脈弱。この弁証はどれに属するか?
1.脾陽不足
2.水湿浸漬
3.湿熱壅盛
4.腎気虚弱
5.脾虚失運
回答→5
【解説】
病名診断:水腫
証候診断:陰水 脾気不足
治法と方剤
・病理: 脾気虚が根本にあり、水液の運化と昇清の機能が失調し、水湿が停滞します。
・治法: 健脾益気、和胃滲湿。脾の働きを健やかにし、気を補い、胃を調和させ、湿邪を排出します。
・代表方剤: 参苓白朮散の加減。
ポイント
・「朝起床時の頭面部浮腫」という症状は、脾の昇清機能が失調していることを示しており、脾虚失運の診断において最も重要なポイントです。
問題 脾陽虚衰の水腫の主な症状はどれか?
1.遍身浮腫、皮膚は光沢があり、胸脘痞悶、尿が赤く便が堅い
2.全身水腫、按ずると陥没する、身体困重、舌苔白膩
3.全身水腫、小便不利、悪寒発熱、四肢関節痠楚
4.腰より下の浮腫が甚だしい、脘腹脹満、食少便溏、面色萎黄、神疲肢冷、舌淡苔白膩、脈沈緩
5.腰より下の浮腫が甚だしい、心悸気促、腰部冷痛痠重、寒さに怯えて精神疲労し、舌質淡胖、苔白、脈沈細
回答→4
問題 中風で気虚血瘀の者を治療するのに、選ぶべき方剤はどれか?
1.桃紅四物湯
2.血府逐瘀湯
3.復元活血湯
4.身痛逐瘀湯
5.補陽還五湯
回答→5
【解説】
病名診断:中風後遺症
証候診断:気虚血瘀
⚫︎病理: 中風の後遺症では、脳や経絡が損傷され、気の流れと血の流れが阻害されます。特に高齢者では、もともとの気虚(気の不足)に加えて、病後の気血の消耗から、気の流れが悪くなって血が滞る気虚血瘀の病態が発生します。
⚫︎特徴的な症状:
・気虚: 疲労感、だるさ、顔色の蒼白さ、息切れなど。
・血瘀: 刺すような痛み、舌の暗紫、脈の渋りなど。
・これらが合わさることで、半身不随や言語障害などの後遺症を引き起こします。
1.桃紅四物湯
内科学では使用されていません。
2.血府逐瘀湯
胸部の瘀血による胸痺や、瘀血による発熱に用いる方剤です。気虚を補う作用は強くありません。
3.復元活血湯
外傷による脇痛、特に瘀血停着が激しい場合に用いる方剤です。
4.身痛逐瘀湯
瘀血停着による腰痛に用いる方剤です。
5.補陽還五湯
中風後遺症の気虚血瘀に特化した方剤です。
・君薬として大量の生黄耆を配合しているのが最大の特徴です。
・生黄耆: 強い補気作用を持ち、「気旺んなれば血行る(気が盛んになれば血が巡る)」という原則に基づき、気の推動力を強めることで血行を改善します。
・当帰、赤芍、地竜、川芎、桃仁、紅花: これらの生薬が、当帰の補血活血作用を助け、経絡を通し、瘀血を強力に取り除きます。
生黄耆 当帰 赤芍 川芎 桃仁 紅花 地竜
問題 患者、女、45歳。平素より頭暈頭痛があり、今朝突然に意識が朦朧として倒れ、人事不省となる、顎関節を堅く閉じ、口をつむぎ開かない、両手は固く握り、大小便閉、肢体は強直して痙攣。今は面赤身熱、気粗口臭、躁擾不寧、苔黄膩、脈弦滑数。この治法はどれか?
1.祛風除痰、宣竅通絡
2.平肝潜陽、化痰開竅
3.豁痰熄風、辛温開竅
4.清肝熄風、辛涼開竅
5.滋陰潜陽、熄風通絡
回答→4
【解説】
病名診断:中風・中臓腑
「突然に意識が朦朧として倒れ、人事不省となる」という症状から、病名診断は中風・中臓腑です。
証候診断:陽閉
患者の症状は、中風の中でも陽閉と呼ばれる、熱と邪気が体の要所を塞いでいる病態を示しています。
⚫︎中風・中臓腑の証拠
・「顎関節を堅く閉じ、口をつむぎ開かない、両手は固く握り、大小便閉、肢体は強直して痙攣」: これらの症状は、邪気が経絡を強く塞ぎ、身体の動きを阻害している「閉証」の特徴です。特に、身体が硬直して開かないという症状は陽閉に特有のものです。
⚫︎陽閉の証拠
・面赤身熱: 熱邪が盛んで、顔が赤く体が熱くなります。
・気粗口臭、躁擾不寧: 邪熱が心神を乱すことで、呼吸が荒く、イライラして落ち着きがなくなります。
・苔黄膩、脈弦滑数: 舌苔が黄色く油っぽいのは痰熱、脈が速く、弦を張り、滑らかであるのは肝陽と痰熱が盛んであることを反映しています。
治法と方剤
・病理: 陽昇風動により気血が上逆し、痰火を伴って清らかな竅を覆い塞いでいる状態です。
・治法: この病態の治療は、肝の熱を清め、内風を鎮め(清肝熄風)、辛涼な生薬で竅を開く(開竅)ことが重要です。
・代表方剤:局方至宝丹、安宮牛黄丸は辛涼開竅の代表的な方剤です。
ポイント
⚫︎中風の鑑別: 中風の治療では、まず中臓腑か中経絡かを鑑別し、次に中臓腑の場合は「閉証」か「脱証」かを判断します。そして、閉証の場合は「陽閉」か「陰閉」かを鑑別することが極めて重要です。
⚫︎陽閉と陰閉の鑑別:
・陽閉: 熱証を伴い、身体が硬直して開かない。面赤身熱、脈弦滑数などが特徴です。
・陰閉: 寒証を伴い、身体が弛緩して開かない。面色蒼白、手足の冷え、脈沈緩などが特徴です。
問題 下記の中で、中風の陽閉と陰閉とを弁別するための主な根拠でないのはどれか?
1.顔面潮紅と面白唇暗
2.躁動不安と静かつ煩躁ではない
3.舌苔白膩と舌苔黄膩
4.脈沈滑緩と脈弦滑数
5.肢体軟癱と肢体強痙
回答→5
【解説】
中風の中でも、意識障害を伴う重篤な状態を中臓腑と呼びます。中臓腑はさらに「閉証」と「脱証」に分類され、閉証は「陽閉」と「陰閉」に分けられます。
「肢体軟癱と肢体強痙」は、中風の中臓腑の病態を、生命力が失われた脱証と、邪気が塞いでいる閉証に分けるための鑑別点です。したがって、閉証の内部にある陽閉と陰閉を区別するための根拠ではありません。
問題 患者、年齢は70歳を超える。肥満体質で常に眩暈がおきる、最近眩暈が酷くなり、頭脹痛、煩躁、神志ははっきりしている、面色潮紅、手足がわずかに震える、舌紅少苔、脈弦。まず考慮するべき病証はどれか?
1.風中経絡
2.肝陽頭痛
3.中風陽閉
4.中風先兆
5.肝風顫証
回答→5
【解説】
病名診断:顫証(せんしょう)
「手足がわずかに震える」が主症状であることから、病名診断は顫証です。
証候診断:風陽内動証
患者の症状は、肝陽が亢進し、それが熱化して内風(肝風)を生じ、揺れ動いている風陽内動証の病態を示しています。
・「常に眩暈がおきる、最近眩暈が酷くなり、頭脹痛、煩躁、面色潮紅」: これは肝陽上亢の典型的な症状です。眩暈が酷くなり、頭痛が脹るように痛み、イライラしやすくなるのは、肝陽が上逆していることを示しています。
・「手足がわずかに震える」: これは内風(肝風)の発生による症状で、顫証の最も重要な特徴です。
・「神志ははっきりしている」: この点が、意識を失う中風・中臓腑と大きく異なります。
・「舌紅少苔」: 陰虚や熱盛を反映しています。
・「脈弦」: 肝の病変、特に肝陽上亢を反映しています。
ポイント
・顫証の定義: 「顫」とは、震え動く状態を指し、顫証は頭や手足の震えを主症状とする病証です。
・顫証と中風の鑑別: どちらも「風」と関連が深く、震えの症状が見られることがあります。しかし、本症例では「神志ははっきりしている」ことから、意識障害を伴う中風ではないと判断できます。
・顫証の病証: 顫証には「風陽内動証」のほかにも、「痰熱風動証」「気血虧虚証」など五つの証候があります。本症例は、肝陽上亢の症状から、風陽内動証に該当します。
1.風中経絡
突然発症し、口眼歪斜などの麻痺症状を伴います。本症例のような軽度の震えとは異なります。
2.肝陽頭痛
頭痛と眩暈が主症状で、震えを伴うことはありますが、病証の主徴ではありません。
3.中風陽閉
突然倒れて意識を失い、身体が硬直します。本症例のように「神志ははっきりしている」状態とは明らかに異なります。
4.中風先兆
中風の予兆を指す言葉ですが、病証そのものを指すものではありません。
5.肝風顫証
「顫証」は頭や手足が震えることを主症状とする病証です。本症例の「手足がわずかに震える」という症状に最も合致し、肝陽上亢が進んで内風を生じた「風陽内動証」に該当します。
問題 患者、男、27歳。2日前に汗をかき風に当たり、頭身酸痛、悪寒発熱、咽痛が現れ、さらに顔面及び両下肢に水腫が見られるようになった、尿少黄赤、舌暗紅、苔薄黄、脈浮滑数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.真武湯
2.生脈散
3.五皮飲
4.越婢加朮湯
5.麻黄連翹赤小豆湯
回答→4
【解説】
病名診断:水腫・陽水
・「顔面及び両下肢に水腫」という症状から、病名診断は水腫です。
・「悪寒発熱」という表証を伴うため、陽水と判断できます。
証候診断:風水氾濫
患者の症状は、外部の風邪が体表を襲い、水分代謝を司る肺の機能が失調したことで水腫が生じた風水氾濫の病態を示しています。
⚫︎病因: 「汗をかき風に当たり」という情報から、外邪(風邪)の侵入が原因であることがわかります。
⚫︎風水氾濫の証拠:
・「頭身酸痛、悪寒発熱」: これは風邪が体表に停滞していることによる、風邪の表証です。
・「顔面及び両下肢に水腫」: 風邪により肺の宣発粛降機能が阻害され、水分が停滞して浮腫が発生します。
⚫︎風熱の証拠:
・「咽痛が現れ、尿少黄赤」: 風邪が熱化し、咽の痛みや、尿が少なく色が濃くなるといった熱症状が現れます。
・「舌暗紅、苔薄黄、脈浮滑数」: 舌の色が暗紅色なのは熱や瘀血、苔が薄黄色なのは熱邪を反映し、脈が速い(数)のは熱証を示しています。
治法と方剤
・治法: この病態の治療は、発越水気、兼清裏熱です。体表の水気を発散させ、同時に内部の熱を清めることが重要です。
・代表方剤: 越婢加朮湯
1.真武湯
陰水の腎気衰微に用いる温陽利水の方剤です。本症例のような表証や熱証には適しません。
2.生脈散
気陰両虚の治療に用いる方剤であり、水腫の治療には使用しません。
3.五皮飲
陽水の水湿浸漬に用いる方剤で、表証が顕著でない場合に適しています。
4.越婢加朮湯
風水氾濫による水腫の代表的な方剤です。発汗作用を持つ麻黄と清熱作用を持つ石膏を組み合わせることで、表邪を解くとともに内部の熱を清めることができます。
5.麻黄連翹赤小豆湯
湿毒侵淫による陽黄や水腫に用いる方剤であり、本症例の病態には適しません。
問題 患者、女、45歳。平素より頭暈頭痛があり、今朝突然に意識が朦朧として倒れ、人事不省となる、顎関節を堅く閉じ、口をつむぎ開かない、両手は固く握り、大小便閉、肢体は強直して痙攣。今は面赤身熱、気粗口臭、躁擾不寧、苔黄膩、脈弦滑数。この治法はどれか?
1.祛風除痰、宣竅通絡
2.平肝潜陽、化痰開竅
3.豁痰熄風、辛温開竅
4.清肝熄風、辛涼開竅
5.滋陰潜陽、熄風通絡
回答→4
【解説】
病名診断:中風・中臓腑
「突然に意識が朦朧として倒れ、人事不省となる」という症状から、中風・中臓腑と診断できます。
証候診断:陽閉
患者の症状は、中風の中でも熱と邪気が体の要所を塞いでいる陽閉の病態を示しています。
⚫︎中風・中臓腑の閉証の特徴:
・「顎関節を堅く閉じ、口をつむぎ開かない、両手は固く握り、大小便閉、肢体は強直して痙攣」。これらの症状は、邪気が経絡を強く塞ぎ、身体が硬直する「閉証」に特有のものです。
⚫︎陽閉の証拠:
・「面赤身熱、気粗口臭、躁擾不寧」:顔面が赤く体が熱い、呼吸が荒く口臭がある、イライラして落ち着かないといった症状は、陽気や邪気が過剰となり、熱が盛んになっていることを示しています。
・「苔黄膩、脈弦滑数」:舌苔が黄色く油っぽいのは痰熱、脈が速く弦を張り滑らかであるのは、肝陽と痰熱が盛んであることを反映しています。
1.祛風除痰、宣竅通絡
中風後遺症の「風痰阻絡」による言語障害の治法です。代表方剤は解語丹です。
2.平肝潜陽、化痰開竅
中風後遺症の「肝陽上亢・痰邪阻竅」による言語障害の治法です。代表方剤は天麻鈎藤飲や鎮肝熄風湯です。
3.豁痰熄風、辛温開竅
中風・中臓腑の陰閉の治法です。本症例のような熱証とは異なります。代表方剤は蘇合香丸合滌痰湯です。
4.清肝熄風、辛涼開竅
中風・中臓腑の陽閉に最も適した治法です。本症例のすべての熱症状や硬直症状と一致します。
5.滋陰潜陽、熄風通絡
中風後遺症の「肝陽上亢・脈絡瘀阻」による半身不随の治法です。代表方剤は鎮肝熄風湯加減や天麻鈎藤飲です。
ポイント
・中風の鑑別: 中風の治療では、まず中臓腑か中経絡かを鑑別し、次に中臓腑の場合は「閉証」か「脱証」かを判断します。そして、閉証の場合は陽閉か陰閉かを鑑別することが極めて重要です。
・陽閉と陰閉の鑑別: 陽閉は熱証を伴うのに対し、陰閉は寒証を伴います。本症例の「面赤身熱」や「苔黄膩」といった症状は、陽閉の明確な根拠となります。