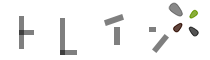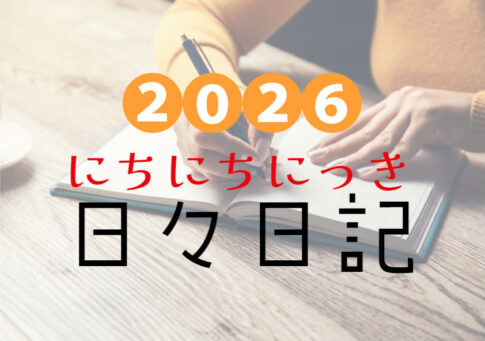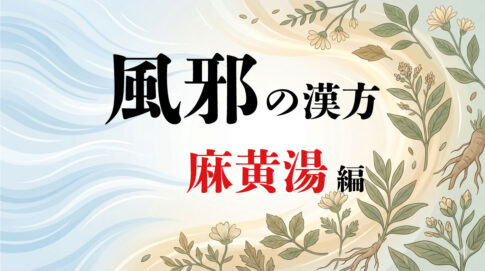問題 盗汗の臨床症状はどれか?
1.大汗が淋漓で、声低息短、精神疲弊、四肢厥冷を伴い、脈微欲絶
2.白昼に時々汗が出る、動くと益々甚だしい
3.発熱煩渇し、突然全身に悪寒戦慄が走る、その後汗が出て、熱勢は暫時退く
4.睡眠中に汗が出て、目が覚めると止まる
5.汗が出て、その色が黄で柏汁のよう
回答→4
問題 身体が疼痛し沈重、甚だしいと肢体浮腫、悪寒無汗、或いは咳喘胸悶、口不渇、舌苔白、脈弦緊。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.苓甘五味姜辛湯
2.葶藶大棗瀉肺湯
3.小青竜湯
4.大青竜湯
5.麻杏石甘湯
回答→3
【解説】
病名診断:痰飲、溢飲
「身体が疼痛し沈重、甚だしいと肢体浮腫」という症状は、水湿が四肢の皮膚に溢れ出た溢飲の病態を示しています。これは痰飲の一種です。
証候診断:表寒裏飲
患者の症状は、体表に風寒の邪が停滞し、体内に水飲(痰飲)が停滞している表寒裏飲の複合的な病態を示しています。
・表寒の証拠:「悪寒無汗」は、風寒の邪が体表を閉塞していることを示しています。
・裏飲の証拠:「身体が疼痛し沈重、肢体浮腫、咳喘胸悶、口不渇、舌苔白、脈弦緊」は、体内の水飲が停滞し、肺の機能や経絡の流れを阻害していることを示しています。特に「脈弦緊」は、寒邪と水飲が結びついている重要な徴候です。
1.苓甘五味姜辛湯
支飲の寒飲伏肺で、表証が明らかではない場合に用います。本症例は「悪寒無汗」という明確な表証があるため、不適切です。
2.葶藶大棗瀉肺湯
支飲で飲が多いが寒が少ない場合に用います。本症例の脈弦緊という強い寒の症状には適しません。
3.小青竜湯ー解表蠲飲、止咳平喘
外感した風寒の邪を発散させ、体内に停滞した水飲を温化して取り除きます。これにより、咳や喘息も鎮めます。本症例のような表寒裏飲の病態に最も適した方剤です。
4.大青竜湯
溢飲で表寒裏熱の病態に用いる方剤です。本症例は裏熱の症状がないため不適切です。
5.麻杏石甘湯
外感裏熱の喘証に用いる方剤です。本症例の寒飲の病態には適しません。
ポイント
類似方剤との鑑別:
小青竜湯は、表寒と裏飲が同時に存在する場合に用います。表証がない場合は苓甘五味姜辛湯、裏に熱がある場合は大青竜湯など、症状に応じて鑑別することが重要です。
問題 胃熱壅盛型の吐血を治療するために、選ぶべき方剤はどれか?
1.瀉心湯合十灰散
2.瀉白散合黛蛤散
3.玉女煎
4.大承気湯
5.黄土湯
回答→1
【解説】
1.瀉心湯合十灰散
・瀉心湯は清熱瀉火の効能があり、十灰散は涼血止血の効能があります。
・瀉心湯で胃の熱邪を冷まし、十灰散で出血を止めるという、この病態に最も適した組み合わせです。
2.瀉白散合黛蛤散
肝火犯肺による咳血の治療方剤です。吐血には適しません。
3.玉女煎
胃熱が原因の鼻血や歯肉からの出血に用いる方剤です。吐血に用いるには不十分です。
4.大承気湯
熱が結滞し、燥邪となった場合の便秘に用いる方剤です。吐血の止血には対応できません。
5.黄土湯
脾胃虚寒による便血の治療方剤です。本症例の熱証とは真逆の病態であるため、不適切です。
問題 吐血がなかなか止まらず、時軽時重、血色暗淡、神疲乏力、心悸気短、面色蒼白、舌質淡、脈細弱の症状。その治法はどれか?
1.健脾和胃、寧絡止血
2.益気養血、化瘀寧絡
3.補中益気、寧絡止血
4.補脾養胃、收斂止血
5.健脾益気、摂血
回答→5
【解説】
病名診断:吐血
証候診断:気虚血溢
患者の症状は、脾の気が不足して血液を統摂する機能が失われ、出血が止まらなくなっている気虚血溢の病態を示しています。
・気虚の証拠: 「神疲乏力」「心悸気短」「面色蒼白」「舌質淡」「脈細弱」は、脾気や心気の不足、そして気血の不足が深刻であることを示します。特に「脈細弱」は、気血両虚の典型的な脈象です。
・脾の統血機能失調: 「吐血がなかなか止まらず、時軽時重」「血色暗淡」は、脾の気が虚して血液を統摂できず、出血が慢性的に続いている状態を表しています。
1.健脾和胃、寧絡止血
健脾和胃と寧絡止血を組み合わせた治法は、内科学のテキストでは一般的ではありません。
2.益気養血、化瘀寧絡
益気養血と化瘀を同時に行うことは、出血時に化瘀薬を用いるリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
3.補中益気、寧絡止血
内科学のテキストでは一般的ではありません。
4.補脾養胃、收斂止血
内科学のテキストでは一般的ではありません。
5.健脾益気、摂血
気虚血溢の治療方法です。
ポイント
実証と虚証の鑑別: 吐血の診断では、まず実証(胃熱壅盛、肝火犯胃)と虚証(気虚血溢)を鑑別することが極めて重要です。
・実証: 熱象が顕著(舌紅、脈数など)で、出血の色は鮮やかです。
・虚証: 気血両虚の症状が顕著(神疲、顔色蒼白、脈細弱など)で、出血の色は暗淡です。
「摂血」の概念: 「摂血」は、脾の統血作用を回復させることで出血を止めるという、中医学独特の治療法です。「収斂止血」などの物理的な止血とは区別されます。気虚血溢による吐血には、脾の統血機能を回復させる帰脾湯が第一選択となります。
問題 下記の中で、咳血の治療で主要な方法でないものはどれか?
1.涼血止血
2.滋陰降火
3.瀉肝寧絡
4.清熱潤肺
5.補肺益気
回答→5
【解説】
1.涼血止血
肝火犯肺や陰虚肺熱による咳血に用いられます。出血している場合は、まず熱を冷まし、血の巡りを穏やかにして止血することが重要です。これは咳血治療の主要な方法です。
2.滋陰降火
陰虚肺熱による咳血の治療法です。陰液を補い、虚熱を冷ますことで出血を止めます。これも咳血治療の主要な方法です。
3.瀉肝寧絡
肝火犯肺による咳血の治療法です。肝の過剰な火を鎮め、絡脈の損傷を防ぎます。これも咳血治療の主要な方法です。
4.清熱潤肺
燥熱傷肺による咳血の治療法です。肺の熱を清し、乾燥した肺を潤すことで出血を止めます。これも咳血治療の主要な方法です。
5.補肺益気
気虚による出血の治療に用いられます。ご提示の解説の通り、脾肺気虚が原因となる尿血、便血、皮下出血(紫斑)などの治療には含まれますが、咳血の主な病因は「熱」や「火」であり、「気虚」は咳血の主要な病因とは考えられていません。
問題 小便黄赤、灼熱感、尿血が鮮紅、心煩口渇、面赤口瘡、夜寝不安、舌紅、脈数の症状が見られる。その治法はどれか?
1.清心瀉火、化瘀止血
2.清利湿熱、涼血止血
3.清熱瀉火、涼血止血
4.清熱養陰、寧絡止血
5.滋陰降火、涼血止血
回答→3
【解説】
病名診断:尿血
「尿血が鮮紅」という症状から、病名診断は尿血です。
証候診断:下焦熱盛
患者の症状は、下半身(下焦)に熱邪が盛んにこもり、それが膀胱や腎の絡脈を傷つけ、出血を引き起こしている下焦熱盛の病態を示しています。
・熱邪の証拠: 「小便黄赤、灼熱感、尿血が鮮紅、舌紅、脈数」は、熱邪が盛んであることを示しています。特に「灼熱感」は、熱が尿道にこもっていることを示します。
・熱邪の広がり: 「心煩口渇、面赤口瘡、夜寝不安」は、下焦の熱が上炎して心や胃に影響を与えていることを示しています。
1.清心瀉火、化瘀止血
この組み合わせの使用は内科学では存在しない。
2.清利湿熱、涼血止血
この組み合わせの使用は内科学では存在しない。
3.清熱瀉火、涼血止血
下焦熱盛による尿血に完全に合致する治法です。
4.清熱養陰、寧絡止血
燥熱や陰虚の咳血に用いる治法です。本症例の病態とは異なります。
5.滋陰降火、涼血止血
陰虚火旺の病態に用いる治法です。本症例のような実熱盛の病態には適しません。
代表方剤:小薊飲子
小薊飲子は、小薊や藕節で涼血止血を行い、木通、淡竹葉、山梔子で清熱と利尿(瀉火)を同時に行います。特に、滑石と甘草の「六一散」の組み合わせが、利尿によって熱を排出する導熱下行の作用を持つ点がポイントです。
問題 患者、男、44歳。夜寝ると盗汗が、時に自汗もある、五心煩熱、両顴発紅、口渇欲飲、舌紅少苔、脈細数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.大補陰丸
2.知柏地黄丸
3.清骨散
4.滋水清肝飲
5.当帰六黄湯
回答→5
【解説】
病名診断:盗汗・自汗
「夜寝ると盗汗が、時に自汗もある」という症状から、病名診断は盗汗・自汗(寝汗と日中の発汗)です。
証候診断:陰虚火旺
患者の症状は、体の陰液が不足し、相対的に熱が盛んになっている陰虚火旺の病態を示しています。
・陰虚火旺の証拠: 「五心煩熱、両顴発紅、口渇欲飲、舌紅少苔、脈細数」は、陰液の不足から生じる虚熱が盛んになっている典型的な症状です。
・発汗の証拠: 「夜寝ると盗汗、時に自汗もある」は、陰虚による発汗失調を示しています。特に陰虚による盗汗が主ですが、熱が盛んで気が虚しているため自汗も伴うと考えられます。
1.大補陰丸
滋陰降火作用が強力な方剤ですが、盗汗や自汗を止める「固表止汗」の作用は弱いため、本症例には不十分です。
2.知柏地黄丸
陰虚火旺に用いますが、主に腎の陰虚に焦点を当てています。本症例の発汗に直接対応する作用は弱いです。
3.清骨散
陰虚による骨蒸潮熱に用いる方剤です。本症例は盗汗が主症状であるため、清骨散の効能とは異なります。
4.滋水清肝飲
腎陰虚による肝熱の病態に用いる方剤です。発汗が主症状である本症例には不適切です。
5.当帰六黄湯
当帰、生地黄、熟地黄で陰液と血を補い、黄連、黄芩、黄柏の3つの「黄」で虚熱を清します。そして、黄耆で気を補い、表を固めて発汗を止めます。陰虚火旺による自汗・盗汗に用いる代表的な方剤です。
ポイント
・当帰六黄湯の組成: 「六黄」という名前の通り、黄耆、黄連、黄芩、黄柏、生地黄、熟地黄の6つの生薬と当帰から構成されています。黄耆が固表止汗に働く点が大きな特徴です。
・陰虚と発汗の関係: 陰虚による盗汗は、夜間に陽気が陰液を巡らせる力が弱まり、体表から津液が漏れ出すことで起こります。日中の自汗も、陰虚による虚熱が気を消耗させることで生じることがあります。
・類似方剤との鑑別: 陰虚火旺に用いる方剤は多数ありますが、盗汗・自汗といった発汗の症状が主であれば、固表止汗作用を持つ当帰六黄湯が第一選択となります。他の選択肢は、陰虚による熱証の治療に用いられますが、発汗に対する直接的な作用は劣ります。
問題 下記の中で、肝火上炎型の鼻衄における症状でないのはどれか?
1.頭痛眩暈
2.目赤
3.煩躁易怒
4.脈弦数
5.心悸不寧
回答→5
【解説】
「心悸不寧」は心神不安の属する症状で直接に肝と関与しません。
問題 咳嗽の間歇発作、痰中に血が混ざる、或いは鮮血を吐き、胸脇脹痛、煩躁易怒、口苦、舌紅苔薄黄、脈弦数。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.瀉白散合黛蛤散
2.竜胆瀉肝湯
3.当帰竜薈丸
4.丹梔逍遥散
5.滋水清肝飲
回答→1
【解説】
病名診断:咳血
「痰中に血が混ざる、或いは鮮血を吐き」という症状から、病名診断は咳血です。
証候診断:肝火犯肺
患者の症状は、肝の火が盛んになり、それが上炎して肺を侵す肝火犯肺の病態を示しています。
・肝火の証拠: 「胸脇脹痛、煩躁易怒、口苦、脈弦数」は、肝気が鬱結して火に転じている典型的な症状です。
・肺と出血の証拠: 「痰中に血が混ざる、或いは鮮血を吐き」は、肝火が肺の絡脈を損傷し、出血を引き起こしている状態です。
1.瀉白散合黛蛤散
・効能: 瀉白散は瀉肺清熱、止咳平喘の効能があり、黛蛤散は清肝瀉火、化痰止咳の効能があります。
・この2つの方剤を組み合わせることで、肺の熱と肝の熱を同時に治療します。
2.竜胆瀉肝湯
肝胆の湿熱に用いる方剤です。本症例の咳血には、瀉肺作用を持つ他の薬が必要です。
3.当帰竜薈丸
肝火盛による便秘などに用いる方剤で、咳血には不適切です。
4.丹梔逍遥散
肝鬱化火に用いる方剤ですが、出血に対する作用は弱く、咳血には不十分です。
5.滋水清肝飲
腎陰虚による肝熱の病態に用いる方剤で、実証の肝火犯肺には適しません。
ポイント
・咳血の病因鑑別: 咳血は、燥熱傷肺、陰虚肺熱、肝火犯肺の3つの病因に大別されます。本症例は「胸脇脹痛、煩躁易怒、口苦、脈弦数」といった肝の症状が顕著であるため、肝火犯肺と判断します。
・瀉白散と黛蛤散の役割: 瀉白散は肺の熱を清し、黛蛤散は肝の熱を清します。この組み合わせは、肺と肝の連動した病態を治療する上で非常に理にかなっています。
問題 患者、男、55歳。鮮紅色の吐血、口苦脇痛、怒り易い、睡眠が少なく多夢、煩躁不寧、舌質紅絳、脈象弦数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.黛蛤散合十灰散
2.瀉白散合黛蛤散
3.玉女煎
4.竜胆瀉肝湯
5.犀角地黄湯
回答→4
【解説】
病名診断:吐血
「鮮紅色の吐血」という症状から、病名診断は吐血です。
証候診断:肝火犯胃
患者の症状は、肝の火が盛んになり、それが胃を侵して出血を引き起こしている肝火犯胃の病態を示しています。
・肝火の証拠: 「口苦脇痛、怒り易い、睡眠が少なく多夢、煩躁不寧、脈象弦数」は、肝気が鬱結して火に転じている典型的な症状です。
・胃と出血の証拠: 「鮮紅色の吐血」は、肝火が胃を侵し、絡脈を損傷して出血を引き起こしている状態です。
・熱邪の証拠: 「舌質紅絳」や「脈象弦数」は、熱邪が盛んであることを示しています。
1.黛蛤散合十灰散
内科学にはこのような組み合わせの使用例はありません。
2.瀉白散合黛蛤散
肝火犯肺による咳血の治療方剤です。吐血には不適切です。
3.玉女煎
胃熱熾盛による鼻血や歯肉の出血に用いる方剤です。吐血に用いるには不十分です。
4.竜胆瀉肝湯ー瀉肝胆実火、清下焦湿熱
竜胆瀉肝湯は肝胆の実火を清す作用が非常に強力です。肝火犯胃の吐血に用いる代表的な方剤です。さらに、肝火亢盛の自汗盗汗や肝鬱化火の不眠など、幅広い肝火の病態にも応用されることが特徴です。
5.犀角地黄湯
血熱が盛んで、意識障害などの症状がある場合に用いる方剤です。本症例の病態とは異なります。
ポイント
・吐血と咳血の鑑別: 吐血は胃からの出血、咳血は肺からの出血です。本症例は「吐血」であり、「胸脇脹痛、怒り易い」という肝の症状と「吐血」という胃の症状が同時に現れることが、肝火犯胃の診断の鍵となります。
・竜胆瀉肝湯の適用範囲: 竜胆瀉肝湯は、単に吐血を止めるだけでなく、肝胆の実火を根本的に清すことで、その火が原因で引き起こされる様々な症状(口苦脇痛、不眠、多夢など)を同時に改善します。
・方剤の組み合わせ: 咳血であれば瀉白散合黛蛤散を、吐血であれば竜胆瀉肝湯を、というように、出血部位と病因に合わせて適切な方剤を選択することが重要です。
問題 飲留胃腸ではない痰飲の症状はどれか?
1.心下に堅満或いは痛み
2.水走腸間、瀝瀝有声
3.腹満便秘
4.口舌乾燥
5.下肢水腫
回答→5
【解説】
痰飲は、体内の水液代謝が失調し、水湿が体の一部に停滞することで起こる病証の総称です。その中で、「飲留胃腸」は、水飲が胃や腸に停滞する病態を指します。
「飲留胃腸の主な症状」
・心下に堅満或いは痛み: 水飲が胃に停滞することで、みぞおちのあたりが張ったり、硬くなったり、痛んだりします。
・水走腸間、瀝瀝有声: 腸に水飲が停滞することで、腸の中で水がチャプチャプと音を立てる症状です。
・腹満便秘: 水飲が中焦(腹部)に結滞することで、腹部の膨満感や便秘を引き起こします。
・口舌乾燥: 飲留胃腸の症状で、水飲が停滞していても、その水は体にうまく利用されないため、体の上部は水不足になり、口や舌が乾燥することがあります。
下肢の浮腫は、水飲が四肢の皮膚に溢れ出た溢飲や、脾腎陽虚による水腫の特徴です。飲留胃腸では、水飲が主に胃腸に停滞するため、下肢の浮腫は通常見られません。
「痰飲の種類と症状」
・飲留胃腸: 胃腸に停滞
・支飲(しいん): 肺に停滞。
・溢飲(いついん): 四肢や皮膚に停滞。
・懸飲(けんいん): 胸脇に停滞。
問題 心虚胆怯の心悸の治療に選ぶべきのはどれか?
1.桃仁紅花煎
2.安神定志丸
3.帰脾湯
4.苓桂朮甘湯
5.桂枝甘草竜骨牡蠣湯
回答→2
【解説】
病名診断:心悸
動悸や心拍の乱れがあることから、病名診断は心悸です。
証候診断:心虚胆怯
患者の症状は、心と胆の気が不足し、精神が不安定になっている心虚胆怯の病態を示しています。
「心虚胆怯の特徴」
・善驚易恐:些細なことで驚いたり、恐れたりする。
・坐臥不安:落ち着きがなく、じっとしていられない。
・少寐多夢:眠りが浅く、夢を多く見る。
「心悸の特徴」
・ 動悸や心拍の乱れ、脈動数または脈虚弦などが現れます。
1.桃仁紅花煎
心血瘀阻(心臓の血行不良)による心悸の治療方剤です。本症例の気虚の病態とは異なります。
2.安神定志丸
安神定志丸は、心虚胆怯の心悸や心胆気虚の不眠に用いられる代表的な方剤です。人参や茯苓で気を補い、菖蒲や竜歯で精神を安定させます。この病態の治療には、琥珀、磁石、朱砂などを加えることもあります。
3.帰脾湯
心血不足による心悸の治療方剤です。心虚胆怯の病態には、安神定志丸の方がより適しています。
4.苓桂朮甘湯
心悸の病態の中でも、水飲が心に影響を及ぼす水飲凌心に用いられる方剤です。また、支飲の脾陽虚弱では小半夏湯と、痰飲の脾腎陽虚では金匱腎気丸と、痰飲が内阻して嘔吐する場合では小半夏湯と併用するなど、痰飲の病態に幅広く応用されます。
5.桂枝甘草竜骨牡蠣湯
心陽不振による心悸の治療方剤です。
ポイント
・心虚胆怯の診断: 心虚胆怯は、単なる動悸だけでなく「善驚易恐」や「坐臥不安」といった精神的な不安定さが伴うことが大きな特徴です。
「類似方剤との鑑別」
心悸の原因は多岐にわたるため、病態に応じて適切な方剤を使い分けることが重要です。
・水飲凌心であれば苓桂朮甘湯、
・心血不足であれば帰脾湯
・心陽不振であれば桂枝甘草竜骨牡蠣湯
・心血瘀阻であれば桃仁紅花煎
・そして本症例のような心虚胆怯であれば安神定志丸が第一選択となります。
問題 心脾両虚の失眠における特徴症状はどれか?
1.失眠、性情が急躁易怒
2.失眠頭重、痰多胸悶
3.心煩失眠、頭暈、耳鳴、腰酸夢遺
4.多夢易醒、肢倦神疲、面色少華
5.失眠多夢、易於驚醒、胆怯心悸、遇事善驚
回答→4
【解説】
「心脾両虚の特徴」
・多夢易醒: 眠りが浅く、夢を多く見て目が覚めやすい。これは心血虚で心が安定せず、神を蔵すことができないために起こります。
・肢倦神疲: 四肢がだるく、精神が疲弊している。これは脾の気が不足し、四肢に栄養を運ぶことができないために起こります。
・面色少華: 顔色に艶がなく、くすんでいる。これは脾が血を生み出す機能が弱く、心血が不足して顔面を栄養できないために起こります。
ポイント
・心脾両虚の病理: 心は血を主り、精神活動を司ります。脾は血を生み出す源であり、気を生成し、運化を司ります。心脾両虚になると、脾が血を生み出せなくなり、心血が不足して心神を養えず、不眠となります。また、気血が不足するため、全身倦怠感や顔色の悪化が見られます。
・帰脾湯の構成: 帰脾湯は、人参、黄耆、白朮、甘草といった益気健脾の生薬と、当帰、竜眼肉、酸棗仁、遠志といった養血安神の生薬から構成されており、心と脾を同時に治療する優れた方剤です。
・不眠の鑑別: 不眠の病因は多岐にわたるため、心脾両虚だけでなく、肝鬱化火、痰熱内擾、陰虚火旺、心胆気虚といった病態を正確に鑑別することが、適切な治療法を選択する上で重要です。
問題 患者、女、26歳。ここ2ヶ月間仕事によるストレスが比較的多く、精神が緊張する、夜間はいつも失眠、入眠困難、入眠しても驚いて目を覚まし易い。心煩不安、心悸、頭暈健忘、時に耳鳴、腰酸、口乾咽燥、舌質紅、脈細数。この辨証が属するものはどれか?
1.心胆気虚
2.心脾両虚
3.陰虚火旺
4.血虚肝熱
5.心腎不交
回答→3
【解説】
病名診断:不寐
「夜間はいつも失眠、入眠困難、入眠しても驚いて目を覚まし易い」という症状から、病名診断は不寐(不眠症)です。
証候診断:陰虚火旺
患者の症状は、心と腎の陰液が不足し、相対的に熱が盛んになっている陰虚火旺の病態を示しています。
・陰虚の証拠: 「頭暈健忘」「時に耳鳴」「腰酸」「口乾咽燥」は、腎陰が不足していることを示唆します。特に「腰酸」は、腎虚の重要なサインです。
・虚火の証拠: 「心煩不安」「心悸」「舌質紅」「脈細数」は、陰液の不足から生じる虚熱が盛んになっている典型的な症状です。
・病態の背景: 「仕事によるストレス」が、肝鬱化火を経て陰液を消耗させ、この病態を形成したと考えられます。
1.心胆気虚
心悸不安、驚きやすさ、脈細弦などが特徴です。本症例のような口乾や腰酸といった陰虚症状はありません。
2.心脾両虚
不眠多夢、顔色萎黄、食欲不振、倦怠感などが特徴です。本症例の「舌紅」「脈細数」といった熱証はありません。
3.陰虚火旺
心煩不安、心悸、頭暈健忘、耳鳴、腰酸、口乾咽燥、舌質紅、脈細数といった症状を呈します。本症例の症状に完全に合致します。
4.血虚肝熱
不眠、眩暈、顔色蒼白、夢多、爪の異常などが特徴です。陰虚火旺とは症状が異なります。
5.心腎不交
陰虚火旺により引き起こされる病理結果の一つです。不眠の弁証としては、根本的な病態である陰虚火旺がより適切です。
ポイント
・不眠の鑑別: 不眠の弁証では、まず虚実を弁別することが重要です。実証であれば熱邪を清し、虚証であれば正気を補います。
・陰虚火旺の診断: 陰虚火旺は、虚熱(心煩、舌紅、脈数など)と陰液不足(口乾、腰酸、耳鳴など)の症状が同時に現れることが大きな特徴です。
・黄連阿膠湯と朱砂安神丸: どちらも陰虚火旺による不眠に用いられますが、心腎不交の病態が特に顕著であれば黄連阿膠湯を、不安や動悸が強く、精神的な不安定さが主であれば朱砂安神丸を、というように使い分けます。
問題 窒息しそうな胸悶痛、或いは痛みが肩背に及び、息切れして呼吸が速い、肢体沈重、形体肥胖、脘悶食欲がない、吐き気、舌苔白膩、脈滑。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.烏頭赤石脂丸合蘇合香丸
2.参附竜牡湯
3.丹参飲
4.膈下逐瘀湯
5.括楼薤白半夏湯
回答→5
【解説】
病名診断:胸痺
「窒息しそうな胸悶痛、或いは痛みが肩背に及び、息切れして呼吸が速い」という症状から、病名診断は胸痺(狭心症)です。
証候診断:痰濁壅塞
患者の症状は、体内の痰湿が凝集して胸部に停滞し、気の流れを塞いでいる痰濁壅塞の病態を示しています。
・胸痺の証拠: 「胸悶痛」や「息切れ」は、胸部の気の流れが阻滞されていることを示しています。
・痰濁の証拠: 「肢体沈重」「形体肥胖」「脘悶食欲がない」「吐き気」「舌苔白膩」「脈滑」は、痰湿が過剰に生成され、停滞している典型的な症状です。特に「形体肥胖」は、痰湿体質であることを示唆し、「舌苔白膩」「脈滑」は痰濁の存在を強く裏付けます。
1.烏頭赤石脂丸合蘇合香丸
陰寒凝滞で陰寒が極盛である胸痺の治療方剤です。本症例の痰濁の病態には適しません。
2.参附竜牡湯
陽気虚衰の胸痺で、心陽が脱しようとする重篤な病態に用いる方剤です。本症例の痰濁実証とは異なります。
3.丹参飲
心血瘀阻による胸痺の軽症に用いる方剤です。本症例の痰濁の病態には不十分です。
4.膈下逐瘀湯
瘀血内結の積証(腹部のしこりなど)の治療方剤です。胸痺には不適切です。
5.括楼薤白半夏湯
痰濁壅塞による胸痺に最も適した方剤です。
・この方剤は、痰濁壅塞による胸痺の代表方剤です。括楼、薤白、半夏の組み合わせで、胸部の陽気を巡らせ、痰濁を取り除き、胸部の閉塞を解消する作用に優れています。
ポイント
・胸痺の病因鑑別: 胸痺の病因は、痰濁壅塞、心血瘀阻、陰寒凝滞、陽気虚衰など多岐にわたります。本症例は「形体肥胖」「舌苔白膩」「脈滑」といった痰濁の症状が顕著であるため、痰濁壅塞と判断します。
・括楼薤白半夏湯の配合: 括楼は胸を開き、痰を化し、薤白は陽気を巡らせ、痰結を散らし、半夏は燥湿化痰に働きます。これらの生薬が互いに作用し、胸部の痰濁を効率的に取り除きます。
・類似方剤との鑑別: 胸痺の治療では、病因に応じて方剤を使い分けることが非常に重要です。痰濁が原因であれば括楼白半夏湯を、瘀血が原因であれば丹参飲を、といったように、症状から正確に病因を読み取ることが鍵となります。
問題 患者李様、女、43歳。ここ1ヶ月間胸部に刺痛を感じ、痛みは固定して移動せず、夜間に重くなる。時に心悸不寧が見られる、舌質紫暗、脈象沈渋。この場合の辨証が属するものはどれか?
1.陰寒凝滞
2.痰濁壅塞
3.心血瘀阻
4.痰熱中阻
5.心腎陰虚
回答→3
【解説】
病名診断:胸痺
胸部に胸悶痛の症状があることから、病名診断は胸痺です。
証候診断:心血瘀阻
患者の症状は、心臓の血脈に瘀血が停滞し、気の流れを阻害している心血瘀阻の病態を示しています。
・瘀血の証拠:
・胸部の刺痛、固定して移動せず、夜間に重くなる: 瘀血による疼痛は、場所が固定され、まるで針で刺されたような痛みで、夜間に悪化するという特徴があります。
・舌質紫暗、脈象沈渋: 舌の色が紫がかって暗く、脈が深く渋る(流れが悪い)のは、体内に瘀血が停滞している典型的な徴候です。
・他の症状:
・心悸不寧: 瘀血が心脈を阻害することで、心臓の鼓動が不規則になり、動悸や不安感が生じます。
方剤:血府逐瘀湯
血府逐瘀湯は、胸中の瘀血を除き、気の巡りを改善する代表的な方剤です。桔梗、枳殻、柴胡で気の巡りを整え、桃仁、紅花、川芎、赤芍などで活血化瘀の作用を強めます。特に、牛膝は引血下行(血を下方に導く)作用で胸部の瘀血を解消するのを助けます。
問題 陰虚火旺や熱病後の心煩失眠の治療に選用すべきはどれか?
1.朱砂安神丸
2.半夏秫米湯
3.黄連阿膠湯
4.礞石滾痰丸
5.交泰丸
回答→3
【解説】
1.朱砂安神丸
陰虚火旺による不眠や心悸に用いますが、黄連阿膠湯に比べて重鎮安神の作用が強く、特に精神的な不安定さが顕著な場合に適します。
2.半夏秫米湯
痰食が停滞して胃の働きが乱れたことによる不眠に用いる方剤です。本症例の陰虚熱の病態とは異なります。
3.黄連阿膠湯
黄連阿膠湯は、特に陰虚火旺や熱病後の陰液消耗による心煩失眠に用いられる代表的な方剤です。阿膠や芍薬で陰液と血を補い、黄連や黄芩で熱を清します。また、鶏子黄は滋陰安神に働きます。
4.礞石滾痰丸
痰火が極めて盛んである狂躁状態に用いる方剤で、非常に強力な作用を持ちます。本症例の陰虚病態には適しません。
5.交泰丸
心と腎の陰陽がバランスを失い、心火が盛んで腎陽が不足する心腎不交の不眠に用います。これは「助腎陽、清心火」の効能を持つ方剤です。
ポイント
・陰虚火旺の不眠: 陰虚火旺による不眠は、陰液不足による虚熱が心神を乱すことで起こります。黄連阿膠湯は、このような病態に特化して陰を補い、熱を冷ますことで根本的に治療します。
・黄連阿膠湯の構成: 黄連阿膠湯は、阿膠、芍薬、鶏子黄で陰液を補い、黄連、黄芩で熱を清すという、滋陰と清熱を同時に行う優れた配合です。
・交泰丸との違い: 交泰丸は、心腎不交の不眠に用いられますが、その病理は心火の盛んと腎陽の不足であり、黄連阿膠湯が治療する陰液不足による虚熱とは異なります。それぞれの病理を正確に把握することが重要です。
問題 心痛が背まで貫き、背痛が心まで貫く。激痛は止むことがない、身寒肢冷、喘息し横になれない、脈沈緊。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.烏頭赤石脂丸合蘇合香丸
2.参附竜牡湯
3.丹参飲
4.膈下逐瘀湯
5.括楼薤白半夏湯
回答→1
【解説】
病名診断:胸痺
「心痛が背まで貫き、背痛が心まで貫く」「喘息し横になれない」という症状から、病名診断は胸痺です。これは虚血性心疾患の重症な状態を示唆します。
証候診断:陰寒凝滞の重症(陰寒極盛)
患者の症状は、体内の陰寒の邪が凝集し、心脈を塞いでいる陰寒凝滞の病態を示しています。
・陰寒の証拠: 「身寒肢冷(しんかんしれい)」「脈沈緊(みゃくちんきん)」は、体内に寒邪が盛んであり、陽気が運ばれていないことを示しています。
・閉塞の証拠: 「心痛が背まで貫き、背痛が心まで貫く」「激痛は止むことがない」「喘息し横になれない」は、寒邪が心脈を強く閉塞し、重篤な状態であることを示しています。
1.烏頭赤石脂丸合蘇合香丸
・烏頭赤石脂丸: 温陽散寒止痛の効能を持ち、強い寒邪を温め散らす作用があります。
・蘇合香丸: 芳香開竅、行気止痛の効能を持ち、気血の巡りを速やかに開通させます。
・解説: 陰寒凝滞による重症の胸痺には、単一の方剤では力が足りません。強い温陽散寒作用を持つ烏頭赤石脂丸と、速やかに気血の巡りを開通させる蘇合香丸を併用することで、迅速かつ強力に病態に対応します。
2.参附竜牡湯
陽気虚衰の胸痺で心陽が脱しようとする場合に用いる方剤です。本症例の寒邪の凝滞が主体の病態とは異なります。
3.丹参飲
心血瘀阻の軽症に用いる方剤です。本症例の重篤な陰寒の病態には不十分です。
4.膈下逐瘀湯
瘀血内結の積証の治療方剤です。胸痺には不適切です。
5.括楼薤白半夏湯
痰濁壅塞による胸痺の治療方剤です。本症例の陰寒の病態とは異なります。
ポイント
・胸痺の病因鑑別: 胸痺の重症な病態は、陰寒凝滞と陽気虚衰に大別されます。本症例は「身寒肢冷」「脈沈緊」といった明らかな寒邪の症状と、「激痛」という強い閉塞の症状があるため、陰寒凝滞の重症と判断します。
・烏頭赤石脂丸の構成: 赤石脂、蜀椒、乾姜、烏頭、炮附子といった、温裏散寒作用の強い生薬が中心です。
・蘇合香丸の構成: 蘇合香、麝香、竜脳といった芳香開竅作用の強い生薬が中心です。
・治療の原則: 陰寒凝滞の重症には、強力な温陽散寒と開竅止痛を同時に行うことが重要です。そのため、それぞれの作用に特化した方剤を併用することが効果的です。
問題 怔忡証が臨床上で多く見られるのはどれか?
1.陰証
2.陽証
3.実証
4.虚証
5.寒証
回答→4
【解説】
「驚悸と怔忡の鑑別」
驚悸と怔忡は、どちらも動悸を指す病名ですが、その病理と症状に違いがあります。
⚫︎驚悸
・誘因: 外部からの刺激(驚き、恐怖、ストレスなど)がきっかけで動悸が起こります。
・病理: 比較的実証に多く見られます。
・特徴: 動悸が発作的に起こり、誘因が取り除かれると症状が治まります。
⚫︎怔忡
・誘因: 外部からの刺激とは関係なく、内因的に発生します。
・病理: 虚証に多く見られます。
・特徴: 動悸が常時続いており、休息しても症状は治まりません。少し動いただけで動悸が激しくなる傾向があります。
臨床上、「驚悸」は病気の初期や比較的軽症の段階で多く見られ、その多くは実証が原因です。一方、「怔忡」は病状が進行し、心身が虚弱になった段階で多く見られ、その多くは虚証が原因となります。
問題 胸部悶痛、甚だしければ肩背に痛みが及ぶ、短気喘息、横になれない。その診断はどれか?
1.結胸
2.胸痹
3.懸飲
4.支飲
5.胃痛
回答→2
【解説】
1.結胸
邪気が胸部に結びつく病証で、みぞおちから下腹部にかけての硬さや痛み、押すと痛む(拒按)などが特徴です。本症例の症状とは異なります。
2.胸痹
胸部の悶えるような痛み(悶痛)を主とし、痛みが肩や背中に放散することや、息切れ(気短)、呼吸困難(喘息)、横になれないなどの症状を伴います。本症例の症状に完全に合致します。
3.懸飲
痰飲が胸脇に停滞する病証で、咳や唾を吐くときに脇が引っ張られるように痛む(咳引脇痛)ことが特徴です。
4.支飲
痰飲が胸膈部に停滞する病証で、喘咳が主症状となり、胸部の脹満感や呼吸困難を伴います。胸痺のような強い胸部悶痛が主ではありません。
5.胃痛
主にみぞおちの痛みで、胸部全体に及ぶ悶痛や呼吸困難は伴いません。
問題 気鬱化火型の鬱証を治療するのに選ぶべき方剤はどれか?
1.竜胆瀉肝湯
2.温胆湯
3.天麻釣藤飲
4.半夏白朮天麻湯
5.丹梔逍遙散
回答→1
【解説】
病名診断:鬱証
証候診断:気鬱化火
1.竜胆瀉肝湯
肝鬱化火の不眠(不寐)の治療方剤です。鬱火が心神を攪乱する病態に用いられ、清熱作用が中心となります。鬱証の根本である気の鬱滞を疏す作用は丹梔逍遙散に比べて弱いため、本症例には不適切です。
2.温胆湯
気滞痰鬱が熱に転じた鬱証の治療方剤です。本症例の気鬱化火とは病理が異なります。
3.天麻釣藤飲
肝陽が上亢して引き起こされるめまいなどの治療方剤です。
4.半夏白朮天麻湯
痰濁による頭痛の治療方剤です。
5.丹梔逍遙散
丹梔逍遙散は、肝気の鬱結を疏し、同時に山梔子や牡丹皮で鬱滞した熱を冷まします。気鬱化火型の鬱証の治療に最も適した方剤です。
ポイント
⚫︎鬱証と不眠の治療方針:
・鬱証: 肝の疏泄機能の失調が根本にあるため、疏肝が治療の中心となります。
・不眠: 鬱火が心神を乱すことが主な病理であるため、清熱が治療の中心となります。
⚫︎竜胆瀉肝湯と丹梔逍遙散の使い分け:
・竜胆瀉肝湯: 清熱作用が強力で、肝火による不眠や頭痛、耳鳴り、脇痛などが主症状の場合に用います。
・丹梔逍遙散: 疏肝作用が中心で、気鬱による精神症状や、月経不順などを伴う場合に、清熱作用を補助的に用います。
問題 患者、男、30歳。病が急激に発症。もともと性格はせっかち、頭痛失眠、両目は怒ったように睨んで、面紅目赤、突然に狂乱して、垣根を越え屋根に上り、怒り罵声を叫ぶようにあびせる、親しい親しくないに関らず、物を壊し人を傷つける、普段より力がある、不食不眠。舌質紅絳、苔黄膩、脈象弦大滑数。この治療で最も適切な方剤はどれか?
1.黄連温胆湯
2.生鉄落飲
3.竜胆瀉肝湯
4.清営湯
5.鎮肝熄風湯
回答→2
【解説】
病名診断:狂証
「突然に狂乱して、垣根を越え屋根に上り、怒り罵声を叫ぶ」「物を壊し人を傷つける」「不食不眠」といった激しい精神・行動異常の症状から、病名診断は狂証です。
証候診断:痰火上擾
患者の症状は、体内の痰と火が結びつき、上方に逆上して心神を激しく攪乱している痰火上擾の病態を示しています。
⚫︎痰火の証拠:
・性格: 「もともと性格はせっかち」は、肝鬱化火の傾向があることを示唆します。
・熱の証拠: 「面紅目赤」「舌質紅絳」「脈象弦大滑数」は、体内の熱邪が極めて盛んであることを示しています。
・痰の証拠: 「苔黄膩」「脈象滑」は、痰湿が停滞していることを示唆します。
⚫︎心神の攪乱: 「突然に狂乱」「頭痛失眠」「不食不眠」は、痰と火が心神を激しく上擾し、精神活動を制御不能にしている状態です。
1.黄連温胆湯
痰熱内擾による心悸や不眠に用いる方剤です。本症例のような極めて激しい狂乱状態には、より強力な作用を持つ生鉄落飲が適しています。
2.生鉄落飲
狂証の中でも痰火上擾の病態に特化した方剤です。天門冬、麦門冬、玄参などで陰を滋養し、黄連、連翹、辰砂などで熱を清し、鎮静作用を高めます。また、貝母、胆南星、橘紅などで痰を取り除きます。
3.竜胆瀉肝湯
肝鬱化火や肝胆湿熱に用いる方剤です。本症例の痰火上擾の病態には、痰を取り除く作用が弱いため不十分です。
4.清営湯
邪熱が営分に入った病証に用いる方剤です。狂証には用いられません。
5.鎮肝熄風湯
肝陽上亢による中風後遺症や頭痛・めまいに用いる方剤です。狂証には不適切です。
ポイント
・狂証の病因: 狂証は、一般的に「痰」と「火」が結びついて心神を乱すことで発症します。
・生鉄落飲の配合: 生鉄落飲には、鎮静作用の強い辰砂(朱砂)が配合されており、重篤な狂乱状態を鎮めるのに効果的です。
・類似方剤との鑑別: 黄連温胆湯も痰熱を清しますが、生鉄落飲はより強い鎮心滌痰、瀉火作用を持ち、狂証のような重篤な病態に用いられます。病状の軽重を判断して使い分けることが重要です。
問題 突然に昏倒し、痙攣吐涎となる。叫び声は猪や羊の叫び声のよう、時間の経過とともに意識が回復する。平素から性情急躁、心煩失眠、咯痰不爽、口苦く乾く、便秘、舌紅苔黄膩、脈弦滑数。その治療する方剤はどれか?
1.定癇丸
2.生鉄落飲
3.竜胆瀉肝湯合滌痰湯
4.温胆湯合白金丸
5.当帰竜薈丸
回答→3
【解説】
病名診断:癇証
「突然に昏倒し、痙攣吐涎となる」「叫び声は猪や羊の叫び声のよう」「時間の経過とともに意識が回復する」という特徴的な発作症状から、病名診断は癇証です。
証候診断:痰火内盛
患者の症状は、体内の痰と火が結びつき、心神を激しく攪乱している痰火内盛の病態を示しています。
⚫︎癇証の病理: 癇証の主な病理は「風」「痰」「火」の3つが密接に関係しており、本症例では特に痰と火が盛んになっています。
⚫︎痰火の証拠:
・熱の証拠: 「性情急躁」「心煩失眠」「口苦く乾く」「便秘」「舌紅苔黄膩」「脈弦滑数」は、熱邪が盛んであることを示しています。
・痰の証拠: 「咯痰不爽」「舌苔黄膩」「脈滑」は、痰湿が停滞していることを示唆します。
1.定癇丸
癇証の病態の中でも、風痰閉阻に用いる方剤です。本症例の痰火内盛とは病理が異なります。
2.生鉄落飲
狂証の痰火上擾に用いる方剤です。癇証の発作とは症状が異なります。
3.竜胆瀉肝湯合滌痰湯
・竜胆瀉肝湯: 肝火を瀉し、熱を清す作用が強力です。
・滌痰湯: 痰を取り除く作用が強力で、心神を乱す痰邪を解消します。
・解説: 痰火内盛の癇証は、肝火の亢進と痰濁の停滞が同時に存在します。そのため、清熱作用に優れた竜胆瀉肝湯と、強力な祛痰作用を持つ滌痰湯を併用することで、病因を根本的に治療します。
4.温胆湯合白金丸
癲証の痰熱交蒸に用いる方剤です。狂証や癇証とは異なる病態です。
5.当帰竜薈丸
狂証の痰火内盛に用いる方剤です。
ポイント
・癇証の診断: 癇証の最も重要な特徴は、突然の意識障害と痙攣発作、そして発作後に意識が回復することです。
・痰火内盛の鑑別: 癇証の病態の中でも、「舌紅苔黄膩」「脈弦滑数」といった熱象と痰象が同時に見られることが、痰火内盛を判断する鍵となります。
問題 患者、男、21歳。今日ある人に腹を立てた後、眩暈、胸悶、乏力などの症状が現れ、その後突然倒れ瞬間に神志不省となり、痙攣、痰涎を嘔吐する。甲高い叫び声とともに二便を失禁する、舌苔白膩、脈弦滑。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.竜胆瀉肝湯
2.滌痰湯
3.定癇丸
4.竜胆瀉肝湯合涤痰湯
5.牛黄清心丸
回答→3
【解説】
病名診断:癇証
「突然倒れ瞬間に神志不省となり、痙攣、痰涎を嘔吐する。甲高い叫び声とともに二便を失禁する」という特徴的な発作症状から、病名診断は癇証です。
証候診断:風痰閉阻
患者の症状は、外風や内風と痰が結びつき、経絡や心神を閉塞している風痰閉阻の病態を示しています。
・発作前兆: 「腹を立てた後、眩暈、胸悶、乏力」といった症状は、肝気の鬱滞から風や痰が引き起こされる前兆を示唆します。
・風と痰の徴候: 「舌苔白膩」と「脈弦滑」は、体内に風邪と痰湿が停滞していることを強く示唆する舌脈の特徴です。
1.竜胆瀉肝湯
肝鬱化火の不眠や痰火内盛の癇証などに用いる方剤です。本症例のような風痰閉阻の病態には適しません。
2.滌痰湯
祛痰作用が強力ですが、単独では癇証の治療には力が足りず、中風の中臓腑の陰閉など、他の病態にも用います。
3.定癇丸
定癇丸は、癇証の病態の中でも風痰閉阻に特化した代表的な方剤です。天麻、全蝎、僵蚕で風を鎮め、胆南星、姜半夏、貝母などで痰を取り除き、辰砂や琥珀で鎮静作用を高めることで、痙攣や発作を抑制します。
4.竜胆瀉肝湯合涤痰湯
癇証の病態の中でも、痰火内盛に用いる方剤です。本症例の風痰閉阻とは異なります。
5.牛黄清心丸
内科学のテキストでは使用されない方剤です。
ポイント
⚫︎癇証の鑑別: 癇証の主な病態には風痰閉阻、痰火内盛、心腎虧虚があります。
・風痰閉阻: 舌苔白膩、脈弦滑。
・痰火内盛: 舌質紅、舌苔黄膩、脈弦滑数。
・心腎虧虚: 舌苔薄膩、脈細弱。
⚫︎定癇丸の構成: 天麻、川貝母、姜半夏、茯苓などの祛痰熄風の生薬が中心となり、辰砂や琥珀で心神を鎮める作用を強めます。
⚫︎病因の理解: 本症例では、怒りによって肝気が鬱滞し、風や痰を生成したことが発作の引き金となっています。この病因を理解することが、根本的な治療につながります。
問題 肝気鬱結型の鬱証を治療するのに選ぶべき方剤はどれか?
1.柴胡疏肝散加越鞠丸
2.竜胆瀉肝湯に左金丸を加える
3.丹梔逍遥散に左金丸を加える
4.逍遥散に越鞠丸加える
5.柴胡疏肝散に枳実導滞丸加える
回答→1
【解説】
1.柴胡疏肝散加越鞠丸
・柴胡疏肝散: 疏肝理気、活血止痛の効能を持ち、肝気鬱結を治療する基本的な方剤です。
・越鞠丸: 行気解鬱、清熱化湿、消食活血の効能を持ち、気の鬱滞に加え、熱、湿、食、血といった様々な鬱(五鬱)を同時に治療することができます。
・解説: 柴胡疏肝散で肝気鬱結を主として治療し、越鞠丸を加えることで、気鬱に起因する様々な付随症状(火鬱、湿鬱、食鬱、血鬱)にも対応し、治療効果を高めることができます。
2.竜胆瀉肝湯に左金丸を加える
このような組み合わせは内科学のテキストでは一般的ではありません。
3.丹梔逍遥散に左金丸を加える
肝鬱化火の鬱証に用いる方剤です。丹梔逍遥散は逍遥散に山梔子、牡丹皮を加えて清熱作用を高めたもので、火熱症状が顕著な場合に適します。
4.逍遥散に越鞠丸加える
このような組み合わせは内科学のテキストでは一般的ではありません。
5.柴胡疏肝散に枳実導滞丸加える
食滞を伴う肝気鬱結に用いることは考えられますが、内科学のテキストでは一般的ではありません。
問題 痰気が咽喉に鬱結して起こる病証はどれか?
1.噎膈
2.癭瘤
3.臓躁
4.梅核気
5.癲証
回答→4
【解説】
1.噎膈
食道に病変があり、飲食物が飲み込みにくくなったり、つかえたりする病証です。長引くと心血や胃気の虚弱に至ります。
2.癭瘤
前頸部に生じる腫れやしこり(甲状腺腫など)を指します。病理は気滞・痰凝・血瘀が原因です。
3.臓躁
精神的な不安や感情の不安定さが主な症状で、心神の失調が原因です。
4.梅核気
痰と気が結びついて咽喉に異物感が生じる病証で、本症例の病理と完全に一致します。
5.癲証
精神が抑鬱して寡黙になり、ぼんやりと独り言を言うなどの症状を特徴とする病証です。
問題 患者、女、16歳。昨日過食した後に、胃脘脹満疼痛、噯腐呑酸、大便不爽、苔厚膩、脈滑。かつて保和丸を服用したが効果は無かった。今度の治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.小承気湯
2.大承気湯
3.大柴胡湯
4.涼膈散
5.保和丸
回答→1
【解説】
病名診断:胃痛
「胃脘脹満疼痛」が主症状であることから、病名診断は胃痛です。
証候診断:飲食停滞
患者の症状は、暴飲暴食によって飲食物が胃腸に停滞し、気の流れを阻害している飲食停滞の病態を示しています。
⚫︎飲食停滞の証拠:
・病因: 「過食した後に」という病因が明確です。
・症状: 「胃脘脹満疼痛」「噯腐呑酸」は、飲食物の停滞による気の阻塞と腐敗を反映する典型的な症状です。
・舌脈: 「苔厚膩」「脈滑」は、宿食(停滞した飲食物)の存在を強く示唆する舌脈の特徴です。
・便通: 「大便不爽」は、停滞した飲食物が大腸にまで及び、伝導機能が阻害されていることを示します。
1.小承気湯ー瀉熱通便、消痞除満
問題文にあるように、飲食停滞の治療に用いられる保和丸を服用しても効果がなかったことから、停滞がより重く、大腸にまで及んでいると判断できます。小承気湯は、気の巡りを整え、便通を促す作用が強力であり、停滞した飲食物を速やかに排出するのに適しています。
2.大承気湯
飲食停滞がさらに進行し、燥熱を伴って便秘がひどく、腹痛が激しい場合に用いる方剤です。本症例の「大便不爽」よりも重い便秘に用います。
3.大柴胡湯
胆石症など、肝胆の病態に用いる方剤です。本症例の飲食停滞とは病理が異なります。
4.涼膈散
内科学のテキストでは一般的ではありません。
5.保和丸
飲食停滞の軽症に用いる方剤です。問題文にあるように、この方剤では効果がなかったため、より強力な方剤が必要です。
ポイント
・飲食停滞の軽重の鑑別: 飲食停滞は、その軽重によって用いる方剤が異なります。軽症で胃の停滞が主であれば保和丸を用いますが、停滞が大腸に及び、便通異常が見られる場合は、承気湯類(小承気湯、大承気湯など)を用います。
問題 胃脘脹悶、攻撑作痛、脘痛連脇、何時も情緒波動で痛作、噯気頻繁、舌苔薄白、脈沈弦。治療のために選ぶべき方剤はどれか?
1.保和丸
2.柴胡疏肝散
3.丹梔逍遥散
4.良附丸
5.左金丸
回答→2
【解説】
病名診断:胃痛
証候診断:肝気犯胃
1.保和丸
飲食停滞による胃痛に用いる方剤です。本症例の病因は飲食ではなく、情緒です。
2.柴胡疏肝散
この方剤は、肝気鬱結による病証の代表方剤です。柴胡、枳殻、陳皮などで気の巡りを改善し、芍薬、甘草などで胃の痛みを和らげます。本症例の「情緒変動で痛作」や「脘痛連脇」といった特徴に最も適しています。
3.丹梔逍遥散
肝鬱による熱症状(内熱)を伴う場合に用います。本症例には熱症状は見られません。
4.良附丸
寒邪客胃による胃痛に用いる方剤です。痛みが温めると和らぐなどの寒邪の特徴がありません。
5.左金丸
肝胃鬱熱による胃痛に用いる方剤で、胃の灼熱痛や吐酸などの熱症状が顕著な場合に適します。本症例の症状とは異なります。
問題 瘀血停滞による胃痛の治療で、まず選用すべきはどれか?
1.益胃湯
2.玉女煎
3.丹参飲
4.一貫煎
5.丹梔逍遙散
回答→3
【解説】
1.益胃湯
胃の陰液が不足する胃陰不足に用いる方剤です。瘀血の病態とは異なります。
2.玉女煎
胃熱熾盛(胃に強い熱がある)による出血や口渇に用いる方剤です。瘀血の病態には適しません。
3.丹参飲
丹参飲は、活血化瘀(血行を促進して瘀血を除く)作用に優れた丹参を君薬とし、行気止痛作用のある檀香と砂仁を配合した方剤です。胃部の瘀血を解消し、気の巡りを改善することで、痛みを速やかに和らげる効果があります。
4.一貫煎
肝陰不足による脇痛や胃痛に用いる方剤です。本症例の瘀血の病態とは異なります。
5.丹梔逍遙散
肝鬱化火による発熱や鬱証に用いる方剤です。瘀血の病態には不適切です。
問題 患者、女、57歳。胃病歴が20余年。毎回不注意な食事によって嘔吐する、時作時止、面色少華、倦怠乏力、脘腹痞悶。昨日飲食過多により、嘔吐酸腐、脘腹脹満、噯気厭食となった。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.木香順気散
2.柴胡疏肝散
3.保和丸
4.理中丸
5.香砂六君子湯
回答→3
【解説】
病名診断:嘔吐
証候診断:飲食停滞
患者の病態は、慢性的な脾胃の虚弱があるところに、昨日の「飲食過多」が加わって、飲食物が停滞した飲食停滞です。
⚫︎脾胃虚弱の証拠:
・病歴: 「胃病歴が20余年」「毎回不注意な食事によって嘔吐する」という慢性的な経過から、脾胃の機能が虚弱になっていることがわかります。
・虚弱の症状: 「面色少華(めんしょくしょうか)」「倦怠乏力(けんたいぼうりょく)」は、脾胃が虚弱で気血を生み出せないため、全身に栄養が行き届いていないことを示しています。
⚫︎飲食停滞の証拠:
・病因: 「昨日飲食過多により」という原因が明確です。
・症状: 「嘔吐酸腐」「脘腹脹満」「噯気厭食」は、停滞した飲食物が腐敗し、気の流れを阻害している典型的な症状です。
この症例は、脾胃虚弱という本(根本)がありながら、今は飲食停滞という標(表面的な病態)が主となっているのが特徴です。
1.木香順気散
積聚(腹部のしこり)や寒湿中阻による病態に用いる方剤です。本症例の飲食停滞には適しません。
2.柴胡疏肝散
肝気鬱結による胃痛や鬱証に用いる方剤です。本症例の病因は情緒ではなく、飲食です。
3.保和丸
保和丸は、飲食停滞による様々な症状(嘔吐、胃痛、腹痛など)の治療に用いられる代表的な方剤です。本症例のように、脾胃虚弱があっても、一時的な飲食停滞が主な病態である場合、まず食積を解消するためにこの方剤を選択します。
4.理中丸
脾胃虚寒による嘔吐や胃痛に用いる方剤です。本症例は虚寒よりも飲食停滞が主であるため、まず食積を解消する必要があります。
5.香砂六君子湯
脾胃虚寒による胃痛の治療に用いますが、飲食停滞が主な病態である本症例には適しません。
ポイント
・本と標の鑑別: 本症例は、脾胃虚弱という本(根本原因)がありますが、病態の主は飲食停滞という標(急性症状)です。急性の飲食停滞を解決することがまず治療の要点となります。
・保和丸の役割: 保和丸は、飲食物の消化を促進する作用に優れており、飲食停滞による症状を速やかに解消するのに適しています。
・健脾丸との関連: 脾胃虚弱と飲食停滞の両方がある場合、健脾丸がより適しているとされていますが、これは内科学のテキストでは一般的ではないため、選択肢の中では保和丸が最も適切です。
・脾胃虚弱を根本から治療するには: 飲食停滞の症状が治まった後は、香砂六君子湯や理中丸などの脾胃を補う方剤を用いて、根本的な脾胃虚弱を治療していくことが重要です。
問題 突然の嘔吐、発熱悪寒、頭身疼痛、胸脘満悶、舌苔白膩、脈濡緩を伴う。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.保和丸
2.玉枢丹
3.藿香正気散
4.理中丸
5.新加香薷飲
回答→3
【解説】
病名診断:嘔吐
証候診断:外邪犯胃
1.保和丸
飲食停滞による嘔吐に用いる方剤です。本症例の外邪による病態とは異なります。
2.玉枢丹
穢濁の気(汚れた邪気)による急性の嘔吐に用いる方剤です。本症例の風寒表証には適しません。
3.藿香正気散ー解表化湿、理気和中
この方剤は、外邪(風寒や暑湿)が体表を侵し、同時に湿濁が内臓(胃腸)に停滞する病態に最も適しています。藿香は、湿濁を化して気を巡らせるとともに、表邪を発散させる君薬として配合されており、発熱悪寒と嘔吐の両方に効果があります。
4.理中丸
脾胃虚寒による嘔吐に用いる方剤です。本症例のような外邪や湿濁の病態には不適切です。
5.新加香薷飲
暑湿の邪による感冒の治療に用いる方剤です。本症例の病態は、これと似ていますが、嘔吐が主症状であり、藿香正気散の方がより包括的に対応できます。
問題 嘔吐呑酸、噯気頻繁、胸脇悶痛、舌辺紅、苔薄膩、脈弦。その治法はどれか?
1.疏肝和胃、降逆止嘔
2.消食化滞、和胃降逆
3.滋養胃陰、降逆止嘔
4.燥湿祛痰、和胃降逆
5.以上どれも当てはまらない
回答→1
問題 胃陰虧虚による胃痛の治療で、まず選用すべきはどれか?
1.益胃湯
2.玉女煎
3.丹参飲
4.一貫煎
5.丹梔逍遙散
回答→4
【解説】
1.益胃湯
胃の陰液不足に用いる方剤ですが、主として胃陰不足の呃逆などに用いられます。肺胃陰傷の痿証や脾胃陰虚の虚労にも使用されます。
2.玉女煎
胃熱熾盛による鼻血や消渇に用いる方剤です。本症例の胃陰虧虚とは病理が異なります。
塾地黄 石膏 知母 麦門冬 牛膝
3.丹参飲
瘀血停滞による胃痛の治療に用いる方剤です。心血瘀阻の胸痺の軽症にも用いられます。
4.一貫煎
一貫煎は、肝腎の陰を補うことで胃陰を回復させ、同時に気の巡りを改善して痛みを和らげます。この方剤は、肝陰不足の脇痛や、脇痛を伴う肝陰虚の虚労、そして本症例のような胃陰虧虚の胃痛などに適しています。
生地黄 沙参 麦門冬 当帰 枸杞子 川楝子
5.丹梔逍遙散
肝鬱化火による発熱や鬱証に用いる方剤です。内傷発熱の肝鬱発熱や鬱証の気鬱化火に左金丸と併用することもあります。
柴胡 薄荷 生姜 当帰 白朮 白芍 茯苓 炙甘草 山梔子 牡丹皮
問題 患者、女、43歳。昨晩不注意で身体を冷やし、突然の嘔吐、胃の内容物及び清水を吐きだし、悪寒発熱、頭身疼痛、無汗、口不渇、胸脘満悶、舌苔白膩、脈濡緩を伴う。この治療で最も適当な方剤はどれか?
1.藿香正気散
2.苓桂朮甘湯
3.小半夏湯
4.温胆湯
5.香砂六君子丸
回答→1
【解説】
病名診断:嘔吐
「突然の嘔吐」が主症状であるため、病名診断は嘔吐です。
証候診断:外邪犯胃
患者の症状は、外部からの風寒の邪気が体表に侵入し、同時に湿濁が胃に停滞している外邪犯胃の病態を示しています。
・病因: 「昨晩不注意で身体を冷やし」という明確な外邪の侵入があります。
・風寒表証: 「悪寒発熱、頭身疼痛、無汗」は、風寒の邪が体表を侵した典型的な症状です。
・湿濁内停: 「胃の内容物及び清水を吐きだし」「胸脘満悶」「舌苔白膩」「脈濡緩」は、湿濁が中焦に停滞し、気の流れを阻害している状態を示します。
これらの症状を総合すると、風寒の表証と湿濁の内停が同時に見られる外邪犯胃と診断できます。
1.藿香正気散ー解表化湿、理気和中
この方剤は、外感風寒と内傷湿滞が同時に存在する病証に最も適しています。藿香は、湿濁を化して気を巡らせると同時に、表邪を発散させる働きを持つ君薬です。発熱悪寒と嘔吐の両方に対応できるため、本症例の治療に最適な方剤です。
藿香 紫蘇葉 白芷 半夏 陳皮 白朮 茯苓 桔梗 厚朴 大腹皮 生姜 大棗 炙甘草
2.苓桂朮甘湯
痰飲が停滞する痰飲内阻の嘔吐に使用する方剤です。本症例の外感病の症状には適しません。
茯苓 桂枝 白朮 甘草
3.小半夏湯
苓桂朮甘湯と同様に、痰飲内阻の嘔吐に用いる方剤です。
4.温胆湯
嘔吐の治療には使用されていません。
半夏 陳皮 茯苓 甘草 竹筎 枳実
5.香砂六君子丸
脾胃虚寒の回復期などに用いる方剤です。本症例の急性的な外感病の病態には不適切です。
六君子湯+香附子 砂仁
問題 胃脘脹悶、攻撑作痛、脘痛連脇、何時も情緒波動で痛作、噯気頻繁、舌苔薄白、脈沈弦。治療のために選ぶべき方剤はどれか?
1.保和丸
2.柴胡疏肝散
3.丹梔逍遥散
4.良附丸
5.左金丸
回答→2
【解説】
病名診断:胃痛
「胃脘脹悶」「攻撑作痛」という症状から、病名診断は胃痛です。
証候診断:肝気犯胃
患者の症状は、肝気の鬱結が胃に影響を及ぼしている肝気犯胃の病態を示しています。
⚫︎肝気鬱結の証拠
・情緒波動で痛作: 感情の変化、特に怒りや不機嫌によって痛みが発作的に現れるのは、肝気の鬱滞が原因であることを示します。
・脘痛連脇: 胃の痛みが脇にまで及ぶのは、肝の経絡が胸脇部を通るため、肝気の鬱結が原因であることを示唆します。
・脈沈弦: 脈が沈んで弦を張っているのは、気の鬱滞と肝の病変を反映する典型的な脈象です。
⚫︎胃の症状
・胃脘脹悶、攻撑作痛: 胃部の張りや、突っ張るような強い痛みは、気が鬱滞して気の巡りが悪くなっているためです。
・噯気頻繁: ゲップが多いのは、胃の気の流れが阻害され、逆流しているためです。
1.保和丸
飲食停滞の胃痛などを治療する方剤です。本症例の病因は飲食ではなく、情緒です。
山査子 萊菔子 神麹 半夏 陳皮 茯苓 連翹
2.柴胡疏肝散
この方剤は、肝気鬱結による病証の代表方剤です。柴胡、枳殻、陳皮などで気の巡りを改善し、芍薬、甘草などで胃の痛みを和らげます。この方剤は、本症例の「情緒変動で痛作」や「脘痛連脇」といった特徴に最も適しています。
四逆散(枳実→枳穀)+川芎 香附子 陳皮
3.丹梔逍遥散
肝鬱発熱の内傷発熱を治療する方剤です。本症例には熱症状が見られません。
柴胡 薄荷 生姜 当帰 白芍 白朮 茯苓 炙甘草 牡丹皮 山梔子
4.良附丸
寒邪客胃の胃痛などを治療する方剤です。本症例には寒邪の特徴がありません。
高良姜 香附子
5.左金丸
肝胃鬱熱の胃痛などを治療する方剤です。本症例の症状とは異なります。
黄連 呉茱萸
ポイント
・寒邪客胃であれば良附丸、
・飲食停滞であれば保和丸、
・肝気犯胃であれば柴胡疏肝散、
・肝胃鬱熱であれば左金丸、というように使い分けます。
問題 下記の中で、脾胃虚弱型の嘔吐における症状でないものどれか?
1.不注意な飲食によりすぐに嘔吐する
2.朝、食べた物を夕暮れに吐く
3.面色不華
4.四肢が温まらない
5.時に嘔吐し時に止まる
回答→2
【解説】
朝、食べた物を夕暮れに吐くは、脾胃虚弱の嘔吐ではなく、反胃の症状です。
・反胃: 食物が胃に停滞して消化されず、長時間経ってから吐き出す病証です。具体的な症状として、朝食べたものを夕方に吐く(朝食暮吐)や、夕食を翌朝に吐く(暮食朝吐)といった特徴があります。吐き出した物は未消化であり、吐く前には胃の張りや痛みを伴います。
・脾胃虚弱の嘔吐: 食べた後すぐに吐くことが多く、吐き出した物は必ずしも未消化ではありません。