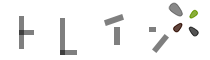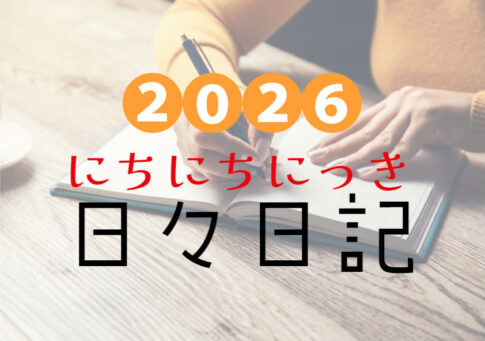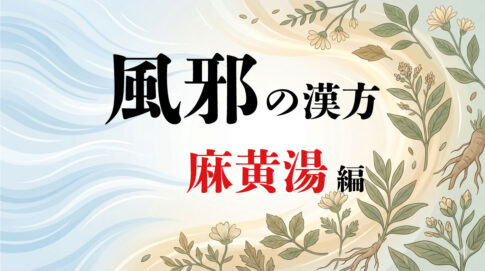問題 気淋の実証の治療に用いる主な方剤はどれか?
1.柴胡疏肝散
2.越鞠丸
3.沈香散
4.大七気湯
5.四磨飲子
回答→3
【解説】
気淋は、排尿時に痛みや渋り、ポタポタとしか出ないといった症状を特徴とする病証です。原因によって実証と虚証に分けられます。
⚫︎気淋の実証
・病理特徴: 肝の気の流れ(疏泄)が滞り、気機が鬱滞することで、水液の排出が障害されます。
・臨床症状: 小便が渋り、ポタポタとしか出ず(淋瀝不宣)、下腹部(少腹)に張るような痛みがあります。舌苔は薄白で、脈は沈んで弦を張る傾向があります。
治法と方剤
・治法: 理気通淋。気の流れを整え、尿路の停滞を解消します。
・代表方剤: 沈香散
1.柴胡疏肝散
肝気鬱結による脇痛などに用いる方剤です。気淋の治療には直接用いません。
2.越鞠丸
肝気鬱結による鬱証の初期に、気の流れを改善するために用いる方剤です。
3.沈香散
・気淋の実証に最も適した方剤です。理気通淋の効能により、気の滞りを解消し、排尿をスムーズにします。また、肝鬱気滞による癃閉(尿閉)の治療にも用いられます。
・沈香散は、沈香や橘皮で気の流れを改善し、石葦、滑石、冬葵子などで利尿を促します。また、当帰、王不留行、白芍などで活血通絡作用も併せ持ち、気の滞りによる痛みを和らげます。
4.大七気湯
気滞が重く、寒を伴う積証に用いる方剤です。
5.四磨飲子
肝気横逆による、肺や胃への影響を治療する方剤です。 内科学に載ってない方剤である。
ポイント
・気淋の鑑別: 気淋には実証と虚証があります。実証は肝気の鬱滞によるもので、虚証は腎虚によるものです。症状の鑑別が重要です。
問題 患者、男、30歳。左側腰腹部に突発性劇痛で、痛みが外陰部に放射し、尿頻尿急、超音波の検査で左側の尿管結石が判明され、舌暗紅、脈弦。その治療方剤はどれか?
1.金鈴子散合石葦散加減
2.竜胆瀉肝湯加減
3.済生腎気丸加減
4.萆薢分清飲加減
5.八正散加減
回答→1
【解説】
病名診断:石淋
「超音波の検査で左側の尿管結石が判明され」という情報から、病名診断は石淋です。石淋は、尿路結石によって引き起こされる淋証の一種です。
証候診断:湿熱下注・気滞血瘀
患者の症状は、湿熱が膀胱に停滞することで結石が形成され、その結石が尿路を塞いで気の流れと血の流れを阻害している湿熱下注・気滞血瘀の病態を示しています。
⚫︎石淋の証拠
・「左側腰腹部に突発性劇痛で、痛みが外陰部に放射」: 結石が尿管を通過する際に、強い痛みが生じます。これは「気滞」と「血瘀」が原因です。
・「尿頻尿急」: 湿熱が膀胱に停滞し、尿路が刺激されることで、排尿回数が増え、尿意が切迫します。
⚫︎舌脈
・「舌暗紅」: 舌の色が暗いのは、血の巡りが滞っている「血瘀」を反映しています。
・「脈弦」: 肝の気の流れが滞っている「気滞」を反映しています。
治法と方剤
⚫︎治法: この病態の治療は、理気疏肝、活血止痛と、清熱利水、排石通淋を同時に行うことが重要です。
⚫︎代表方剤
・金鈴子散: 理気疏肝と活血止痛の効能を持ち、激しい痛みを和らげます。
・石葦散: 清熱利水と排石通淋の効能を持ち、結石の排出を促します。
・両方剤の併用: 金鈴子散合石葦散加減は、気滞による激痛を緩和し、湿熱を清めて結石を排出するという、石淋の病態に最も適した組み合わせです。
1.金鈴子散合石葦散加減
石淋の病態に特化しており、理気止痛と清熱排石の作用を兼ね備えています。
2.竜胆瀉肝湯加減
肝胆の湿熱による脇痛などに用いる方剤です。結石の排出作用は持ちません。
3.済生腎気丸加減
腎陽虚による病態に用いる方剤です。本症例の湿熱の実証とは異なります。
4.萆薢分清飲加減
膏淋(尿が濁る)の実証に用いる方剤です。結石の治療には用いません。
5.八正散加減
湿熱下注による熱淋(排尿痛)に用いる方剤です。結石の排出作用は強くありません。
問題 患者、女43歳。腰部が痠軟して痛む、労累により痛みが悪化、腰膝に力が入らない、心煩して眠れない、手足心熱、舌紅、脈弦細数。この治療で選ぶべきものはどれか?
1.六味地黄丸
2.左帰丸
3.知柏地黄丸
4.八仙長寿丸
5.帰芍地黄丸
回答→2
【解説】
病名診断:腰痛
証候診断:腎虚腰痛・腎陰虚
・労累により痛みが悪化」: 疲労によって症状が悪化するのは、正気(気血や精)が不足している虚証の典型的な特徴です。
・「腰膝に力が入らない」: 腎は骨を主り、腰を司るため、腎精が不足すると腰や膝が弱く、力が入らなくなります。これは腎虚腰痛の最も重要な特徴です。
・「心煩して眠れない、手足心熱」: 陰液の不足により陽が相対的に亢進し、虚熱が生じます。その結果、心に熱がこもってイライラし、不眠や手足のほてり(五心煩熱)が生じます。
・「舌紅」: 舌の色が赤いのは、体内に熱(虚熱)があることを示します。
・「脈弦細数」: 脈が弦(肝鬱)を張り、細く(陰虚)、速い(数:熱)のは、陰虚による虚熱の典型的な脈象です。
1.六味地黄丸
腰痛の治療方剤ではなく、腎陰虧虚を伴う陰虚火旺の紫斑、腎精虧耗の健忘、陰液耗傷を伴う石淋、肝腎虧損・髄枯筋痿の痿証、腎陰虧虚の下消など、腎陰虚による様々な病態に広く用いられます。
2.左帰丸
腎陰虚の腰痛に最も適した方剤です。そのほか、腎精不足の偏陰虚の眩暈、腎陰虚の虚労などの治療にも用いられます。六味地黄丸よりも補腎の力が強力です。
3.知柏地黄丸
腎陰虧虚の労淋、腎虚火旺の尿血、陰虚火旺の心悸、陰虚火旺の下消など、陰虚による虚熱が盛んな病態に用いる方剤です。
4.八仙長寿丸
別名は麦味地黄丸で、陰虚が主で火熱がひどくない盗汗の治療方剤です。
5.帰芍地黄丸
六味丸に当帰・白芍を加えた方剤で、肝血不足と腎陰不足の病証を同時に治療します。
※左帰丸は六味地黄丸よりも補腎の力が強く、腎精の不足が顕著な腰痛に最も適しています。その構成生薬には、熟地黄、山茱萸、山薬といった補陰薬に加えて、鹿角膠、亀板膠といった精髄を補う生薬が配合されています。
※労累(ろうるい)ー度な労働や苦労によって心身がひどく疲れている状態を指す言葉です。特に中医学では、単なる疲労を超えた、臓腑の機能が低下するほどの消耗を意味します。
問題 寒湿腰痛で、痛みが下肢に及び、関節の疼痛を伴う。その治療で、主方の他に加えるべき方剤はどれか
1.独活寄生湯
2.四妙丸
3.右帰丸
4.腎気丸
5.左帰丸
回答→1
【解説】
病名診断:腰痛
証候診断:寒湿腰痛(風邪を伴う)
患者の症状は、腰痛の原因が寒湿であり、さらに風邪の侵入を伴っている病態を示しています。
・「寒湿腰痛」: 腰痛の原因が寒湿邪にあることが示されています。
・「痛みが下肢に及び、関節の疼痛を伴う」: これは、寒湿の邪気だけでなく、風邪が経絡を巡っていることを示す重要な手がかりです。風邪は動きが速く、痛みの場所が定まらない、あるいは広範囲に及ぶといった特徴があります。
・寒湿腰痛(風邪を伴う)の特徴: 腰痛の場所が左右不定で、両足や肩背、各関節に牽引痛を伴うことが多いです。
治法と方剤
・寒湿腰痛の主方: 寒湿を温めて取り除く甘姜苓朮湯が主方となります。
・加えるべき方剤: この病態では、風邪が加わっているため、寒湿を取り除く作用に加えて、風邪を追い払い、経絡を通り、肝腎を補う作用を持つ方剤が必要です。
・代表方剤: 独活寄生湯がこれに該当します。この方剤は、祛風湿、止痺痛、益肝腎、補気血の効能を持ち、寒湿に加えて風邪や気血の不足を伴う痺証の治療に用いられます。
1.独活寄生湯
気血・肝腎の不足を伴う痺証や、風邪を伴う寒湿腰痛の治療に用いられる方剤です。袪風湿、止痺痛、益肝腎、補気血の効能があり、本症例の病態に最も適しています。
2.四妙丸
湿熱腰痛の治療に用いる方剤です。本症例の寒湿とは病因が異なります。
3.右帰丸
腎陽虚による腰痛に用いる方剤です。寒湿による実証の痛みとは異なります。
4.腎気丸
陰陽両虚の下消などに用いる方剤です。
5.左帰丸
腎陰虚による腰痛などの治療に用いる方剤です。
問題 淋証の最も重要な特徴はどれか?
1.小便澀滞、少腹満痛
2.小便熱澀刺痛、尿色深紅
3.小便熱澀疼痛、小便が米のとぎ汁のように混濁している
4.小便は淋瀝が止まらない、時作時止
5.小便頻数短澀、滴瀝刺痛
回答→5
【解説】
淋証は、泌尿器系の病証で、排尿時の異常を主症状とします。
⚫︎淋証の主な特徴
・「小便頻数」: 排尿回数が多い。
・「小便短澀」: 尿の量が少なく、排尿がスムーズでない。
・「滴瀝」: 尿がポタポタとしか出ない、または排尿後にも滴り落ちる。
・「刺痛」: 排尿時に刺すような鋭い痛みがある。
ポイント
・淋証の弁証: 淋証は、熱淋、石淋、血淋、気淋、膏淋、労淋の六つ(六淋)に分類されます。これらの鑑別を行う前に、まず淋証の共通する基本的な症状を正確に把握することが重要です。
・最も重要な特徴: 「小便頻数短澀、滴瀝刺痛」は、六淋すべてに共通する基本的な症状であり、淋証を診断する上での核心的な特徴です。
問題 患者、三日以来、小便が一滴も出ず、短赤灼熱、小腹脹満、口苦口粘、舌紅苔黄膩、脈数。その弁証はどれか?
1.気淋実証
2.熱淋
3.膀胱湿熱型の癃閉
4.尿路阻塞型の癃閉
5.以上どれも当てはまらない
回答→3
【解説】
病名診断:癃閉
「小便が一滴も出ず」という症状は、尿が全く出ない癃閉の典型的な特徴です。痛みは訴えていないものの、尿が出ない状態であることから、まず癃閉と診断します。
証候診断:膀胱湿熱
⚫︎癃閉の証拠
・「小便が一滴も出ず」: 尿が全く出ない状態です。
・「短赤灼熱」: 尿量が極端に少なく色が濃く、熱感や灼熱感を伴います。これは湿熱が膀胱に停滞していることを示します。
・「小腹脹満」: 尿が膀胱に溜まり、下腹部が膨らんで苦しい状態です。
⚫︎湿熱の証拠
・「口苦口粘」: 湿熱が上焦に影響し、口の中に苦さや粘り気を感じます。
・「舌紅苔黄膩」: 舌の色が赤く(熱)、苔が黄色く油っぽい(湿熱)のは、湿熱が盛んであることの典型的な舌象です。
・「脈数」: 脈が速い(数)のは、熱邪の存在を示しています。
治法と方剤
・治法: 清熱利湿、通利水道。熱を清め、湿を排出し、尿路の通りを良くします。
・代表方剤: 八正散
・八正散の効能: いただいた解説にあるように、八正散は清熱瀉火、利尿通淋の効能があり、膀胱湿熱による癃閉だけでなく、熱淋の治療にも用いられる方剤です。
1.気淋実証
尿がポタポタとしか出ず、下腹部の張るような痛みがあるのが特徴で、本症例の尿が全く出ない状態とは異なります。
2.熱淋
尿の量が少なく、灼熱刺痛を伴いますが、尿は全く出ないわけではありません。また、寒熱(発熱悪寒)などの表証を伴うこともあります。
3.膀胱湿熱型の癃閉
本症例の「小便点滴不通」「短赤灼熱」「小腹脹満」「口苦口粘」「舌紅苔黄膩」といったすべての症状に合致します。
4.尿路阻塞型の癃閉
尿路が物理的に塞がれている病態で、排尿が全くできないか、細い線のようにしか出ないのが特徴です。本症例は、超音波検査などで物理的な閉塞が確認されていないため、弁証に基づく診断ではこの選択肢は優先されません。
ポイント
・癃閉と淋証の鑑別: 癃閉は「排尿困難」を主症状とし、排尿時の痛みは伴わないか、あっても軽度です。一方、淋証は「排尿痛」が主症状であり、排尿困難は伴いますが、全く出ないわけではありません。この鑑別が重要です。
問題 患者、男、67歳。尿道の疼痛により、排尿が中断、尿血、腹腰に絞痛あり、舌紅苔黄、脈弦。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.四磨飲
2.石葦散
3.小薊飲子
4.八正散
5.以上どれも当てはまらない
回答→2
【解説】
病名診断:淋証・石淋
・「尿道の疼痛により、排尿が中断」という症状から、尿路に異物が詰まっていることが推測できます。
・「尿血」と「腹腰に絞痛」を伴うことから、これは石淋の典型的な病態です。砂粒が小さければ排尿時に激しい痛みが生じ、大きければ排尿が急に中断し、耐え難い痛みを伴うことがあります。
証候診断:湿熱下注、煎熬尿液(せんごうにょうえき)
患者の症状は、湿熱が下焦に停滞し、尿液が煎じられて結晶が析出することで結石が形成された病態を示しています。
⚫︎湿熱の証候
・「尿道の疼痛、尿血」: 湿熱が膀胱の経絡を損傷していることを示します。
・「腹腰に絞痛」: 結石による気の滞りと血の滞り、それに伴う激しい痛みです。
・「舌紅苔黄、脈弦」: 舌の色が赤いのは熱、苔が黄色いのは湿熱、脈が弦を張るのは気の滞りを反映しています。
治法と方剤
・病理: 石淋の病理要点は、湿熱が膀胱に下注し、尿液を煎じ詰めて結石を形成することです。
・治法: この病態の治療は、清熱利水、排石通淋が基本となります。
・代表方剤: 石葦散
・石葦散の効能:石葦散は石葦、冬葵子、滑石、車前子など、清熱利水と排石作用に優れた生薬で構成されており、石淋の治療に最も適しています。
1.四磨飲
肝気鬱結による胸部の張りや喘息などに用いる方剤です。石淋の治療には適しません。
2.石葦散
石淋の治療に特化した方剤です。清熱利水と排石通淋の効能を持ち、結石の排出を促します。
3.小薊飲子
下焦の熱盛による尿血(血淋)に用いる方剤で、排石作用は持ちません。
4.八正散
湿熱下注による熱淋や膀胱湿熱型の癃閉に用いる方剤ですが、結石の排出に特化した作用は弱いです。
問題 患者、女、56歳。過度な労働による疲労のため、小便不調となる、腰膝痠痛、面白神疲、形寒肢冷、舌淡苔白、脈弱。この治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.香茸丸
2.温脾湯
3.補中益気湯
4.済生腎気丸
5.左帰丸
回答→4
【解説】
病名診断:癃閉
「過度な労働による疲労のため、小便不調となる」という情報から、排尿障害が病気の主軸であることがわかります。
証候診断:腎陽衰憊
患者の症状は、過労によって腎の陽気が衰え、膀胱の気化作用が失調した腎陽衰憊の病態を示しています。
⚫︎腎陽衰憊の証拠
・「腰膝痠痛」: 腎の陽気と精が不足することで、腰や膝にだるさや痛みが現れます。
・「面白神疲」: 顔色が悪く(白)、気力がない(神疲)のは、陽気が不足している気虚の症状です。
・「形寒肢冷」: 陽気の不足により、体を温める作用が失われ、寒がりになり、手足が冷たくなります。これは腎陽虚の最も重要な特徴です。
・「舌淡苔白」: 陽気の不足と寒湿の停滞を反映しています。
・「脈弱」: 陽気や正気が不足している虚証の典型的な脈象です。
治法と方剤
・治法: 温補腎陽、利水消腫。腎の陽気を温めて補い、水分代謝を改善します。
・代表方剤: 済生腎気丸
・済生腎気丸の構成: 温補腎陽の作用を持つ附子や桂枝と、利水消腫の作用を持つ車前子、牛膝などがバランス良く配合されており、腎陽衰憊による癃閉に効果を発揮します。
1.香茸丸
腎陽衰憊の癃閉に用いられますが、精血の不足が顕著な場合に適しています。
2.温脾湯
腎陽衰憊の癃閉で、特に寒湿が内結している場合に用いる方剤です。
3.補中益気湯
中気不足による癃閉に用いる方剤です。本症例のような腎陽虚の症状(形寒肢冷)は主症状ではありません。
4.済生腎気丸
腎陽衰憊による癃閉に最も適した方剤です。温補腎陽と利水作用を兼ね備えており、膀胱の気化機能を回復させます。
5.左帰丸
腎陰虚による腰痛などに用いる方剤で、本症例の腎陽虚とは病態が異なります。
問題 患者林様、女、56歳。小便熱渋し刺痛があり、尿色紫紅、甚だしければ血塊が混じる、舌苔黄、脈滑数。この診断はどれか?
1.熱淋
2.癃閉
3.気淋
4.石淋
5.血淋
回答→5
問題 小便澀滞、淋瀝不宣、少腹満痛、舌苔薄白、脈沈弦。その治療方剤はどれか?
1.天台烏薬散
2.逍遥散
3.石葦散
4.沈香散
5.八正散
回答→4
【解説】
病名診断:淋証・気淋
・「小便澀滞、淋瀝不宣」という排尿困難の症状から、病名診断は淋証です。
・「少腹満痛」と「脈沈弦」は気の停滞を強く示しており、これが小便の通りを妨げていると判断できるため、気淋と診断できます。
※小便澀滞ー排尿がスムーズでなく、渋るように感じる状態を指す
※淋瀝不宣ー排尿がスムーズに行われず、ポタポタと少しずつしか出ない状態を指す
証候診断:気淋実証
患者の症状は、肝の気の流れが滞ることで、水液の排出が障害されている気淋実証の病態を示しています。
1.天台烏薬散
寒凝気滞による小腸疝気を治療する方剤です。本症例の気淋とは病態が異なります。
2.逍遥散
気鬱脾虚の黄疸などに用いる方剤であり、淋証の治療には使用しません。
3.石葦散
石淋の治療に用いる方剤です。本症例の気淋とは病態が異なります。
4.沈香散
最も適した方剤です。理気通淋の効能により、気の滞りを解消し、排尿をスムーズにします。
5.八正散
湿熱下注による熱淋に用いる方剤です。本症例の舌苔薄白や脈沈弦といった症状とは異なり、熱証(灼熱刺痛、苔黄など)が顕著な場合に用います。
問題 患者、男、56歳。長期にわたる精神抑鬱のため、小便不暢が現れる、脇脹、ため息をよくつく、舌紅苔黄、脈弦数。この治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.沈香散
2.四逆散
3.逍遥散
4.春沢湯
5.六磨湯
回答→1
【解説】
病名診断:癃閉
「小便不暢が現れる」という情報から、排尿障害が主症状であることがわかります。
証候診断:肝気鬱結
患者の症状は、長期にわたる精神的な抑鬱が原因で、肝の気が鬱滞している肝気鬱結の病態を示しています
⚫︎肝気鬱結の証候
・「長期にわたる精神抑鬱」: 病因そのものです。精神的なストレスが気の流れを滞らせます。
・「小便不暢」: 肝の疏泄機能が失調し、気の流れが悪くなることで、水液の排出が妨げられます。
・「脇脹、ため息をよくつく」: 気の鬱滞が経絡に現れた典型的な症状です。
⚫︎舌脈
・「舌紅苔黄、脈弦数」: 肝鬱が熱化していることを示唆しています。舌が赤く、苔が黄色く、脈が弦を張り(肝)、速い(熱)のは、肝鬱化熱の典型的な舌脈です。
1.沈香散
実証の気淋や、肝鬱気滞による癃閉の治療に用いる方剤です。理気通淋の効能が、本症例の病態に最も適しています。
2.四逆散
肝気鬱結を治療する方剤ですが、直接的な通淋作用は強くありません。 内科学では使用されないです。
3.逍遥散
気鬱脾虚の黄疸などに用いる方剤です。
4.春沢湯
中気不足による癃閉に用いる方剤です。本症例の病態とは異なります。
5.六磨湯
気滞が重い便秘や、肝鬱気滞による癃閉に沈香散と併用することがあります。
問題 患者、産後一日目に排尿困難、尿量少、排尿不利、小腹墜脹でお碗の如く、精神疲労、食欲不振、気短、舌淡薄苔、脈細弱。診断はどれか?
1.淋証
2.癃閉
3.水腫
4.鼓脹
5.癥瘕
回答→2
問題 痺証の特徴で、肢体関節の疼痛が遊走性で痛処が一定しない場合、治療するために選ぶべき方剤はどれか?
1.薏苡仁湯
2.防風湯
3.九味羌活湯
4.烏頭湯
5.独活寄生湯
回答→2
【解説】
病名診断:痺証
痺証は、風、寒、湿の邪気が経絡を塞ぎ、気血の流れが悪くなることで、肢体や関節の疼痛、重だるさ、麻痺などを引き起こす病証です。
証候診断:行痺
患者の症状は、三邪(風、寒、湿)の中で風邪が優勢である行痺の病態を示しています。
⚫︎行痹の証拠
・「疼痛が遊走性で痛処が一定しない」: 風邪には「遊走」という性質があるため、痛みが体のあちこちに移動するのが最大の特徴です。
・関節の屈伸がスムーズでなく、悪風発熱を伴うこともあります。
「苔薄白、脈浮」: 風邪が体表にあることを反映しています。
1.薏苡仁湯
痺証の中でも、湿邪が優勢な着痺の治療方剤です。痛みの遊走性はなく、重だるさや腫れが主症状となります。
2.防風湯
行痺の治療方剤です。疏風作用に優れており、痛みの移動や遊走性を伴う痺証に最も適しています。
3.九味羌活湯
中医学の内科のテキストには記載されていません。
4.烏頭湯
痺証の中でも、寒邪が優勢な痛痺の治療方剤です。激しい痛みが特徴で、温めると痛みが和らぎます。
5.独活寄生湯
慢性化した痺証で、気血不足や肝腎の虚弱を伴う場合の治療方剤です。
問題 患者顧様、女、28歳。頻尿で多尿、脂膏の如く混濁する、尿は甘い味、口乾唇燥、舌質紅少苔、脈沈細数者。この治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.程氏萆薢分清飲
2.水陸二仙丹
3.六味地黄丸
4.左帰丸
5.知柏地黄丸
回答→3
【解説】
病名診断:消渇・下消
「頻尿で多尿」、「脂膏の如く混濁する」、「尿は甘い味」という症状は、消渇の中でも下消の典型的な特徴です。
証候診断:腎陰虧虚
⚫︎腎陰虧虚の証拠
・「口乾唇燥」: 陰液の不足により、口や唇が乾燥します。
⚫︎舌脈
・「舌質紅少苔」: 陰虚による虚熱が盛んであることと、津液の不足を反映しています。
・「脈沈細数」: 脈が沈んで深く(病が奥にある)、細く(陰虚)、速い(熱)のは、陰虚による虚熱の典型的な脈象です。
1.程氏萆薢分清飲
湿熱が原因で尿が濁る膏淋の実証、特に尿濁の湿熱内蘊の治療に用いる方剤です。本症例のような腎陰虚の病態とは異なります。
2.水陸二仙丹
腎虚による遺精に用いる方剤で、本症例の消渇には適しません。
3.六味地黄丸
腎陰虧虚による下消に最も適した方剤です。三補三瀉の配合により、腎陰を補いつつ、停滞した邪を瀉すバランスの取れた処方です。
4.左帰丸
腎陰を補う力が六味地黄丸より強力ですが、三瀉の作用がないため、本症例のような病態の初期には六味地黄丸の方が適している場合があります。左帰丸は腎精不足の眩暈、腎陰虚の虚労、腎陰虚の腰痛などの治療にも用いられます。
5.知柏地黄丸
六味地黄丸に知母と黄柏を加え、陰虚による虚火が盛んな病態を治療する方剤です。腎陰虧虚の労淋の治療に無比山薬丸と併用されたり、腎虚火旺の尿血、陰虚火旺の心悸、陰虚火旺の下消などの治療にも用いられたりします。
問題 四肢が痿軟で麻木し、身体困重し、足脛の発熱、胸脘部が痞悶し、小便短赤、舌苔黄膩、脈細数。治療に必要な主な方剤はどれか?
1.三仁湯
2.白虎加桂枝湯
3.羌活勝湿湯
4.加味二妙散
5.蠲痺湯
回答→4
【解説】
病名診断:痿証
「四肢が痿軟で麻木し」という症状は、痿証の最も重要な特徴です。痿証とは、四肢がだんだん無力になり、筋力が低下して動かしにくくなる病証を指します。
証候診断:湿熱浸淫・気血不運
患者の症状は、湿熱が筋や脈に浸み込み、気血の運行を妨げている湿熱浸淫・気血不運の病態を示しています。
⚫︎湿熱浸淫・気血不運の証拠
・「身体困重し」: 湿邪の重い性質によるもので、全身が重だるく感じます。
・「足脛の発熱、胸脘部が痞悶し、小便短赤」: いずれも湿熱の症状です。足が熱を帯び、胸や胃のあたりが痞え、尿が少なく色が濃いのは、湿熱が体内に停滞していることを示します。
⚫︎舌脈
・「舌苔黄膩」: 舌苔が黄色く、油っぽいのは湿熱の典型的な舌象です。
・「脈細数」: 脈が細く(虚)、速い(熱)のは、湿熱による陰液の損傷を反映しています。
1.三仁湯
湿邪が主体の湿熱病の治療に用いる方剤です。本症例のような痿証には適しません。
2.白虎加桂枝湯
風湿熱痺の治療方剤です。痺証の熱症状には適しますが、痿証の治療には直接用いられません。
3.羌活勝湿湯
風湿頭痛の治療方剤です。痿証の治療には適しません。
4.加味二妙散
・湿熱浸淫の痿証に最も適した方剤です。清利湿熱の効能により、痿証の原因である湿熱を取り除きます。
・加味二妙散は、湿熱による陰部のできものや痿証の治療に優れた方剤です。その構成生薬は、蒼朮や黄柏が湿熱を清利し、牛膝、当帰、防已、萆薢などが経絡を通し、亀板が陰を滋養するという、湿熱による痿証の病態に特化した処方となっています。
5.蠲痺湯
寒湿が優勢でない着痺(湿痺)の治療に用いる方剤です。
問題 患者、女、36歳。多食善飢、形体消痩、時に歯痛、歯齦が赤く腫れる、便秘、舌紅苔黄、脈滑。この治療で最も適切な方剤はどれか?
1.大承気湯
2.白虎湯
3.玉女煎
4.増液湯
5.二冬湯
回答→3
【解説】
病名診断:消渇・中消
「多食善飢、形体消痩」という症状は、消渇の中でも中消の典型的な特徴です。消渇は、多飲、多食、多尿を主症状とする病証で、中消は胃の熱が盛んになることで食欲が増し、体が痩せていくタイプです。
証候診断:胃熱熾盛
患者の症状は、胃に熱がこもり、その熱が盛んになっている胃熱熾盛の病態を示しています。
⚫︎胃熱熾盛の証拠
・「時に歯痛、歯齦が赤く腫れる」: 胃の経絡は歯茎や顔面を通るため、胃にこもった熱が上方に逆上し、歯の痛みや歯茎の腫れを引き起こします。
・「便秘」: 胃の熱が盛んになり、津液(体液)を消耗することで、大腸が乾燥して便秘になります。
⚫︎舌脈
・「舌紅苔黄」: 舌が赤く、苔が黄色いのは、熱邪が盛んであることを示しています。
・「脈滑」: 脈が滑らかで勢いがあるのは、熱邪や実邪が盛んなことを示しています。
1.大承気湯
胃腸の熱結や燥屎による便秘・腹痛に用いる方剤です。本症例の便秘には適応する可能性がありますが、根本的な胃熱熾盛と陰虚を治療するものではありません。
2.白虎湯
陽明病の熱盛に使用される方剤で、非常に強力な清熱作用を持ちます。中消の症状にも適応しますが、本症例の陰液不足の症状には対応しきれません。
3.玉女煎
胃熱熾盛による中消に最も適した方剤です。胃の熱を冷ます石膏と、消耗した陰液を補う熟地黄、麦門冬、知母を組み合わせることで、「清陽明(胃)補少陰(腎)」という病態に的確に対応します。
4.増液湯
津液不足による便秘に用いる方剤です。本症例の胃熱の治療には適しません。
5.二冬湯
肺と腎の気陰両虚による上消の治療に用いる方剤です。本症例の中消の病態とは異なります。
ポイント
・消渇の鑑別: 消渇は、上消(肺)、中消(胃)、下消(腎)に分けられ、それぞれ治療法が異なります。「多食善飢」が中消を判断する重要な根拠となります。
・玉女煎の効能: 玉女煎は清熱(石膏・知母)と滋陰(熟地黄・麦門冬)の両作用を兼ね備えています。これにより、胃の熱を冷ましながら、熱によって消耗した陰液を補うことができます。
・「清陽明補少陰」: 玉女煎は、陽明経(胃)の熱を清め、少陰経(腎)の陰を補うという特徴的な治療原則に基づいており、これが胃熱と陰虚が同時に存在する病態に効果を発揮する理由です。
問題 手足が軟弱で無力、筋脈が弛緩して緊張がない、肌肉が萎縮する者、診断すべきはどれか?
1.痿病
2.中風
3.痹証
4.風痱
5.痙病
回答→1
【解説】
病名診断:痿病
「手足が軟弱で無力」、「筋脈が弛緩して緊張がない」、「肌肉が萎縮する」という三つの症状は、痿病を診断する上での最も重要な特徴です。
1.痿病
四肢の筋力が低下し、軟弱無力となることを主症状とする疾病です。いただいた解説にある通り、筋脈の弛緩や筋肉の萎縮を伴うのが特徴です。
2.中風
突発的に意識障害、半身不随、言語障害などが現れる病気です。本症例の、ゆっくりと進行する筋肉の萎縮とは異なります。
3.痹証
風、寒、湿などの邪気が経絡を塞ぎ、関節や筋肉に痛み、重だるさ、麻痺などを引き起こす病証です。痛みが主症状であり、本症例の筋力低下とは異なります。
4.風痱
中風の後遺症で、特に言語障害や歩行困難などを主症状とします。本症例の筋肉の軟弱や萎縮とは病態が異なります。
5.痙病
項背の強いこわばりや、四肢のけいれん、角弓反張(体を後ろに反らせる)などを主症状とする病気です。弛緩して無力になる痿病とは正反対の症状です。
問題 消渇病の常見併発症ではないのはどれか?
1.雀盲
2.水腫
3.肺痿
4.中風
5.癰疽
回答→3
【解説】
消渇病(現代の糖尿病に類似)は、長期にわたる病態の進行に伴い、さまざまな合併症を引き起こすことがあります。これを中医学では「変証」と呼びます。
1.雀盲
・病理: 消渇病の進行により、燥熱が肝や腎の精血を損傷することで生じます。
・現代医学の対応: 糖尿病性腎症など、腎臓系の合併症に相当します。
・消渇の後半期に、陰損及陽によって脾腎の陽気が衰微した結果として現れます。
2.水腫
・病理: 燥熱による陰液の消耗が極まり、最終的に腎の陽気まで損なわれると、水分代謝が失調し、水腫が生じます。
・現代医学の対応: 糖尿病性腎症など、腎臓系の合併症に相当します
・消渇の後半期に、陰損及陽(いんそんきゅうよう)によって脾腎の陽気が衰微した結果として現れます。
3.肺痿
・病理: 肺の慢性的な虚損性疾患で、咳や痰が主症状となります。消渇病の上消は病位が肺ですが、その病理は燥熱傷津であり、虚熱型の肺痿との関連性はありますが、虚寒型の肺痿とは異なります。
・肺痿は肺の虚損性の疾患であり、その虚寒タイプは消渇の燥熱傷津の病理とは直接的に関連しません。そのため、消渇病の一般的な合併症としては挙げられにくいです。
4.中風
・病理: 陰虚燥熱が体内の津液を煮詰めて痰を生じさせ、その痰が経絡を阻滞することで心や脳の働きを妨げ、中風を引き起こします。
・現代医学の対応: 脳梗塞や脳出血など、脳血管系の合併症に相当します。
・陰虚燥熱が痰を生じ、痰が経絡を塞ぐ病理状態を反映します。
5.癰疽
・病理: 消渇病の進行により、燥熱が体内にこもり、気血の流れが悪くなることで、皮膚の局所に毒素がたまり、化膿して癰疽が生じます。
・現代医学の対応: 糖尿病性壊疽など、皮膚や軟部組織の合併症に相当します。
・消渇の後半期に、燥熱が内結して営陰を損傷し、絡脈が瘀阻した結果として生じます。
ポイント
・消渇病の変証: 消渇病は、長期にわたり津液を消耗し、陰虚や燥熱が進行することで、全身の臓腑に影響を及ぼします。
・変証の病理: 雀盲、水腫、中風、癰疽といった合併症は、それぞれ肝腎、脾腎、心脳、気血といった臓腑や経絡が、消渇病の病理(燥熱、陰虚、痰、瘀血など)によって損傷を受けた結果として生じます。
・肺痿との鑑別: 肺痿は、肺の慢性的な虚損性疾患であり、消渇の病理と直接的に結びつかない虚寒の病態も存在します。このため、他の選択肢に比べて消渇の一般的な合併症としては当てはまりにくいと判断されます。
問題 痺証で、関節の激しい痛み、腫大、僵硬、変形、屈伸が制限されることが主な症状である場合、上記のどれに属するか?
1.行痺
2.痛痺
3.着痺
4.熱痺
5.尪痺
回答→5
【解説】
1.行痺
風邪が優勢なタイプ。痛みが遊走性で定まらないのが最大の特徴です。
2.痛痺
寒邪が優勢なタイプ。激しい痛みが特徴で、温めると痛みが和らぎ、冷えると悪化します。
3.着痺
湿邪が優勢なタイプ。患部が重く、感覚が鈍く、腫脹を伴うことが多く、痛みの場所は一定です。
4.熱痺
熱邪が優勢なタイプ。関節に灼熱感や紅腫を伴い、触れると激しい痛みがあります。冷やすと痛みが和らぎます。
5.尪痺(おうひ)
痺証が慢性化し、重症化したタイプです。風寒湿の邪気だけでなく、体内の瘀血や痰湿、肝腎の虚弱が複雑に絡み合った病態です。
「尪痺の弁証」
⚫︎特徴
・「関節の激しい痛み、腫大、僵硬(きょうこう)」: 邪気の停滞が長期化し、気血の運行が著しく阻害されていることを示します。
・「変形、屈伸が制限」: 骨や筋脈の損傷が進行し、機能が失われている状態です。
・「筋肉萎縮」: 長期の関節の機能障害により、筋肉が使われなくなり萎縮します。
⚫︎病理
・尪痺は、単なる外邪の侵入だけでなく、外邪、内邪(瘀血・痰湿)、腎虚が同時に存在しているという複合的な病態です。
⚫︎進展
・進行が遅く、長期間かけて徐々に悪化します。最終的には関節が変形し、硬化する「骨痺」へと進展することもあります。
治療方剤ー独活寄生湯
・効能: 風湿を祛り、痺痛を止め、肝腎を益し、気血を補うという、尪痺の複雑な病理に総合的に対応できる方剤です。
・構成生薬: 独活、細辛、秦艽、防風などで風湿を祛り、桑寄生、杜仲、牛膝などで肝腎を補い、人参、茯苓、甘草、当帰、白芍、熟地黄などで気血を補うことで、根本から治療します。
問題 患者、女、58歳。ここ3ヶ月、全身の乏力感を自覚、だんだんと下肢が痿軟無力となり、関節の活動が不利となり、少気懶言、神疲乏力、面浮不華、食少納呆、腹脹便溏が現れてきた。舌淡、舌体胖大、苔白、脈沈細。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.加味二妙散
2.補中益気湯
3.参苓白朮散
4.実脾飲
5.八珍湯
回答→3
【解説】
病名診断:痿証
「下肢が痿軟無力となり、関節の活動が不利となり」という症状は、痿証の最も重要な特徴です。痿証とは、四肢の筋力低下、筋脈の弛緩、筋肉の萎縮が進行する病証です。
証候診断:脾胃虧虚
患者の症状は、脾胃の機能が虚弱になり、気血を生み出す力が不足している脾胃虧虚の病態を示しています。
⚫︎虚証の証拠
・「ここ3ヶ月、全身の乏力感」: 長期間にわたる症状の進行は、虚証の痿証の特徴です。
・「少気懶言、神疲乏力、面浮不華」: 気が少なく話すのが億劫で、精神的に疲労し、顔色に華やかさがないのは、気血不足による症状です。
⚫︎脾胃虚弱の証拠
・「食少納呆、腹脹便溏」: 食欲不振、お腹の張り、泥のような便は、脾胃の運化機能が失調していることを示します。
⚫︎舌脈
・「舌淡、舌体胖大、苔白」: 舌の色が淡く、舌体が大きくむくみ、苔が白いのは、脾気虚と水湿の停滞を反映しています。
・「脈沈細」: 脈が深く(沈)、細いのは、正気が不足している虚証の脈象です。
治法と方剤
・治法: 健脾益気、滲湿和胃。脾胃の機能を回復させ、気を補い、体内の湿邪を排出し、胃の働きを整えます。
・代表方剤: 参苓白朮散
1.加味二妙散
湿熱浸淫の痿証に用いる方剤です。本症例の脾胃虚弱による虚寒の病態とは異なります。
2.補中益気湯
中気不足、特に気虚下陥による痿証に用いる方剤です。昇陽作用が強いのが特徴です。
3.参苓白朮散
脾胃虧虚の痿証に最も適した方剤です。脾胃を健やかにし、気を益し、湿を排出する効能があり、本症例の「脾虚湿盛」という病態に的確に対応します。
4.実脾飲
脾陽虚衰による水腫に用いる方剤です。本症例の痿証が主症状とは異なります。
5.八珍湯
気血両虚を治療する方剤です。本症例の脾虚湿盛の病態には、利湿作用のある参苓白朮散がより適しています。八珍湯は気血虧虚の石淋や虚証の気淋などの治療にも用いられます。
ポイント
・補中益気湯と参苓白朮散の鑑別: どちらも脾胃の虚弱を治療しますが、補中益気湯は「昇陽」の作用が強く、めまいや脱肛などの症状を伴う場合に適しています。一方、参苓白朮散は「滲湿」の作用が強く、本症例の「腹脹便溏」「舌体胖大」といった湿盛の症状が顕著な場合に適しています。
問題 手足が軟弱で無力、筋脈が弛緩して緊張がない、肌肉が萎縮する者、診断すべきはどれか?
1.痿病
2.中風
3.痺証
4.風痱
5.痙病
回答→1
問題 痺証の特徴で、肢体関節の疼痛が遊走性で痛処が一定しない場合、治療するために選ぶべき方剤はどれか?
1.薏苡仁湯
2.防風湯
3.九味羌活湯
4.烏頭湯
5.独活寄生湯
回答→2
【解説】
病名診断:痺証
証候診断:行痺
1.薏苡仁湯
痺証の中でも、湿邪が優勢な着痺の治療方剤です。痛みの遊走性はなく、重だるさや腫れが主症状となります。
2.防風湯
行痺の治療方剤です。疏風作用に優れており、痛みの移動や遊走性を伴う痺証に最も適しています。
3.九味羌活湯
中医学の内科のテキストには記載されていない方剤です。
4.烏頭湯
痺証の中でも、寒邪が優勢な痛痺の治療方剤です。激しい痛みが特徴で、温めると痛みが和らぎます。
5.独活寄生湯
慢性化した痺証で、気血不足や肝腎の虚弱を伴う場合の治療方剤です。
問題 風寒湿痺の共通の症状はどれか?
1.関節が腫大し変形し、肌肉が萎縮
2.肢体関節が重着し、或いは腫脹がある
3.肢体関節が疼痛し、屈伸しにくい
4.関節が紅く腫れて熱痛し、触れると痛む
5.肢体の筋脈が弛緩し、軟弱無力
回答→3
問題 患者、男、38歳。口乾唇燥により、口渇多飲、尿頻で尿量が多い、脂膏の如く混濁する、時に煩燥、手足心熱、遺精、舌質紅苔薄黄、脈象細数。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.左帰丸
2.玉女煎
3.消渇方
4.白虎加人参湯
5.知柏地黄丸
回答→5
【解説】
病名診断:消渇・下消
「口渇多飲、尿頻で尿量が多い」という症状は、消渇の中でも下消の典型的な特徴です。
証候診断:陰虚火旺を伴う腎陰虧虚
患者の症状は、腎の陰液が不足している腎陰虧虚に、さらに虚熱が盛んになった陰虚火旺の病態を示しています。
⚫︎腎陰虧虚の証拠
・「口乾唇燥」は、陰液の不足による乾燥症状です。
・「口渇多飲、尿頻で尿量が多い」は、腎陰が不足しているために、津液の代謝が失調していることを示します。
⚫︎陰虚火旺の証拠
・「時に煩燥、手足心熱、遺精」: 陰虚による虚火が上炎し、心の働きを乱し、性機能に影響を与えていることを示します。
⚫︎舌脈
・「舌質紅苔薄黄」: 舌が赤く、苔が薄く黄色いのは、陰虚による虚熱の存在を示唆しています。
・「脈象細数」: 脈が細く(陰虚)、速い(熱)のは、陰虚火旺の典型的な脈象です。
1.左帰丸
腎精不足の偏陰虚に用いる方剤です。虚火を冷ます作用がないため、本症例の陰虚火旺には不十分です。
2.玉女煎
胃熱熾盛による中消に用いる方剤です。本症例は腎の症状が主であるため、適しません。
3.消渇方
上消(肺)の病態に用いる方剤です。本症例の病態とは異なります。
4.白虎加人参湯
上消で肺胃の熱が盛んで、気陰を消耗している場合に用いる方剤です。本症例の病態とは異なります。
5.知柏地黄丸
陰虚火旺を伴う腎陰虧虚の下消に最も適した方剤です。腎陰を補う六味地黄丸に、虚火を冷ます知母と黄柏を加えることで、本症例の病態に的確に対応します。
ポイント
⚫︎腎陰虧虚と陰虚火旺の鑑別: 腎陰虧虚に加えて、「煩躁」「手足心熱」「遺精」「脈数」といった熱の症状が顕著な場合は、陰虚火旺と判断します。
⚫︎知柏地黄丸の効能と構成
・知母と黄柏を加えることで、火を瀉し、陰を固める「苦寒堅陰」という配合が特徴です。
・知母の潤性と黄柏の燥性が相殺し、瀉火の効能がより効果的に働くという、薬の配合の妙が凝縮されています。
・このため、六味地黄丸よりも虚火を冷ます作用が強力であり、本症例のような病態に最も適しています。
・知柏地黄丸は、腎陰虧虚の労淋の治療に無比山薬丸と併用されることもあり、腎虚火旺の尿血、陰虚火旺の心悸などの治療にも広く用いられます。
問題 患者、女、34歳。煩渇により、多飲が比較的甚だしい、口乾舌燥、小便頻数で尿量が比較的多い、舌苔薄黄、脈洪数無力。この治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.消渇方
2.二陰煎
3.清肺飲
4.二冬湯
5.白虎湯
回答→1
【解説】
病名診断:消渇・上消
「多飲が比較的甚だしい、小便頻数で尿量が比較的多い」という症状は、消渇の中でも上消の典型的な特徴です。
証候診断:肺熱津傷
患者の症状は、肺に熱がこもり、その熱によって津液(体液)が損傷された肺熱津傷の病態を示しています。
⚫︎肺熱津傷の証拠
・「煩渇により、多飲が比較的甚だしい」: 肺の熱が津液を消耗することで、口の渇きが非常に強くなり、多飲を伴います。
・「口乾舌燥」: 肺の熱による津液の消耗が、口や舌の乾燥として現れています。
⚫︎舌脈
・「舌苔薄黄」: 舌苔が薄く黄色いのは、熱邪が体表にあることを示唆しています。
・「脈洪数無力」: 脈が大きく(洪)、速い(数)のは熱邪が盛んなこと、無力なのは津液の不足を反映しています。
1.消渇方
上消の治療に特化した方剤です。養陰生津、清熱潤燥の効能により、肺熱津傷の病態に的確に対応します。
2.二陰煎
火盛傷陰による狂証に用いる方剤です。消渇の治療には適しません。
3.清肺飲
肺熱による癃閉の治療方剤です。本症例のような津液の消耗が主体の病態には適しません。
4.二冬湯
肺と腎の気陰両虚を伴う上消に用いる方剤です。本症例はまだ虚証が顕著ではなく、肺熱が主体の初期段階であるため、よりシンプルな消渇方が適しています。
5.白虎湯
熱病の治療に用いる方剤ですが、単独では津液の補充作用が不十分な場合があります。
ポイント
・消渇の鑑別: 消渇は多飲・多食・多尿のどの症状が最も顕著かによって、上消(多飲)、中消(多食)、下消(多尿)に分けられます。本症例の「多飲が比較的甚だしい」という点が上消を判断する重要な根拠です。
・消渇方の効能と構成: 消渇方は天花粉、生地黄汁、蓮根汁、牛乳といった生津潤燥の生薬や食材を多く含み、肺の熱を清め、津液を補う作用に優れています。
・他の上消治療方剤との比較: 白虎加人参湯も上消に用いられますが、消渇方はより養陰生津に重点を置いた処方であり、本症例の病態に合致しています。
問題 気虚型虚労の主な症状はどれか?
1.面色不華、唇甲色淡
2.五心煩熱、口乾咽燥
3.短気乏力、自汗便溏
4.神倦嗜臥、形寒肢冷
5.気短乏力、咳嗽咳痰
回答→3
【解説】
虚労は、多種の原因によって臓腑が損傷し、気、血、陰、陽が不足する慢性的な病態の総称です。この虚労の弁証では、まず気虚、血虚、陽虚、陰虚といった「四虚」のどれに当てはまるかを鑑別し、次に病変のある臓腑を特定します。
1.面色不華、唇甲色淡
顔色が悪く、唇や爪の色が薄いのは、血虚型虚労の典型的な症状です。
2.五心煩熱、口乾咽燥
手足のひらや胸部が熱感を帯び、口や喉が乾燥するのは、陰虚型虚労の典型的な症状です。
3.短気乏力、自汗便溏
短気乏力は気虚の共通症状であり、自汗は気虚全般に、便溏は特に脾気虚に現れる症状です。したがって、これは気虚型虚労の主な症状です。
4.神倦嗜臥、形寒肢冷
精神的にだるく横になりたがり、体が寒がりで手足が冷えるのは、陽虚型虚労の典型的な症状です。
5.気短乏力、咳嗽咳痰
気短乏力は気虚の共通症状ですが、咳嗽咳痰は肺に病変がある場合に特に見られる症状です。したがって、これは肺気虚型虚労に属する症状です。
問題 脾気虚型の虚労を治療する主な方剤はどれか?
1.附子理中丸
2.拯陽理労湯
3.参苓白朮散
4.帰脾湯
5.加味四君子湯
回答→5
【解説】
1.附子理中丸
脾陽虚や脾腎陽虚に用いる方剤です。本症例のような脾気虚には、補陽作用が強すぎるため適しません。
2.拯陽理労湯
心陽虚の虚労に用いる方剤です。本症例の脾気虚とは病位が異なります。
3.参苓白朮散
脾気虚に加えて湿邪が停滞している病態に用いる方剤で、利湿作用が強いのが特徴です。
4.帰脾湯
心脾両虚の不眠や、心血不足の動悸などに用いる方剤です。
5.加味四君子湯
脾気虚の虚労に最も適した方剤です。基本的な補気剤である四君子湯に、気を補う黄耆と利湿作用のある白扁豆が加わることで、脾気虚の病態を総合的に治療できます。
ポイント
・四君子湯との違い: 加味四君子湯は、基本の四君子湯(人参、茯苓、白朮、甘草)に、さらに気を補う黄耆と利湿作用を持つ白扁豆を加えることで、脾気虚の病態に特化して強化された処方です。
・脾気虚の診断: 「飲食減少」「大便溏薄」「面色萎黄」といった脾胃の機能失調を示す症状が、脾気虚型虚労を診断する上での重要な根拠となります。
問題 陽虚型虚労の主な症状はどれか?
1.面色不華、唇甲色淡
2.五心煩熱、口乾咽燥
3.短気乏力、自汗便溏
4.神倦嗜臥、形寒肢冷
5.気短乏力、咳嗽咳痰
回答→4
問題 陰虚発熱型の内傷発熱を治療するために選ぶべき方剤はどれか?
1.大補陰丸
2.六味地黄丸
3.清骨散
4.左帰丸
5.以上どれも当てはまらない
回答→3
【解説】
病名診断:内傷発熱
証候診断:陰虚発熱
1.大補陰丸
陰虚火旺による遺精などに用いる方剤です。陰を補う力が主で、熱を清める作用は比較的穏やかです。
2.六味地黄丸
腎陰虧虚による下消などの治療に用いる基本の滋陰剤です。陰を補う作用が主で、清熱作用は強くありません。
3.清骨散
陰虚発熱の治療に特化した方剤です。虚熱を清める作用が優れており、特に骨蒸熱に効果を発揮します。
4.左帰丸
腎陰虚による腰痛などに用いる方剤です。陰を補う作用が強力ですが、清熱作用はほとんどありません。
ポイント
・清骨散の効能と構成: 清骨散は清虚熱、退骨蒸の効能が最も優れています。その構成は、銀柴胡、胡黄連、秦艽、地骨皮、青蒿といった虚熱を清める生薬が主体であり、滋陰の薬は知母と鼈甲に留められています。
・他の滋陰剤との違い: 知柏地黄丸、六味地黄丸、大補陰丸、左帰丸はいずれも陰虚を治療する代表的な方剤ですが、清熱の力が不十分であるため、発熱が主症状である陰虚発熱には、まず清骨散で虚熱を鎮める治療が優先されます。
・治療の段階: まずは清骨散で熱を下げ、熱が鎮まった後に、六味地黄丸などで陰を補う治療に移行するのが一般的な治療方針です。
問題 内傷発熱で、肝鬱発熱の臨床特徴はどれか?
1.発熱が常に疲労後に発生する或いは憎悪する
2.午後或いは夜間に発熱
3.熱勢が常に情緒波動により増減する
4.熱感を自覚する部位がある
5.五心煩熱
回答→3
問題 気虚発熱の病理特徴は陽気が陰中へ下陥して陽気が鬱熱になり、陰火が生じて発熱する。
1.正しい
2.誤っている
回答→1
【解説】
気虚発熱とは、体内の正気(気)が不足することで生じる発熱です。この病態の最も重要な病機は、「陽気が陰中へ下陥して鬱熱になり、陰火が生じる」ことです。
具体的には、以下の流れで病態が形成されます。
1・鬱熱と陰火: 下陥した陽気は、陰気の寒さによって鬱滞し、熱に変わります。この熱を「陰火」と呼び、これが発熱の原因となります。
2・中気不足: 脾胃の気が不足する(中気不足)。
3・気の昇降失調: 脾胃の気には、清陽を上へ昇らせる働きがあります。この機能が失調すると、清陽が上昇できなくなります。
4・陽気の下陥: 上昇すべき清陽が、逆に陰性の領域(陰中)へと下陥してしまいます。
問題 湿熱浸淫型の痿証を治療する主要な方剤はどれか?
1.加味二妙散
2.香砂六君子湯
3.益胃湯
4.参苓白朮散
5.甘露消毒丹
回答→1
【解説】
1.加味二妙散
気血不運の痿証に最も適した方剤です。清利湿熱の効能により、痿証の原因である湿熱を取り除きます。
2.香砂六君子湯
寒湿による胃腸の虚弱に用いる方剤です。本症例の湿熱の病態とは異なります。
3.益胃湯
胃陰や肺胃の陰が不足した病態に用いる方剤です。特に、肺胃陰傷による痿証の治療に用いられます。
4.参苓白朮散
脾胃虧虚、精微不運による痿証の治療方剤です。湿熱による実証の病態には適しません。
5.甘露消毒丹
湿熱による発熱や黄疸などに用いる方剤です。
問題 脾胃虧虚型の痿証を治療する主要な方剤はどれか?
1.加味二妙散
2.香砂六君子湯
3.益胃湯
4.参苓白朮散
5.甘露消毒丹
回答→4
問題
1.
2.
3.
4.
5.
回答→
【解説】
問題
1.
2.
3.
4.
5.
回答→
【解説】
問題
1.
2.
3.
4.
5.
回答→
【解説】