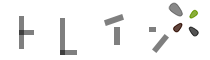問題 小児生理の特徴に関する記述で誤っているのはどれか。
1.臓腑嬌嫩、形気未充
2.稚陽未充、稚陰未長
3.発育迅速、形気漸充
4.年齢が進めば、その成長発育が速くなる
5.体格と智力が同時に成長する
回答→4
【解説】
中医学では、小児は「稚陽未充、稚陰未長(ちようみじゅう、ちいんみちょう)」という特徴を持ち、臓腑の機能が未熟であると考えます。しかし、その成長発育は非常に迅速です。
1.臓腑嬌嫩、形気未充
正しい。「臓腑嬌嫩(ぞうふきょうどん)」とは、臓腑の機能がまだ未熟で繊細であることを意味します。「形気未充(けいきみじゅう)」とは、体形や気の力がまだ十分に満ちていないことを意味します。これは小児の生理の基本的な特徴です。
2.稚陽未充、稚陰未長
正しい。小児の陽気はまだ未熟で、陰液もまだ十分に成長していないという意味で、小児の生理を的確に表しています。
3.発育迅速、形気漸充
正しい。「発育迅速」とは成長が速いこと。「形気漸充」とは、体形や気の力が徐々に満ちていくことを意味します。これも小児生理の特徴です。
4.年齢が進めば、その成長発育が速くなる
間違い。小児の成長発育は、一般的に年齢が若いほど速く、年齢が進むにつれて徐々に緩やかになります。思春期には再び急激な成長期を迎えますが、全体的な傾向としてはこの記述は誤りです。
5.体格と智力が同時に成長する
正しい。中医学では、腎は「精」を貯蔵し、これは生殖や成長、そして脳の機能(智力)に関わると考えます。したがって、体格の発育と智力の成長は、腎の精の充実とともに進むと考えられ、これは正しい記述です。
問題 小児の疾病を診断するために、最も重要なことはどれか。
1.按診
2.脈診
3.問診
4.望診
5.聞診
回答→4
【解説】
小児は、自分の症状を正確に言葉で表現することが難しいため、問診や脈診が成人ほど有効ではありません。特に乳幼児の場合、言葉による情報がほとんど得られません。このため、小児の診断では、言葉に頼らずに直接観察できる望診が最も重要となります。
問題 小児の中薬の使用量が相対的に多い理由はどれか。
1.生薬に対する耐受性強い
2.投薬後の効果が比較的遅い
3.多くは急性の重病
4.用薬時間は短く、服薬時は常に浪費的
5.どれも違う。
回答→4
【解説】
小児への投薬量が相対的に多いのは、服薬時のロスを考慮し、有効な薬の量を確保するためです。
問題 新生児が必要とする中薬の服薬量は成人と比べるとどれか。
1.1/6
2.1/3
3.1/2
4.1/4
5.1/5
回答→1
【解説】
中医学の臨床経験に基づくと、小児への投薬量は、成人の量(通常は15〜20g程度)を基準に、年齢や体重、病状に応じて調整されます。
・新生児(出生後28日以内):成人の1/6
・1〜3歳:成人の1/3
・3〜7歳:成人の1/2
・7〜12歳:成人の2/3
問題 小児の傷食嘔吐を治療するためにまず選ぶべき方剤はどれか。
1.保和丸
2.香砂六君子湯
3.小承気湯
4.理中丸
5.瀉黄散
回答→1
【解説】
傷食とは、飲食物の消化不良が原因で起こる病態です。小児は脾胃の機能が未熟なため、食べ過ぎたり消化の悪いものを食べたりすると、飲食物が脾胃に停滞して傷食を起こしやすくなります。
1.保和丸ー消食和胃
傷食による消化不良を治療する代表的な方剤です。山査子、神曲、莱菔子といった、停滞した飲食物を強力に消化させる生薬で構成されており、小児の傷食嘔吐に最も適しています。
2.香砂六君子湯ー益気健脾、和胃化痰
脾胃の虚弱が原因の食欲不振や吐き気に用いる方剤です。消化不良(傷食)の「実証」ではなく、脾胃の「虚証」に用います。
3.小承気湯ー軽下熱結
便秘を伴う腸の熱結に用いる方剤で、嘔吐の治療には適しません。
4.理中丸ー温中健脾
脾胃の虚寒が原因の嘔吐や下痢に用います。消化不良による「実証」には不適切です。
5.瀉黄散ー瀉脾胃伏火
脾胃の熱が原因の症状に用いる方剤です。嘔吐の治療には直接用いられません。
問題 小児の脾胃虚寒の腹痛の治法はどれか。
1.温中散寒 理気止痛
2.消食導滞 行気止痛
3.温中理脾 緩急止痛
4.活血化瘀 行気止痛
5.健脾和胃 理気止痛
回答→3
【解説】
脾胃虚寒とは、脾胃の陽気が不足し、冷えによって機能が低下した病態です。小児は「稚陽未充」といって、もともと陽気が不足しがちなので、冷たい飲食物や外気の冷えにより、脾胃虚寒になりやすいです。
1.温中散寒 理気止痛
温中散寒は正しいですが、「理気」は気の巡りを良くする治法で、脾胃虚寒には直接的ではありません。
2.消食導滞 行気止痛
飲食物の停滞による腹痛(傷食)の治法であり、脾胃虚寒には不適切です。
3.温中理脾 緩急止痛
・温中散寒:中焦(脾胃)を温め、冷えを取り除く。
・理脾:脾の働きを整える。
・緩急止痛:痛みを和らげ、急迫した症状を緩める。
4.活血化瘀 行気止痛
血の滞り(瘀血)による腹痛に用いる治法です。
5.健脾和胃 理気止痛
脾胃の虚弱が原因ですが、冷え(寒)の要素を捉えられていません。
問題 小児の傷食泄瀉を治療するためにまず選ぶべきはどれか。
1.木香順気丸
2.枳実導滞丸
3.保和丸
4.木香檳榔丸
5.どれも違う
回答→3
【解説】
1.木香順気丸
脾胃の気の停滞と湿邪が原因の腹満、下痢に用いる方剤です。傷食(飲食物の停滞)には直接対応していません。
2.枳実導滞丸
消化不良が原因で、便秘や腹満が主症状となる病態に用いる方剤です。「泄瀉(下痢)」には不適切です。
3.保和丸
山査子、神曲、莱菔子といった、停滞した飲食物を消化させる生薬で構成されています。消化不良による腹満や下痢(泄瀉)を治療する代表的な方剤であり、小児の傷食泄瀉に最も適しています。
4.木香檳榔丸
気の停滞や熱が原因の便秘や腹痛に用いる方剤です。下痢には適しません。
問題 小児の脾腎陽虚泄瀉を治療するためにまず選ぶべきはどれか。
1.四神丸
2.附子理中丸
3.訶子散
4.固腸丸
5.どれも違う
回答→2
【解説】
1.四神丸
腎陽虚による五更泄瀉に用いる代表的な方剤です。脾腎陽虚に用いますが、理中丸と比較して、より腎陽虚に特化しています。
2.附子理中丸
理中丸に附子という生薬が加わった方剤です。理中丸は脾胃の冷えを温める作用がありますが、附子が加わることで、脾の陽気だけでなく、腎の陽気を温める作用が強化されます。したがって、脾腎陽虚による下痢に最も適した方剤です。
3.訶子散
慢性的な下痢に用いますが、脾腎陽虚を温める作用は強くありません。
4.固腸丸
下痢を止める作用が主で、脾腎の陽気を補う作用は強くありません。
問題 乳食内積の積滞の臨床特徴に属さないのはどれか。
1.乳片を嘔吐する
2.腹満脹痛
3.腹満でうつ伏せが楽
4.大便酸臭
5.食欲不振
回答→3
【解説】
乳食内積とは、乳幼児が乳汁や飲食物を消化しきれずに胃腸に停滞させ、消化不良を起こした病態です。中医学では積滞と呼ばれます。
腹満がある場合、腹部が圧迫されるうつ伏せは通常、苦しくなります。うつ伏せが楽になるのは、腹部に冷えがある場合や、腹部の筋肉が緊張している場合など、他の病態でみられることがあります。乳食内積による腹満では、うつ伏せは不快に感じることが多いです。
問題 慢驚風の常見症状に属さないのはどれか。
1.発病が緩やかで、攣ったり止んだりしている
2.時に頭が揺れる、 あるいは、顔面の筋肉が引きつり、片側の肢体が痙攣する。
3.面色が蒼白、萎黄
4.精神疲倦、嗜睡或いは昏迷の状態
5.高熱痙攣
回答→5
【解説】
小児の痙攣を伴う病態は、中医学では主に「急驚風」と「慢驚風」に分類されます。
「急驚風」
・病因: 外感六淫、食積、驚嚇など、実邪が原因。
・特徴: 発病が急で、高熱を伴うことが多い。痙攣は強い。
「慢驚風」
・病因: 長期にわたる病気や消耗により、脾や腎の虚弱が原因。
・特徴: 発病が緩やかで、熱は主症状ではない。痙攣は比較的弱く、発作と寛解を繰り返す。
1.発病が緩やかで、攣ったり止んだりしている
正しい。慢驚風は、虚弱が原因であるため、発病が急ではなく緩やかで、痙攣も断続的に現れるのが特徴です。
2.時に頭が揺れる、 あるいは、顔面の筋肉が引きつり、片側の肢体が痙攣する。
正しい。慢驚風の痙攣は、全身性の強いものではなく、頭が揺れたり、顔の引きつり、片側の肢体の痙攣など、比較的弱い痙攣が一般的です。
3.面色が蒼白、萎黄
正しい。脾の虚弱や気血の不足が原因であるため、顔色は青白かったり、黄色っぽかったりします。
4.精神疲倦、嗜睡或いは昏迷の状態
正しい。気血が不足し、精気が消耗しているため、精神的に疲れていたり、眠りがちになったり、重症の場合は昏迷に陥ることもあります。
5.高熱痙攣
間違い。高熱痙攣は、急驚風の最も典型的な症状です。慢驚風は虚弱が原因であるため、高熱を伴うことは稀です。
問題 猩紅熱の特徴はどれか。
1.丘疹、疱疹、痂皮が同時に現れる
2.口腔の粘膜斑
3.耳後及び枕部に臀核が大きく腫れる
4.口の周りに蒼白色の輪圏があり、イチゴ状の舌、皮膚に線状湿疹
5.黏膜に湿疹が多く見られる
回答→4
問題 水痘の徴候は発熱の他に皮膚に何回かに分けて出る症状はどれか。
1.斑疹
2.斑疹 丘疹
3.丘疹 疱疹
4.丘疹 疱疹 結痂
5.膿疱
回答→4
問題 流行性耳下腺炎の頬腫の特徴でないのはどれか。
1.耳たぶを中心に漫腫
2.皮膚が赤くなる
3.腫れのへりがはっきりしていない
4.触ると弾力と圧痛がある
5.発病の最初に発熱があるかもしれない
回答→2
【解説】
流行性耳下腺炎は、中医学では痄腮(ささい)と呼ばれます。その病因は、温毒の邪気が体内に侵入し、少陽経と太陽経に停滞することで、耳下腺の腫れや痛み、発熱などの症状を引き起こします。
温毒が停滞しているため、発熱や熱感を伴いますが、一般的に皮膚の表面は赤くならず、色は変化しないのが特徴です。皮膚が赤く腫れるのは、局所の熱毒が非常に盛んな乳癰などの病態でよく見られます。
問題 流行性耳下腺炎の症状でないのはどれか。
1.耳下腺部が腫れて疼痛
2.腫脹部位の境界がはっきりせず、表皮は赤くない。
3.口を開くのに支障があり、耳下腺管口の紅腫
4.年齢が大きな児童は睾丸の腫痛を併発する。
5.重症患者は、耳下腺管口を押すと膿液が出る。
回答→5
問題 患者、女45歳、発熱悪寒、肢体痠痛、頭痛無汗、渇喜熱飲、鼻塞、流清涕、苔薄白、脈浮緊。治療するためにまず選ぶべきはどれか。
1.桂枝湯
2.川芎茶調散
3.参蘇飲
4.荊防敗毒散
5.桑菊飲
回答→4
【解説】
・発熱悪寒、頭痛無汗、鼻塞、流清涕:悪寒が強く、汗がない(無汗)ことから、病邪が体表を閉塞している表証であることがわかります。特に、悪寒が強く、流れる鼻水が透明(清涕)であることから、寒邪が原因であると判断できます。
・肢体痠痛:風寒の邪気が経絡を阻害し、気の巡りを悪くするため、手足がだるく痛む症状が現れます。
・渇喜熱飲:喉の渇きはありますが、冷たい飲み物ではなく温かい飲み物を好むことから、体の内側に熱が盛んではないことを示唆しています。
・苔薄白:舌苔が薄く白いのは、病邪が体表にあることを示します。
・脈浮緊:浮は病邪が体表にあることを示し、緊は寒邪が経絡を緊縮させていることを示しています。
これらの症状を総合すると、病因は風寒であり、病態は表寒証と診断されます。
1.桂枝湯(辛温解表剤)ー解肌、和営衛
風邪による表虚証、つまり、悪寒はあるが汗が出るタイプの風邪に用います。無汗のこの症例には不適切です。
2.川芎茶調散ー疏風止痛
風邪による頭痛に特化した方剤です。全身の表寒証を治療するのには不十分です。
3.参蘇飲(扶正解表剤)ー益気解表、理気化痰
気虚を伴う風寒の感冒に用います。この患者は気虚の症状が明確ではないため、まず選ぶべきではありません。
4.荊防敗毒散(扶正解表剤)ー疏風散寒、解毒
風寒の邪気が盛んで、表証が強い病態に用いる代表的な方剤です。悪寒、無汗、頭痛などの症状に広く対応します。本症例に最も適しています。
独活 羌活 川芎 柴胡 桔梗 枳穀 茯苓 甘草 防風 荊芥
5.桑菊飲(辛涼解表剤)ー疏風清熱
風邪による表熱証、つまり、発熱が強く、喉の痛みなどを伴う風邪に用います。本症例の表寒証には不適切です。
問題 患者、女56歳、発熱、微悪風寒、時有汗出、頭痛、鼻塞涕濁、口乾かつ口渇、咽喉に紅腫疼痛、咳嗽、痰黄粘稠、苔薄膩、脈浮数。これはどの証に感冒に属すか。
1.風熱挟湿
2.風熱挟暑湿
3.風熱挟燥
4.風熱
5.時行感冒
回答→4
【解説】
患者の症状(発熱、咽喉の紅腫疼痛、黄色く粘り気のある痰、脈浮数など)は、風熱感冒の典型的な症状と一致します。したがって、正解は風熱です。
問題 発熱悪寒、咳嗽、痰の量は少なかったが次第に増加、痰は白粘、咳をすると胸痛が甚だしくなり、呼吸不利、口乾鼻燥、舌苔薄黄、脈浮数滑。治療するためにまず選ぶべきはどれか。
1.桑菊飲
2.桑杏湯
3.瀉白散
4.止嗽散
5.銀翹散
回答→5
【解説】
「発熱悪寒、咳」という症状は、風熱の邪が体表(衛表)から肺に侵入する病態(風熱犯肺)を反映しており、この段階ではまだ軽症の風熱感冒と見なされます。
しかし、その後に「痰の量が次第に増加し、白く粘る」「咳をすると胸痛が甚だしくなり、呼吸が苦しくなる」といった症状が加わると、これは単なる感冒の範疇を超え、邪気が肺の内部に深くこもり、熱と痰が結びついて肺癰という膿瘍が形成され始めた可能性を示唆しています。
この病態の進行を脈診からも読み取ることができます。「脈浮数滑」の「浮数」は風熱表証を、「滑」は痰熱の停滞を示しており、表の邪と内の痰熱が共存している状態を表します。
このように、初期肺癰は、以下の点で風熱感冒や風燥咳嗽と鑑別されます。
・風熱感冒との鑑別点:風熱感冒では通常、痰が次第に増えたり、胸痛を伴うことはありません。
・風燥襲肺との鑑別点:風燥襲肺では、口や鼻の乾燥はありますが、痰の増加は通常見られません。
したがって、この初期肺癰の治療では、表の風熱を散らし(発散)、同時に肺にこもった熱を冷まして解毒し、熱によって痰が増えるのを防ぐ必要があります。この目的のために、銀翹散を用いることは、理にかなった治療法であると考えられます。
1.桑菊飲
風熱感冒の比較的軽症の段階に適しており、本症例の痰熱が盛んな病態には効力が不十分です。
2.桑杏湯
燥邪による咳に特化しており、熱邪が盛んで痰が絡む本症例には適しません。
3.瀉白散
肺の熱を冷ます作用がありますが、体表の邪気を発散させる「解表」作用がないため、発熱悪寒を伴うこの病態には不適切です。
4.止嗽散
外感の邪気が去った後、咳だけが残った病態に用いるため、発熱がある本症例には不適切です。
5.銀翹散
この方剤は、発熱や悪寒といった体表の風熱を速やかに発散させると同時に、強力な清熱解毒作用で肺にこもった熱を冷まします。これにより、熱がさらに痰を増やすのを防ぎ、病態の進行を食い止めることが期待できます。
金銀花 連翹 牛蒡子 淡豆豉 薄荷 竹葉 桔梗 甘草 荊芥穂
問題 発熱微悪風寒、無汗、肢体痠重、頭昏重脹痛、鼻流濁涕、咳吐痰粘、胸悶氾悪、煩渇尿赤、舌苔薄黄膩、脈濡数が見られる。その治法はどれか?
1.清暑袪湿解表
2.祛風散寒除湿
3.疏風散寒 宣肺止咳
4.辛涼解表 清宣肺熱
5.清暑袪湿 粛肺止咳
回答→1
【解説】
病名診断:感冒
証候診断:暑湿感冒
表(体表)の病態:
・「発熱微悪風寒、無汗」:これは、外邪である風寒の邪が体表に侵入し、発汗を妨げている状態、すなわち表寒証を反映しています。
裏(体内)の病態:
・「鼻流濁涕、咳吐痰粘」:これは、体内にこもった暑熱が肺を侵し、肺の清粛機能を失わせた結果、汚れた鼻水や粘り気のある痰が生成されていることを示します。
・「肢体痠重、頭昏重脹痛、胸悶」:これらの症状は、湿邪が体内に停滞し、気の巡りを阻害していることを示しています。
・「煩渇尿赤、舌苔薄黄膩、脈濡数」:これらは、暑熱と湿邪が結びついた暑湿の病態を強く示唆しています。特に、舌苔の「黄」は熱を、「膩」は湿を、脈の「濡」は湿を、「数」は熱を表しています。
治法は清暑袪湿解表です。この病態の代表的な方剤には、辛温解表薬である香薷を主薬とする新加香薷飲などがあります。
香薷は「夏の麻黄」とも呼ばれ、暑湿感冒における解表の役割を果たします。
問題 咳嗽声重、痰白清稀、喉痒、鼻塞流清涕を伴う、無汗、舌苔薄白、脈浮緊。まず選ぶべき方剤はどれか?
1.麻黄湯
2.三拗湯
3.止嗽散
4.小青竜湯
5.三拗湯合止嗽散
回答→5
【解説】
本症例は、無汗や脈浮緊から寒邪の強さがうかがえ、喉痒や痰を伴うことから風邪と痰の要素も強く認められます。したがって、三拗湯の「宣肺解表」と止嗽散の「止咳化痰、疏風」という効能を組み合わせることで、風寒という病因と、痰という病理産物を同時に治療できる、三拗湯合止嗽散が最も適切な方剤となります。
病名診断:咳嗽
証候診断:風寒襲肺
・外感の証拠:「無汗、舌苔薄白、脈浮緊」は、外邪が体表を閉塞し、肺に侵入していることを示します。
・風寒の証拠:「痰白清稀、鼻塞流清涕」は、病邪が冷たい性質(寒)を持つことを示します。
・「咳嗽声重」:咳の音が重く力強いのは、肺に邪気がこもった実証の咳の特徴です。
・「喉痒」:喉の痒みは、風邪が咽喉を侵している状態を反映しています。
これらの症状を総合すると、風邪と寒邪がともに強い「風寒襲肺」と診断されます。
この病態の治療は、単一の治法では不十分であり、複数の側面からアプローチする必要があります。
・三拗湯ー宣肺解表
麻黄、杏仁、甘草で構成され、寒邪が強く、肺の気が閉塞して無汗である病態(風寒閉肺)に用います。
・止嗽散ー止咳化痰、疏表宣肺
桔梗、荊芥、紫苑、百部などで構成され、風邪が強く、痰を伴う咳嗽に用います。特に「喉痒」などの風邪の症状に効果的です。
紫苑 百部 白前 桔梗 陳皮 荊芥 甘草
1.麻黄湯
風寒襲肺の「喘証」が主症状の場合に用いる方剤です。本症例は喘息ではなく咳嗽が主症状であるため不適切です。
2.三拗湯
寒邪が強い風寒咳嗽に用いますが、喉痒や痰の要素を十分に治療するには不十分です。
3.止嗽散
風邪や痰が強い風寒咳嗽に用いますが、無汗などの寒邪の強い症状には効力が不十分です。
4.小青竜湯
外寒内飲の病態に用いる方剤で、水様性の痰や喘息が主症状となります。本症例には適しません。
5.三拗湯合止嗽散
三拗湯で寒邪を散らし、止嗽散で風邪と痰を治療できるため、この症例の複雑な病態に最も合致します。
問題 乾咳が続き咳き込む、痰が少なく粘稠、時々痰に血が混ざる、痰は吐き出し難い。悪寒発熱、鼻唇乾燥、咽乾かつ痛、舌辺尖紅、苔乾薄黄、脈浮数の症状が見られる。まず選ぶべき方剤はどれか?
1.銀翹散
2.桑菊飲
3.桑杏湯
4.清金化痰湯
5.瀉白散合黛蛤散
回答→3
【解説】
病名診断:咳嗽
証候診断:風燥傷肺(温燥)
・燥邪の証拠:「乾咳が続き、痰が少なく粘稠、鼻唇乾燥」は、乾燥した邪気である燥邪が肺を傷つけ、津液(体を潤す水分)が消耗されたことを示しています。
・熱の証拠:「悪寒発熱、咽乾かつ痛、舌辺尖紅、苔乾薄黄、脈浮数」は、熱邪が体表と肺に存在していることを示しています。特に「舌辺尖紅」は熱が盛んであることを、「苔乾」は乾燥していることを示唆します。
・血痰:「痰に血が混ざる」のは、燥邪と熱邪が津液を損傷し、肺の経絡を傷つけた結果です。
1.銀翹散
風熱感冒の代表的な方剤ですが、燥邪を潤す作用が弱いため、乾咳や痰に血が混じる症状には不十分です。
2.桑菊飲
風熱感冒の軽症に用いますが、潤燥作用が弱いため不適切です。
3.桑杏湯ー清宣温燥、潤肺止咳
沙参、杏仁、桑葉などで構成され、燥邪と熱邪を同時に治療する代表的な方剤です。桑葉で表の燥邪を発散させ、沙参や梨皮で津液を補い、杏仁や貝母で潤肺止咳作用を発揮します。本症例の「燥」と「熱」という病理に最も合致する方剤です。
4.清金化痰湯
痰熱が肺にこもった病態に用いる方剤です。潤燥作用は強くありません。
5.瀉白散合黛蛤散
肺熱や肝火による咳に用いる方剤で、燥邪を潤す作用はほとんどありません。
問題 平素から体質が虚弱で感冒にかかり易い。三日前から悪寒発熱、無汗、身楚倦怠、咳嗽、咯痰白色、舌淡苔白、脈浮無力の症状が出てきた。選ぶべき方剤はどれか?
1.荊防敗毒散
2.玉屏風散
3.参蘇飲
4.麻黄湯
5.どれでもない
回答→3
【解説】
病名診断:感冒
証候診断:気虚感冒
・気虚の証拠:「平素から体質が虚弱で感冒にかかり易い」「身楚倦怠」「脈浮無力」は、気の不足(気虚)が原因で、体の抵抗力(衛気)が弱まっている状態を示しています。
・風寒の証拠:「悪寒発熱、無汗」「咳嗽、咯痰白色」は、風寒の邪気が体表と肺に侵入したことを示しています。
1.荊防敗毒散
風寒感冒の治療方剤です。風寒の邪気が非常に強い「実証」に用いるため、本症例のような虚弱な体質には不適切です。
2.玉屏風散
感冒の予防、喘息の緩和期の肺虚、自汗を伴う肺衛不固の治療方剤です。すでに感冒を発症している本症例には適しません。
3.参蘇飲
気虚感冒の治療方剤です。本症例のように、虚弱体質で風寒の邪を受けている病態に最も合致します。
4.麻黄湯
風寒襲肺の「実喘」の治療方剤です。本症例は喘息ではなく、また虚証であるため不適切です。
※内科学では感冒への治療に桂枝湯と麻黄湯が採用されていない。
問題 患者、乾咳、咽喉乾痛、口鼻乾燥、痰が少なく粘っこい、頭痛身熱、舌苔薄黄、舌紅少津、脈浮数。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.桑杏湯
2.桑菊飲
3.止嗽散
4.ニ陳湯
5.沙参麦門冬湯
回答→1
【解説】
病名診断:咳嗽
証候診断:風燥傷肺
・燥邪の証拠:「乾咳」「痰が少なく粘っこい」「口鼻乾燥」「舌紅少津」は、乾燥した邪気である燥邪が肺の津液(体を潤す水分)を損傷したことを示しています。
・熱邪の証拠:「咽喉乾痛」「頭痛身熱」「舌苔薄黄」「脈浮数」は、風熱の邪気が体表と肺に存在していることを示しています。
1.桑杏湯
風燥傷肺の咳嗽、燥熱傷肺の咳血の治療方剤です。本症例のように、乾燥と熱が顕著な病態に最も適しています。
2.桑菊飲
風熱犯肺の咳嗽の治療方剤です。潤燥作用が弱いため、乾咳や口鼻乾燥が主症状である本症例には不適切です。
3.止嗽散
風寒襲肺の咳嗽の治療方剤です。本症例のような熱や乾燥の症状には適しません。
4.ニ陳湯
痰湿蘊肺の咳嗽の治療方剤です。本症例の「痰が少なく粘っこい」という症状は、痰湿ではなく燥熱によるものであり、不適切です。
5.沙参麦門冬湯
肺陰虧耗(肺の陰液不足)の咳嗽の治療方剤です。この病態は慢性的な乾咳が主であり、外邪による発熱や頭痛が主症状ではありません。本症例は外邪による急性的な病態であるため不適切です。
問題 下記の説明で、間違いはどれか?
1.外感咳嗽は邪実に属する
2.内傷咳嗽は正虚に属する
3.外感咳嗽と内傷咳嗽は相互に影響する
4.外感咳嗽は内傷咳嗽に転化する
5.肝火犯肺による咳嗽は内傷咳嗽に属する
回答→2
問題 患者、男、21歳。乾咳無痰、咽乾鼻燥、悪寒発熱、頭痛無汗、舌苔薄白少津。この治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.清燥救肺湯
2.桑菊飲
3.桑杏湯
4.杏蘇散
5.銀翹散
回答→4
【解説】
病名診断:咳嗽
証候診断:涼燥犯肺
・風寒の証拠:「悪寒発熱、頭痛無汗」は、風寒の邪気が体表を閉塞していることを示します。
・燥邪の証拠:「乾咳無痰、咽乾鼻燥、舌苔薄白少津」は、乾燥した邪気である燥邪が肺の津液を損傷していることを示します。
・総合判断:これらの症状から、熱の証拠が乏しい「涼」と、乾燥の「燥」が結びついた病態であると判断できます。
1.清燥救肺湯
肺陰虚で燥火内盛の病態に用いる方剤です。外邪による急性の病態である本症例には適しません。
2.桑菊飲
風熱犯肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例は悪寒無汗という寒の症状が主であり、熱の症状ではないため不適切です。
3.桑杏湯
温燥の風燥傷肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例は「悪寒無汗」という寒の症状が主であり、温燥ではないため不適切です。
4.杏蘇散
涼燥の風燥犯肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例の病態に最も合致します。
5.銀翹散
風熱感冒、肺癰の初期に用いる方剤です。本症例は寒の症状が主であり、熱の症状ではないため不適切です。
問題 寒涼を感受した後、鼻塞声重、くしゃみ連声、流清涕、咳嗽痰白清稀が見られ、悪寒微発熱、無汗、頭身痛、舌苔潤薄白、脈浮を伴う。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.荊防敗毒散
2.桂枝加附子湯
3.麻黄附子細辛湯
4.羌活勝湿湯
5.麻黄湯合玉屏風散
回答→1
【解説】
病名診断:感冒
証候診断:風寒感冒
・風寒の証拠:「寒涼を感受した後」「悪寒微発熱、無汗、頭身痛」は、風寒の邪が体表を閉塞している典型的な症状です。
・肺の症状:「鼻塞声重、くしゃみ連声、流清涕、咳嗽痰白清稀」は、寒邪が肺に侵入し、肺の宣発機能が失調した状態を示します。
・舌脈:「舌苔潤薄白、脈浮」は、病邪が体表にあり、まだ体内に深く侵入していないことを示唆しています。
1.荊防敗毒散ー発汗解表・消癰止痛
風寒感冒の治療方剤であり、羌活、独活、荊芥、防風など、発汗や風邪を散らす生薬が多く含まれています。本症例の、体表が閉塞して汗が出ない、風寒感冒の病態に最も適しています。
2.桂枝加附子湯
主に心陽虚の病態に用いる方剤です。本症例のような感冒には適しません。
3.麻黄附子細辛湯
腎虚に風寒表証を伴う病態に用いる方剤です。本症例は腎虚の症状が明らかではないため、まず選ぶべきではありません。
4.羌活勝湿湯
風湿頭痛に用いる方剤です。本症例の感冒には適しません。
5.麻黄湯合玉屏風散
内科学のテキストにはこのような使用例がないため、不適切です。
問題 患者、女45歳。発熱悪寒、肢体痠痛、頭痛無汗、渇喜熱飲、鼻塞、流清涕、苔薄白、脈浮緊。その治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.桂枝湯
2.川芎茶調散
3.参蘇飲
4.荊防敗毒散
5.桑菊飲
回答→4
【解説】
病名診断:感冒
証候診断:風寒感冒
・風寒の証拠:「発熱悪寒、無汗、肢体痠痛、頭痛」は、風寒の邪が体表を閉塞している典型的な症状です。特に、悪寒が強く、汗がない(無汗)ことが重要なポイントです。
・舌脈:「苔薄白、脈浮緊」は、病邪が体表にあり、寒邪が経絡を緊縮させていることを示しています。
1.桂枝湯
営衛不和による自汗の風邪に用いる方剤です。本症例は無汗であるため不適切です。
2.川芎茶調散
主に風寒頭痛に用いる方剤です。本症例のような全身の風寒感冒には対応しきれません。
3.参蘇飲
気虚感冒に用いる方剤です。本症例には気虚の明確な症状がないため、まず選ぶべきではありません。
4.荊防敗毒散ー発散解表・疎風散寒
風寒感冒の治療方剤です。荊芥、防風、羌活、独活など、風寒の邪気を発散させる生薬を多く含んでおり、体表が閉塞して無汗である状態に最も適しています。また、袪痰宣肺の効能も兼ね備えているため、鼻塞や流清涕といった症状にも効果的です。
5.桑菊飲
風熱犯肺の咳に用いる方剤です。本症例は寒邪による風邪であり、熱の症状ではないため不適切です。
※内科学では感冒への治療に桂枝湯と麻黄湯が採用されていない。
問題 養血解表の効能を有する方剤はどれか?
1.荊防敗毒散
2.銀翹散
3.羌活勝湿湯
4.新加香薷飲
5.葱白七味飲
回答→5
【解説】
1.荊防敗毒散
発汗解表、散風袪湿の効能があります。風寒の邪が強い実証に用いるため、養血作用はありません。
2.銀翹散
辛涼透表、清熱解毒の効能があります。風熱の邪を取り除く方剤であり、養血作用はありません。
3.羌活勝湿湯
袪風勝湿の効能があります。風と湿邪による病態に用いる方剤であり、養血作用はありません。
4.新加香薷飲
清暑袪湿解表の効能があります。夏期の暑湿感冒に用いる方剤であり、養血作用はありません。
5.葱白七味飲
滋陰養血解表の効能があります。麦門冬、生地黄といった血や陰液を補う生薬と、葱白、淡豆鼓といった発散作用のある生薬を配合しており、陰血虚損の風寒表証に用いる、養血解表の代表的な方剤です。
問題 乾咳、咳声短促、痰が少なく、時々痰に血が混ざる、痰は吐き出し難い、午後潮熱、手足心熱、形瘦乏力、舌紅少苔、脈細数。その診断はどれか?
1.肺痿、虚熱証
2.咳嗽、肝火犯肺証
3.咳嗽、肺陰虚証
4.咳嗽、風燥傷肺証
5.肺癆、気陰両虚証
回答→3
【解説】
病名診断:咳嗽
証候診断:肺陰虚証(内傷咳嗽)
・陰虚の証拠:「午後潮熱、手足心熱、形瘦乏力、舌紅少苔、脈細数」は、陰液が不足して熱がこもった典型的な陰虚内熱の症状です。
・肺の症状:「乾咳、咳声短促、痰が少なく、時々痰に血が混ざる、痰は吐き出し難い」は、肺の陰液が不足して潤いがなくなり、肺の機能が失調したことを示しています。
鑑別診断
咳嗽で津液不足の症状が見られる場合、肺陰虧虚と風燥傷肺を鑑別することが重要です。
・肺陰虧虚: 内傷咳嗽に属し、慢性的な虚証です。陰虚の症状(潮熱、手足心熱など)を伴うのが特徴です。
・風燥傷肺: 外感咳嗽に属し、急性の実証です。発熱悪寒や頭痛といった外感の症状が主で、陰虚の症状は伴いません。
また、肺痿も同様に乾咳と陰虚の症状が見られますが、「濁唾や涎沫を多く吐く」のが特徴であり、本症例の痰が少ない症状とは異なります。
治療方剤:沙参麦門冬湯
1.肺痿、虚熱証
陰虚症状は共通しますが、「濁唾や涎沫を多く吐く」という特徴がないため、不適切です。
2.咳嗽、肝火犯肺証
胸脇の張りや情志の変動が特徴であり、本症例の症状とは異なります。
3.咳嗽、肺陰虚証
乾咳や少痰に加え、午後の潮熱や手足心熱といった陰虚内熱の症状が見られるのが特徴です。本症例のすべての症状に合致します。
4.咳嗽、風燥傷肺証
外邪による急性の病態で、陰虚の症状を伴いません。
5.肺癆、気陰両虚証
陰虚症状に加えて、気虚の症状(無力感、息切れなど)が顕著に現れるのが特徴です。本症例は陰虚が主体の病態とは異なります。
問題 乾咳が続き咳き込む或いは少量粘痰で吐き出し難い、咽乾或いは痛、鼻唇乾燥、咳甚則胸痛、痰中帯血絲、舌辺尖紅、苔薄黄而乾、脈浮数。その診断はどれか?
1.肺痿、虚熱証
2.肺癆、肺陰虧損証
3.咳嗽、風熱犯肺証
4.咳嗽、風燥傷肺証
5.咳嗽、肝火犯肺証
回答→4
【解説】
病名診断:咳嗽
証候診断:風燥傷肺証
患者の症状は、風邪と燥邪が肺を侵し、熱を伴う**温燥(おんそう)**の病態であると診断できます。
・燥邪の証拠:「乾咳が続き咳き込む」「少量粘痰で吐き出し難い」「咽乾或いは痛、鼻唇乾燥」は、乾燥した邪気である燥邪が肺の津液を損傷したことを示しています。
・熱邪の証拠:「舌辺尖紅、苔薄黄而乾、脈浮数」は、熱邪が体表と肺に存在していることを示しています。
・肺の損傷:「咳甚則胸痛、痰中帯血絲」は、燥熱が肺を深く損傷し、絡脈を傷つけた結果です。
1.肺痿、虚熱証
陰虚症状に加え、粘稠な痰を多く吐くのが特徴です。本症例の、痰が少なく吐き出しにくい症状とは異なります。
2.肺癆、肺陰虧損証
咳嗽、咳血に加え、潮熱、盗汗、消痩といった慢性的な陰虚の症状が顕著に現れます。本症例のような外感による急性的な病態とは異なります。
3.咳嗽、風熱犯肺証
悪寒や身熱、咽痛が特徴ですが、燥邪による乾燥の症状は主ではありません。
4.咳嗽、風燥傷肺証
乾咳、少量粘痰、咽乾、鼻唇乾燥といった燥邪の症状に加え、舌脈に熱の兆候が見られるのが特徴です。本症例のすべての症状に合致します。
5.咳嗽、肝火犯肺証
胸脇の脹痛や情志の変化が特徴です。本症例の症状とは異なります。
※風燥傷肺の咳嗽は、乾燥症状から安易に補陰剤で治療すると、病邪が内に閉じ込められて悪化する危険があります。まず、桑杏湯のように燥邪を発散させ、肺を潤す方剤を用いることが非常に重要です。
問題 気喘と咳嗽が8年間。痰涎壅盛、咯吐不爽、胸中満悶、嘔悪、納呆、舌苔白厚膩、脈滑の症状が見られる。その治法はどれか?
1.祛痰降逆、宣肺平喘
2.疏風散寒、宣肺平喘
3.祛風清熱、宣肺平喘
4.温肺散寒、豁痰平喘
5.温肺散寒、化痰降気
回答→1
【解説】
病名診断:喘証
証候診断:痰濁阻肺証
患者の症状は、体内の痰湿が過剰になり、それが肺の機能を阻害している痰濁阻肺の病態を示しています。
・痰濁の証拠:「痰涎壅盛、咯吐不爽、胸中満悶、舌苔白厚膩、脈滑」は、体内の湿気が集まり、痰濁が形成されて肺の気の流れを塞いでいることを示しています。
・胃気の逆上:「嘔悪、納呆」は、痰湿が中焦にも停滞し、胃の気が逆流していることを反映しています。
治法:祛痰降逆、宣肺平喘
代表方剤:二陳湯合三子養親湯
2.疏風散寒、宣肺平喘
風寒襲肺の喘証(風邪が主因)の治療方法です。本症例の痰湿が主体の病態には適しません。
3.祛風清熱、宣肺平喘
表寒裏熱の喘証(外邪と体内の熱が併存)の治療方法です。本症例の痰湿が主体の病態には適しません。
4.温肺散寒、豁痰平喘
寒哮の治療方法です。寒邪による喘息に用いるため、本症例の痰湿が主体の病態には適しません。
5.温肺散寒、化痰降気
内科学には存在しない治法です。
問題 気粗息涌、胸高脇脹、哮鳴声は鋸を拽く音のよう、黄色痰、粘稠で吐き出し難い、煩悶不安、口乾苦、冷飲を好む、大便秘結、舌紅苔黄膩、脈滑数。選ぶべき方剤はどれか?
1.麻杏甘石湯
2.清金化痰湯
3.定喘湯
4.射干麻黄湯
5.蘇子降気湯
回答→3
【解説】
病名診断:哮証
証候診断:熱哮
患者の症状は、肺に熱と痰がこもった熱哮の病態を示しています。これは哮証の発作期に見られる実証です。
・熱邪の証拠:「気粗息涌」「黄色痰、粘稠で吐き出し難い」「煩悶不安、口乾苦、冷飲を好む」「大便秘結」「舌紅苔黄膩、脈滑数」は、体内の熱邪が盛んであることを示しています。特に、脈が滑らか(滑)で速い(数)のは、熱と痰が結びついている典型的な兆候です。
・肺の閉塞:「胸高脇脹」「哮鳴声は鋸を拽く音のよう」は、肺の気が熱と痰によって閉塞され、正常に機能していないことを示しています。
1.麻杏甘石湯
表寒裏熱の喘証に用いる方剤です。本症例は表証(外邪)の症状が明確ではないため、不適切です。
2.清金化痰湯
痰熱鬱肺の咳嗽に用いる方剤です。哮証の治療には、より強力な平喘作用を持つ方剤が適しています。
3.定喘湯ー宣降肺気、清熱化痰
麻黄、杏仁などで肺の気の逆流を鎮め、喘息を和らげ、黄芩、桑白皮などで肺の熱を冷まし、化痰作用を発揮します。麻黄の宣肺作用と白果の斂肺作用を組み合わせることで、肺気の正常な働きを回復させます。ご提示の通り、方剤名に「定喘」とありますが、特に熱哮の治療に用いられる代表的な方剤です。
4.射干麻黄湯
寒哮の治療方剤です。本症例のような熱証には不適切です。
5.蘇子降気湯
腎陽虚が原因の哮証に用いる方剤です。本症例は実証であり、虚証ではないため不適切です。
問題 発熱悪寒、咳嗽2日。今日になり振寒壮熱、煩躁汗出、咳嗽気急、胸痛で転側不利、腥味のある濁痰を吐く、舌苔黄膩、脈滑数。治療するためにまず選ぶべき方剤はどれか?
1.加味桔梗湯
2.清金化痰湯
3.枯梗杏仁煎
4.瀉白散合黛蛤散
5.《千金》葦茎湯合如金解毒散
回答→5
【解説】
病名診断:肺癰
「発熱悪寒、咳嗽」という外感病から始まり、その後「胸痛」「腥味のある濁痰」といった特徴的な症状が出現していることから、病名診断は肺癰です。
証候診断:肺癰成癰期
患者の症状は、邪熱が体表から肺の内部に深く入り込み、膿瘍が形成されている肺癰成癰期の病態を示しています。
・病態の進行: 「発熱悪寒」の後に「振寒壮熱」が出現するのは、邪気が体表から裏(内部)に侵入したことを示しています。
・熱毒の証拠: 「煩躁汗出、舌苔黄膩、脈滑数」は、熱毒が盛んであることを示しています。
・膿瘍の形成: 「胸痛で転側不利、腥味のある濁痰を吐く」は、熱毒が鬱積し、気血を蒸して腐敗させ、膿瘍を形成したことを示しています。
1.加味桔梗湯
肺癰の潰膿期に用いる方剤です。本症例の成癰期とは病態が異なります。
2.清金化痰湯
痰熱鬱肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例のような膿瘍を伴う重篤な病態には効力が不十分です。
3.枯梗杏仁煎
肺癰の回復期に用いる方剤です。本症例の成癰期とは病態が異なります。
4.瀉白散合黛蛤散
肝火犯肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例の病態とは異なります。
5.《千金》葦茎湯合如金解毒散
・効能:《千金》葦茎湯は清肺化痰、逐瘀排膿の効能があり、如金解毒散は清熱解毒、開宣肺気の効能があります。
・この2つの方剤を合わせることで、熱毒を強力に冷まし、解毒するとともに、肺に形成された膿瘍を排泄する作用が期待できます。この組み合わせは、ご提示の通り、肺癰の成癰期に最も適した治療法です。
肺癰(はいよう)について
肺癰とは、肺に熱毒が鬱積し、気血が停滞することで、膿瘍が形成される病態を指します。西洋医学における「肺膿瘍」や「壊疽性肺炎」に相当します。
病因・病理
主な病因は、外邪(風熱、風寒など)が体表から肺に侵入し、それが体内で熱毒に変化することです。特に、肺の抵抗力が低下している場合に発症しやすくなります。
1.初期(熱毒鬱肺)
・病理: 外邪が肺に侵入し、熱毒が鬱積します。
・症状: 発熱、悪寒、咳、痰など、風熱感冒に似た症状が見られます。
2.成癰期
・病理: 熱毒がさらに盛んになり、気血を蒸し、肺の組織を腐敗させて膿瘍が形成されます。
・症状: 高熱(壮熱)、悪寒(振寒)、胸痛(特に咳で悪化)、呼吸困難、そして舌苔黄膩、脈滑数といった熱毒が盛んな兆候が現れます。
3.潰膿期
・病理: 形成された膿瘍が気管支を破り、排膿が始まります。
・症状: 大量の膿痰が吐き出されます。膿痰は黄色く、しばしば腥臭(なまぐさい匂い)を伴い、時に血が混じります。膿の排泄後は熱が下がることが多いです。
4.回復期
・病理: 膿の排泄が終わり、病状が回復に向かいます。
・症状: 咳や痰の量が減り、発熱が治まります。ただし、疲労感、寝汗、軽度の咳などが残ることがあります。
治療原則
・初期: 疏風清熱、宣肺化痰。外邪を散らし、肺の熱を冷まして痰を解消します。代表方剤は銀翹散など。
・成癰期: 清熱解毒、化瘀排膿。肺の熱毒を強力に冷まし、解毒し、形成された膿瘍を排泄させます。代表方剤は《千金》葦茎湯など。
・潰膿期: 排膿化痰、清肺解毒。膿をスムーズに排泄させ、肺の熱を清します。代表方剤は加味桔梗湯など。
・回復期: 養陰清肺、補気活血。肺の機能を回復させ、残った邪気を取り除きます。代表方剤は枯梗杏仁煎など。
※注意点
・肺癰は、進行すると生命に関わる重篤な病態です。
・中医学的な治療とともに、現代医学的な検査や治療(抗生物質の使用など)が必要となる場合があります。
・治療においては、病期を正確に判断することが非常に重要です。
・特に潰膿期の膿痰は、黄色で腥臭を伴うという特徴的な症状があります。
問題 患者、男、45歳。咳嗽気急し、大量膿血痰を喀吐、味は腥臭。壮熱煩躁、胸悶疼痛、苔黄膩、脈滑数。この診断は肺癰のどの期にあたるか?
1.初期
2.成癰期
3.潰膿期
4.回復期
5.慢性期
回答→3
問題 患者陳様、43歳。喘逆上気し、胸が脹って時に痛む、息粗、鼻煽、咳して不爽、痰吐粘稠。形寒、身熱、煩悶、身痛、無汗、口渇などを伴う、苔薄白、舌質紅、脈浮数。この治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.麻黄湯
2.桂枝加厚朴杏子湯
3.桑菊飲
4.麻杏石甘湯
5.大青竜湯
回答→4
【解説】
病名診断:喘証
「喘逆上気し」という症状から、病名診断は喘証(喘息)であると判断できます。
証候診断:表寒裏熱
この患者の症状は、体表に風寒の邪気が停滞し、体内に熱がこもる表寒裏熱という複合的な病態を示しています。
・表寒の証拠:「形寒、身熱、無汗」は、風寒の邪が体表を閉塞していることを示しています。
・裏熱の証拠:「煩悶、口渇、舌質紅、脈浮数」は、体内に熱がこもっていることを示しています。
・肺の病態:「喘逆上気、胸が脹って時に痛む、息粗、鼻煽」は、肺の宣発粛降機能が失調し、喘息を発症していることを示します。「痰吐粘稠」は、熱邪が津液を煮詰めて痰を生成していることを示唆しています。
1.麻黄湯
風寒襲肺の喘証に用いる方剤です。寒邪が強く、裏に熱がこもっていない実証に用いるため、本症例の裏熱には不適切です。
2.桂枝加厚朴杏子湯
営衛不和の咳喘に用いる方剤です。本症例のような表寒裏熱の病態には適しません。
3.桑菊飲
風熱犯肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例の裏熱には適しますが、表の寒邪を散らす作用が弱いため不適切です。
4.麻杏石甘湯ー辛涼宣泄・清肺平喘
麻黄で体表の寒邪を発散させ、石膏で体内の熱を強力に冷まします。杏仁で肺の気の逆流を鎮め、甘草で諸薬の調和を図ります。表寒裏熱の喘証に用いる代表的な方剤です。
5.大青竜湯
外寒裏熱の煩躁の病証に用いる方剤です。麻杏石甘湯と似ていますが、大青竜湯はより寒熱ともに重い病態に用います。麻黄と石膏の配合比率も異なり、麻黄の量が多いため、本症例には麻杏石甘湯がより適切です。
補足
・息粗
息粗とは、呼吸が荒く、音が大きい状態を指します。
・鼻煽
鼻煽とは、呼吸に伴って小鼻(鼻翼)がヒクヒクと動く状態を指します。
この2つの症状は、どちらも呼吸器の機能が著しく低下していることを示す重要な兆候です。
問題 患者張様、男、29歳。咳嗽発熱、胸痛、吐痰腥臭、喀吐膿血、舌苔黄膩、脈滑数。この診断はどれか?
1.風熱咳嗽
2.痰熱咳嗽
3.肝火犯肺咳嗽
4.虚熱肺痿
5.肺癰
回答→5
問題 患者、身熱が徐々に下がり、咳と膿血痰が日々良くなる、痰は稀、面色少華、気短自汗、形瘦神疲、潮熱盗汗、口燥咽乾、舌淡紅苔薄、脈細数無力。治療にまず選ぶべき方剤はどれか?
1.桑杏湯
2.清燥救肺湯
3.清金化痰湯
4.沙参清肺湯
5.《千金》葦茎湯
回答→4
【解説】
病名診断:肺癰
「身熱が徐々に下がり、咳と膿血痰が日々良くなる」という症状から、肺癰の病態が回復に向かっていることがわかります。したがって、病名診断は肺癰です。
証候診断:肺癰回復期
患者の症状は、膿の排泄が終わり、病状が回復に向かう肺癰回復期の病態を示しています。
・病勢の好転:「身熱が徐々に下がり、咳と膿血痰が日々良くなる」は、病邪が退き、病態が好転していることを示しています。
・気陰両虚の証拠:「面色少華、気短自汗、形瘦神疲、潮熱盗汗、口燥咽乾、舌淡紅苔薄、脈細数無力」は、病気の消耗により、気と陰液がともに不足していることを示しています。これは、病が回復に向かう過程で、正気が虚弱になった状態です。
1.桑杏湯
風燥傷肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例のような気陰両虚の病態には不適切です。
2.清燥救肺湯
肺熱津傷による痿証に用いる方剤です。本症例の肺癰の回復期には適しません。
3.清金化痰湯
痰熱鬱肺の咳嗽に用いる方剤です。本症例は熱や痰がすでに収まりつつあり、虚証に転じているため不適切です。
4.沙参清肺湯ー益気養陰、清熱化痰。
沙参、太子参、黄耆などで気を補い、白芨、薏苡仁、冬瓜仁などで残った熱を清しながら排膿し、新しい肉芽組織の生成(生肌)を促します。ご提示の通り、肺癰の回復期に用いる代表的な方剤です。
5.《千金》葦茎湯
肺癰の成癰期の治療方剤です。本症例のような回復期には不適切です。
問題 哮喘の頻発、発作の時に喉中に痰鳴があり鼾のよう、声低息促、動くと症状が重くなる、痰多白色、胸悶汗出、腰痠肢冷、舌淡苔白膩、脈沈細。選ぶべき方剤はどれか?
1.小青竜湯
2.蘇子降気湯
3.金匱腎気丸
4.射干麻黄湯
5.紫金丹
回答→2
【解説】
病名診断:哮証
「哮喘の頻発、発作の時に喉中に痰鳴があり」という症状から、病名診断は哮証です。特に、この症状は発作期ではなく、緩和期の病態を示しています。
証候診断:上実下虚の腎陽虚
患者の症状は、喘息が慢性化し、上焦(肺)に痰濁が停滞し、下焦(腎)の陽気が不足している上実下虚の病態であると診断されます。これは、腎陽虚が根本にある虚証と、痰濁が停滞している実証が同時に存在する、複雑な病態です。
・腎陽虚(下虚)の証拠:「腰痠肢冷、脈沈細」は、腎の陽気が不足し、体を温める力が弱まっていることを示しています。
・痰濁阻滞(上実)の証拠:「喉中に痰鳴があり鼾のよう、声低息促、痰多白色、胸悶」は、痰湿が上焦に停滞し、肺の働きを阻害していることを示しています。
・総合的な特徴:「動くと症状が重くなる、汗出」は、気の不足(気虚)も同時に存在し、正気が弱っていることを示しています。
1.小青竜湯
外寒内飲の哮証・喘証に用いる方剤です。腎陽を温める作用はありますが、本症例のような上実下虚の病態には適さず、逆に腎陽虚を悪化させる可能性があります。
麻黄 桂枝 乾姜 細辛 芍薬 半夏 五味子 炙甘草
2.蘇子降気湯ー降気平喘、袪痰止咳
蘇子、半夏などで上焦の痰を取り除き、気の逆流を鎮めます。さらに、肉桂で腎を温め、腎気の納気作用を助けることで、下焦の陽気を補います。上実下虚の腎陽虚哮証に用いる代表的な方剤です。
蘇子 半夏 当帰 前胡 厚朴 肉桂 甘草
3.金匱腎気丸
腎陽虚の哮証に用いる方剤ですが、これは上実(痰濁)の症状がほとんどない場合に用います。本症例のように、痰濁が顕著な場合には不適切です。
乾地黄 山薬 山茱萸 沢瀉 茯苓 牡丹皮 炮附子 桂枝
4.射干麻黄湯
発作期の寒哮に用いる方剤です。本症例の緩和期には適しません。
射干 麻黄 生姜 細辛 半夏 紫苑 款冬花 五味子 大棗
5.紫金丹
哮喘が非常に激しい発作期に用いる頓服薬です。本症例の緩和期の治療には適しません。
問題 気粗息涌、胸高脇脹、哮鳴声は鋸を拽く音のよう、黄色痰、粘稠で吐き出し難い、煩悶不安、口乾苦、冷飲を好む、大便秘結、舌紅苔黄膩、脈滑数。選ぶべき方剤はどれか?
1.麻杏甘石湯
2.清金化痰湯
3.定喘湯
4.射干麻黄湯
5.蘇子降気湯
回答→3
【解説】
病名診断:哮証(発作期)
「哮鳴声は鋸を拽く音のよう」とあることから、喘鳴を伴う哮証と診断できます。
証候診断:熱哮
患者の症状は、肺に熱と痰がこもった熱哮の病態を示しています。これは哮証の発作期に見られる実証です。
・熱邪の証拠:「気粗息涌(きそそくゆう)」「黄色痰、粘稠で吐き出し難い」「煩悶不安、口乾苦、冷飲を好む」「大便秘結」「舌紅苔黄膩、脈滑数」は、体内の熱邪が盛んであることを示しています。
・肺の閉塞:「胸高脇脹」「哮鳴声は鋸を拽く音のよう」は、肺の気が熱と痰によって閉塞され、正常に機能していないことを示しています。
1.麻杏甘石湯
表寒裏熱の喘証の治療方剤です。本症例は、表証(外邪)の症状が明確ではないため不適切です。
2.清金化痰湯
痰熱鬱肺の咳嗽の治療方剤です。哮証には、より強力な平喘作用を持つ方剤が適しています。
3.定喘湯ー宣降肺気・清熱化痰
麻黄の宣肺作用と白果の斂肺作用を組み合わせることで、肺気の正常な働きを回復させます。また、黄芩、桑白皮などで熱を清し、半夏などで痰を化します。方剤名に「定喘」とありますが、特に熱哮の治療に用いられる代表的な方剤です。
4.射干麻黄湯
寒哮の治療方剤です。本症例のような熱証には不適切です。
5.蘇子降気湯
腎陽虚が原因の哮証に用いる方剤です。本症例は虚証ではなく実証であるため、不適切です。
問題 気喘と咳嗽が8年間。痰涎壅盛、咯吐不爽、胸中満悶、嘔悪、納呆、舌苔白厚膩、脈滑の症状が見られる。その治法はどれか?
1.祛痰降逆、宣肺平喘
2.疏風散寒、宣肺平喘
3.祛風清熱、宣肺平喘
4.温肺散寒、豁痰平喘
5.温肺散寒、化痰降気
回答→1
【解説】
病名診断:喘証
「気喘と咳嗽が8年間」とあるため、喘鳴を伴う喘証と診断します。
証候診断:痰濁阻肺証
患者の症状は、体内の痰湿が過剰になり、それが肺の働きを阻害している痰濁阻肺の病態を示しています。
・痰濁の証拠:「痰涎壅盛、咯吐不爽、胸中満悶、舌苔白厚膩、脈滑」は、痰湿が肺に停滞し、気の流れを塞いでいる状態です。
・胃気の逆上:「嘔悪、納呆」は、痰湿が胃にも停滞し、胃の気が逆流していることを反映しています。
これらの症状から、痰濁阻肺の実証であると診断できます。
代表方剤:二陳湯合三子養親湯
問題 喘促日久、動くと喘が甚だしく、呼多吸少、気不得続、形瘦神憊、跗腫、汗出肢冷、面青唇紫、舌苔黒潤、脈微細或いは沈弱。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.七味都気丸
2.金匱腎気丸
3.蘇子降気湯
4.六味地黄湯
5.小青竜湯
回答→2
【解説】
病名診断:喘証
「喘促日久」とあることから、喘鳴を伴わない喘証(呼吸困難)と診断できます。
証候診断:虚喘・腎陽虚衰
患者の症状は、喘息が慢性化し、根本的な腎の陽気が著しく不足している虚喘、特に腎陽虚衰の病態を示しています。
・腎の納気機能失調: 「呼多吸少、気不得続」は、腎が気を体内に納める機能(納気)を失った典型的な症状です。
・陽虚の証拠: 「汗出肢冷、面青唇紫、舌苔黒潤、脈微細或いは沈弱」は、腎の陽気が不足し、体を温めたり、気血を巡らせる力が極度に弱まっていることを示しています。特に脈が「微細」や「沈弱」であることは、陽気の衰退が深刻であることを反映しています。
・病態の消耗: 「形瘦神憊、跗腫」は、病が長引き、正気が消耗している状態です。
形瘦神憊ー病気が長引いた結果、精気(生命活動の根本となる物質)が消耗し、体が痩せて精神的にも衰弱している状態を表します。
跗腫ー足の甲がむくむことを指します。これは、腎陽虚や脾腎陽虚といった病態にしばしば見られる症状で、病状が重篤であることを示唆します。
1.七味都気丸
腎陰虚による喘証に用いる方剤です。本症例は陽虚の症状が顕著であるため不適切です。
2.金匱腎気丸
腎陽虚衰の喘証に用いる代表的な方剤です。腎陰を補う六味丸に、腎陽を温める附子と肉桂を加えることで、温補腎陽の作用を強化しています。
3.蘇子降気湯
「上実下虚」の喘証に用いる方剤です。本症例のように、上焦の実証(痰濁など)がほとんどない場合は、まず金匱腎気丸を選択します。
4.六味地黄湯
腎陰を補う方剤であり、腎陽虚の症状が主である本症例には不適切です。
5.小青竜湯
外寒内飲の喘証に用いる方剤です。本症例のような虚証の慢性的な病態には適しません。
問題 患者、壮熱、汗出、咳で大量の膿血痰を吐き、痰は異常な腥臭がある、胸中煩悶かつ痛み、気喘で横になれない、舌質紅或いは紅絳、苔黄膩、脈数実。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.如金解毒散
2.《千金》葦茎湯
3.桔梗杏仁煎合犀黄丸
4.加味桔梗湯
5.桔梗白散
回答→4
【解説】
病名診断:肺癰
「咳で大量の膿血痰を吐き、痰は異常な腥臭がある」という特徴的な症状から、病名診断は肺癰です。
証候診断:肺癰潰膿期
この患者の症状は、肺に形成された膿瘍が破裂し、大量の膿が排泄され始めた肺癰潰膿期の病態を示しています。
・膿瘍破裂の証拠: 「咳で大量の膿血痰を吐き、痰は異常な腥臭がある」は、肺内の膿瘍が気管支に穿破し、腐敗した膿や血液が排出されていることを示します。
・熱毒の証拠: 「壮熱、汗出、胸中煩悶、舌質紅或いは紅絳、苔黄膩、脈数実」は、熱毒が盛んであることを示しています。
・肺気閉塞の証拠: 「気喘で横になれない」は、痰や膿によって肺の気が閉塞していることを示します。
1.如金解毒散
肺癰の成癰期に用いる方剤で、潰膿期には排膿作用が不十分です。
2.《千金》葦茎湯
肺癰の成癰期に用いる方剤です。
3.桔梗杏仁煎合犀黄丸
内科学にはこの併用方法がありません。
4.加味桔梗湯
桔梗で排膿作用を強め、金銀花、薏苡仁などで清熱化痰、排膿を促します。この方剤は特に宣肺の力で膿血を排出させるため、肺癰の潰膿期に最も適しています。
5.桔梗白散
潰膿期で便秘を伴う場合に用いる方剤です。本症例は便秘の症状がないため、まず加味桔梗湯を選択します。
ポイント
・肺癰の病期鑑別:
肺癰の診断では、初期、成癰期、潰膿期、回復期の4つの病期を正確に鑑別することが重要です。成癰期の「胸満作痛」「黄緑色の濁痰」から、「大量の膿血痰を吐く」症状が現れたら潰膿期に移行したと判断します。
問題 患者趙様、女、30歳。喘咳痰多で胸悶し、動くと気喘が甚だしい、腰痠肢冷、汗出心悸、小便頻数、舌苔膩、脈沈細。この治療に選ぶべき方剤はどれか?
1.生脈散
2.金匱腎気丸
3.蘇子降気湯
4.真武湯
5.七味都気丸
回答→3
【解説】
病名診断:喘証
「喘咳痰多で胸悶し」という症状から、病名診断は喘証と判断できます。
証候診断:虚喘・腎陽虚衰の上実下虚
患者の症状は、根本的な腎陽の不足(下虚)と、上焦(胸部)に痰濁が停滞している(上実)という、上実下虚の病態を示しています。
・腎陽虚(下虚)の証拠:「腰痠肢冷、汗出心悸、小便頻数、脈沈細」は、腎の陽気が不足し、体を温めたり、水液を司る機能が弱まっていることを示しています。
・痰濁阻滞(上実)の証拠:「喘咳痰多で胸悶し、舌苔膩」は、痰湿が肺に停滞し、気の流れを塞いでいることを示しています。
1.生脈散
肺虚による虚喘に用いる方剤です。本症例の腎陽虚と痰濁の症状には適しません。
2.金匱腎気丸
腎陽虚衰の喘証に用いますが、上焦の痰濁阻滞が顕著でない場合に用います。本症例のように、痰濁が明らかに存在する場合は不適切です。
3.蘇子降気湯
蘇子、半夏などで上焦の痰を取り除き、気の逆流を鎮めます。さらに、肉桂で腎を温め、腎気の納気作用を助けることで、下焦の陽気を補います。上実下虚の喘証に用いる代表的な方剤です。
4.真武湯
腎陽虚に水飲が停滞した病態に用いる方剤です。本症例の痰濁が主体の病態とは異なります。
5.七味都気丸
腎陰虚による喘証に用いる方剤です。本症例は陽虚の症状が主であるため不適切です。
ポイント
・上実下虚の判断: 「腰痠肢冷」や「脈沈細」といった腎陽虚(下虚)の症状と、「痰多で胸悶」「舌苔膩」といった痰濁阻滞(上実)の症状が同時に見られる場合、上実下虚と判断します。
・蘇子降気湯と金匱腎気丸の使い分けは、蘇子降気湯は、上実(痰濁)の症状が顕著な場合に、祛痰降気と温腎納気の作用を兼ね備えた方剤として選択します。金匱腎気丸は、腎陽虚が主で、上実の症状が少ない場合に、温補腎陽を目的として用います。