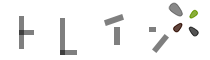問題 湿熱壅滞証の腹痛の治療でまず選ぶべきはどれか。
1.大承気湯
2.玉女煎
3.竜胆瀉肝湯
4.大黄黄連瀉心湯
5.瀉青丸
回答→1
【解説】
1.大承気湯
大黄、芒硝、枳実、厚朴の4つの生薬からなり、腸の熱結を強力に瀉下し、腹満や痛みを解消します。湿熱が腸に停滞した腹痛には、この方剤が最も効果的で、まず選ぶべき方剤です。
2.玉女煎
胃の熱を清し、腎の陰液を補う方剤で、歯肉の腫れや痛みなどに用います。腹痛には用いません。
3.竜胆瀉肝湯
肝胆の熱や下腹部の湿熱を治療する方剤ですが、腸の閉塞を瀉下する作用は弱く、腹痛の主治には不適切です。
4.大黄黄連瀉心湯
心下の熱を清す方剤で、熱による胸苦しさや吐血などに用います。腹部の便秘や痛みには不向きです。
5.瀉青丸
肝の火を清す方剤で、肝火によるイライラや頭痛などに用います。腹痛の治療には不適切です。
問題 泄瀉と痢疾の最も主要な鑑別要点はどれか
1.大便に膿血が有るか無いか
2.大便の回数が多いか少ないか
3.腹痛に裏急後重を伴うか否か
4.排便後に腹痛が軽減するか否か
5.どれでもない
回答→1
【解説】
泄瀉
・現代医学の下痢に相当します。
・脾の運化作用が失調し、水穀が消化されずにそのまま排出される病態です。
・主な特徴は、大便が水様または泥状であること、排便後に腹痛が軽減することです。大便に膿や血は混じりません。
痢疾
・現代医学の細菌性赤痢やアメーバ赤痢などに相当します。
・湿熱や疫毒などの邪気が大腸に侵入し、大腸の血絡を損傷することで起こる病態です。
・主な特徴は、大便に膿や血が混じることです。また、排便時に腹痛がひどくなり、排便後も残便感(裏急後重)が続きます。
1.大便に膿血が有るか無いか
痢疾には膿血が混じり、泄瀉には混じりません。これは両者を鑑別する上で最も重要なポイントであり、根本的な病理の違い(痢疾は大腸の血絡の損傷、泄瀉は脾の運化失調)を反映しています。
2.大便の回数が多いか少ないか
泄瀉でも痢疾でも、大便の回数は増えることが多く、この点だけでは鑑別できません。
3.腹痛に裏急後重を伴うか否か
裏急後重(便意が強く、排便後も残便感がある)は痢疾の典型症状ですが、軽度の痢疾や重度の泄瀉でも類似の症状が現れることがあり、最も主要な鑑別点とは言えません。
4.排便後に腹痛が軽減するか否か
泄瀉では排便後に腹痛が軽減しますが、痢疾では残便感があるため軽減しません。これも鑑別点ではありますが、膿血の有無ほど決定的ではありません。
問題 痛瀉要方はどの証の泄瀉に有効か。
1.食滞胃腸
2.肝気乗脾
3.脾胃虚弱
4.腎陽虚衰
5.感受湿邪
回答→2
【解説】
痛瀉要方が主として治療するのは、肝気乗脾の病態です。その名の通り、「痛みを伴う下痢」に用いる重要な方剤です。
1.食滞胃腸ー保和丸など
3.脾胃虚弱ー参苓白朮散など
4.腎陽虚衰ー四神丸など
5.感受湿邪ー胃苓湯など
問題 泄瀉の初期の治療で適当でないのはどれか
1.分利
2.消導
3.疏利
4.清化
5.固渋
回答→5
【解説】
1.分利
湿邪が原因の泄瀉に対し、利水薬を用いて湿邪を尿とともに排出させる治法です。
2.消導
食滞が原因の泄瀉に対し、消化を助ける薬を用いて停滞した飲食物を排出させる治法です。
3.疏利
肝の気の滞りが原因の泄瀉に対し、気の流れを良くして腸の働きを正常に戻す治法です。
4.清化
熱邪が原因の泄瀉に対し、熱を清し、湿邪を解消する治法です。
5.固渋
下痢や出血など、体内の物質が漏れ出るのを固めて止める治法です。
泄瀉の初期は「邪気を排出する」ことが最優先であり、下痢を無理に止める「固渋」は、虚証に陥った慢性期の治療法です。したがって、泄瀉の初期治療としては不適当です。
問題 痢疾に対する治法でないのはどれか
1.熱痢なれば則ちこれを清す
2.寒痢なれば則ちこれを温す
3.初の痢で実なれば、これを通す
4.久痢で虚なれば、これを補す
5.湿盛痢なれば、則ち分利す
回答→5
【解説】
分利は、主に湿邪が膀胱や腎に停滞した水腫や泄瀉などの治療に用いられる治法であり、湿邪が大腸に停滞する痢疾の治療には適しません。
問題 急に発病する痢疾はどれか
1.湿熱痢
2.寒湿痢
3.疫毒痢
4.休息痢
5.虚寒痢
回答→3
問題 下記の項目で痢疾の治法でないのはどれか
1.湿盛痢なれば、則ち分利す
2.初の痢なれば、通すべき
3.久痢なれば渋すべき
4.便が赤ければ血薬を用いる
5.便が白ければ気薬を用いる
回答→1
問題 痢疾の必須症状でないものはどれか
1.裏急後重
2.下痢赤白膿血
3.夏秋の季節に多発する
4.下痢白凍
5.肛門灼熱
回答→5
【解説】
肛門灼熱は:
・肛門の灼熱感は、湿熱が盛んな熱痢の典型的な症状です。
・しかし、寒邪が原因の寒痢の場合、肛門の灼熱感は現れません。
・したがって、すべての痢疾に共通する必須症状ではありません。
※下痢白凍ー白い凍状の便は、膿便を指す言葉であり、下痢赤白膿血の一部です。痢疾の必須症状です。
問題 痢疾の初期に禁忌すべき薬はどれか
1.疏散表邪
2.清熱涼血
3.調気行血
4.理気化滞
5.収斂止瀉
回答→5
問題 便秘の病因病機でないのはどれか
1.素体陽盛 腸胃積熱
2.情志失和 気機鬱滞
3.気血不足 下元虧損
4.陽虚体弱 陰寒内生
5.選択肢に正解は無い
回答→5
問題 燥熱便秘に対する治法はどれか
1.順気導滞
2.益気潤腸
3.養血潤燥
4.清熱潤下
5.温陽通便
回答→4
問題 便秘1ヶ月、大便乾結、小便短赤、面紅身熱、口乾口臭、舌紅苔黄燥、脈滑数。選ぶべき方剤はどれか
1.大承気湯
2.六磨丸
3.麻子仁丸
4.更衣丸
5.(尊生)潤腸丸
回答→3
【解説】
この病態は、胃腸に熱がこもり、その熱が津液を消耗させることで、便が硬く乾燥し、排出されにくくなっている状態です。治療のポイントは、清熱潤燥、つまり熱を清し、腸を潤すことです。
1.大承気湯
胃腸の熱と便秘を強力に瀉下する方剤ですが、津液の潤い不足を補う作用はありません。今回の症例では、熱に加えて乾燥が顕著なため、潤燥の作用が不足しています。
大黄(後下) 芒硝(溶服) 枳実 厚朴
2.六磨丸
気の滞りによる便秘に用いる方剤であり、熱や津液不足には不適切です。
3.麻子仁丸
麻子仁、杏仁といった潤燥作用のある生薬と、大黄、枳実といった瀉下作用のある生薬が配合されています。胃腸の熱を清しながら、便を潤して排出を促すため、今回の症例に最も適しています。
麻子仁 大黄 杏仁 白芍 枳実 厚朴
4.更衣丸
便秘に用いる方剤ですが、麻子仁丸ほど津液を潤す作用は強くありません。
5.(尊生)潤腸丸
血虚や陰虚による乾燥性便秘に用いる方剤であり、熱証の病態には不適切です。
問題 気虚便秘に対する治法はどれか
1.行気通便
2.潤腸通便
3.益気通便
4.温陽通便
5.どれもちがう
回答→3
問題 血虚便秘の主症でないのはどれか
1.大便秘結
2.面色無華
3.頭昏目眩心悸
4.排便時にいきんでも力が入らない
5.舌淡脈細
回答→4
【解説】
血虚便秘でも、血を生成する「気」も不足していることが多いですが、この症状は気虚便秘の主症状であり、血虚便秘の主症状とは言えません。
問題 済川煎が治療する便秘はどれか
1.気滞便秘
2.熱結便秘
3.気虚便秘
4.血虚便秘
5.陽虚便秘
回答→5
【解説】
済川煎は腎陽虚弱による便秘を治療するための代表的な方剤として知られています。
当帰 肉蓯蓉 牛膝 沢瀉 升麻 枳穀
問題 脇痛の病機でないのはどれか
1.肝気鬱結
2.瘀血阻絡
3.湿熱蘊結
4.肝陰不足
5.飲食停滞
回答→5
問題 肝気鬱結の脇痛の特徴でないものはどれか
1.脇痛は脹痛を主とする
2.痛みは走竄不定
3.疼痛は情志の変化により増減
4.夜になると疼痛が甚だしくなる
5.頻繁な噯気
回答→4
問題 肝陰不足の脇痛はどれか
1.脇肋脹痛
2.脇肋刺痛
3.脇肋隠痛
4.脇肋灼痛
5.脇肋竄痛
回答→3
【解説】
1.脇肋脹痛ー肝気鬱滞
2.脇肋刺痛ー瘀血
4.脇肋灼痛ー肝火
5.脇肋竄痛ー気滞
問題 肝陰不足の脇痛の治法はどれか
1.疏肝理気
2.活血通絡
3.養血柔肝
4.滋補肝腎
5.養陰柔肝
回答→5
【解説】
代表方剤は一貫煎です。
生地黄 沙参 麦門冬 当帰 枸杞子 川楝子
問題 黄疸発生の主な内因はどれか
1.気滞
2.水飲
3.湿濁
4.瘀血
5.痰濁
回答→3
【解説】
黄疸においては、水分代謝の異常(湿)が肝胆の通路を塞ぐ(濁)という病機が最も重要であるため、湿濁が主因となります。痰濁は、湿濁がさらに進んだもので、意識障害や呼吸器系の病気など、より深い病態や固形物を伴う病態の主要因となります。
つまり痰濁は、湿濁がさらに時間や熱の作用によって煮詰められ、凝集し、粘り気を持ち、半固形化した病理産物です。
問題 陽黄と陰黄との鑑別要点でないのはどれか
1.病程は比較的に長いか短いか
2.黄色が鮮明か晦暗か
3.小便が黄色か否か
4.熱証か寒証か
5.虚証か実証か
回答→3
【解説】
小便が黄色くなることは黄疸の共通症状であり、陽黄と陰黄を区別する鑑別要点にはなりません。
・陽黄
病因:湿熱邪が盛んな実熱証が中心。
特徴:黄色の色が鮮やかで、発熱や煩躁といった熱証の症状を伴います。病程は比較的短く、急性に発症することが多いです。
・陰黄
病因:湿邪が主で、体内の陽気が不足した虚寒証が中心。
特徴:黄色の色がくすんでいて、寒気や倦怠感といった寒証の症状を伴います。病程は比較的長く、慢性的に進行することが多いです。
問題 黄疸の治療大法はどれか
1.芳香化湿
2.清熱化湿
3.温中化湿
4.化湿利尿
5.清熱解毒
回答→4
【解説】
黄疸の治療では、熱や寒、虚実に関わらず、まず湿邪を取り除くことが不可欠です。したがって、湿邪を解消し、尿から排出させる「化湿利尿」が、黄疸全体の最も主要な治療大法となります。
問題 陽黄が初発する際に、表証がみられる者の治療で選ぶべき方剤はどれか
1.茵蔯蒿湯
2.小柴胡湯
3.大柴胡湯
4.麻黄連翹赤小豆湯
5.茵蔯五苓散
回答→4
【解説】
「陽黄が初発する際に、表証がみられる者」の病態は、湿熱邪が体表に停滞し、同時に黄疸の症状を引き起こしている状態です。この場合の治療原則は、体表の邪気を取り除き(解表)、同時に体内の熱と湿邪を解消することです(清熱利湿)。
1.茵蔯蒿湯
陽黄の治療で最も代表的な方剤です。ただし、これは熱と湿が体内にこもった裏証の病態に用いるもので、表証の症状(悪寒、発熱など)には対応できません。
2.小柴胡湯
少陽病(半表半裏の病態)を治療する方剤であり、湿熱が主因である黄疸には不適切です。
3.大柴胡湯
小柴胡湯に加えて瀉下薬が配合されており、便秘を伴う少陽・陽明病の治療に用います。黄疸の治療には不適切です。
4.麻黄連翹赤小豆湯
麻黄で体表の邪気を取り除き(発汗)、連翹や赤小豆で湿熱を解消します。陽黄の初発で表証がある場合に、この方剤が最も適しています。
5.茵蔯五苓散
茵蔯蒿湯に五苓散を合わせたもので、陽黄で水分代謝の異常(小便不利など)が顕著な場合に用います。表証の治療には不向きです。
問題 寒湿型の黄疸の症状でないのはどれか
1.身目倶黄
2.腹張便溏
3.神疲畏寒
4.舌淡苔膩
5.脈弦滑
回答→5
【解説】
寒湿型黄疸は、「陰黄」に相当し、脾胃の陽気が不足し、それに湿邪が加わることで生じます。このため、全身に冷えや機能低下の症状が顕著に現れます。
1.身目倶黄
寒湿型でも黄疸である以上、体と目が黄色くなります。ただし、色はくすんだ黄色(晦暗)であるのが特徴です。
2.腹張便溏
脾の運化作用が湿邪と寒邪によって阻害されるため、消化機能が低下し、腹部の張りや軟便・下痢が現れます。
3.神疲畏寒
脾胃の陽気が不足するため、全身のエネルギーが足りず、精神的な疲労や寒さを嫌う症状が現れます。
4.舌淡苔膩
陽気不足で舌に血色がないため舌が淡く、湿邪がこもっているため舌苔が白く脂っぽくなります。
5.脈弦滑
・脈弦は、肝の気の滞りや痰飲の停滞を示す脈です。
・脈滑は、湿熱や痰飲、食滞などの実邪が盛んであることを示す脈です。
・寒湿型黄疸は、陽気不足による虚寒証が中心であり、通常、沈、弱、遅や緩となります。
問題 積と聚を鑑別する上で意味のないものはどれか
1.積は病程が長く、聚は病程が短い
2.積は固定不移で、聚は聚散無常である
3.積は血に、聚は気に属する
4.積は臓病に、聚は腑病に属する
5.積ん病位は大腹に、聚の病位は小腹にある
回答→5
【解説】
腹部にしこりや腫瘤ができる病態を積聚と呼びます。
「積」
・病位:臓(肝臓、脾臓など)にある病気。
・病態:血の凝滞が主であり、実質的なしこりを形成します。
・特徴:固定不移、つまり痛みの場所やしこりの位置が固定していて移動しないのが特徴です。病程は長く、慢性的な経過をたどります。
「聚」
・病位:腑(胃、大腸など)にある病気。
・病態:気の凝滞が主であり、実質的なしこりは形成しません。
・特徴:聚散無常性の経過をたどります。
積と聚の鑑別は、病程の長短、痛みの移動の有無、血と気のどちらが主か、五臓と六腑のどちらが病位か、という点で行われます。病位の上下は鑑別する上で意味がありません。
問題 肝気鬱滞の聚証に対する治療で用いられる主な方剤はどれか
1.六磨湯
2.木香順気散
3.大七気湯
4.逍遙散
5.甘麦大棗湯
回答→2
【解説】
聚証とは、気の滞りが原因で腹部にしこりや痛みが現れ、その症状が移動したり、現れたり消えたりする病態です。 肝気鬱滞は、精神的なストレスなどによって肝の気の流れが滞った状態です。したがって、肝気鬱滞の聚証とは、肝の気の滞りが腹部に影響を及ぼし、移動性の腹痛やしこりを引き起こしている病態です。この場合の治療原則は、理気、つまり気の流れをスムーズにすることです。
1.六磨湯
気の滞りを解消する方剤ですが、より強力に気の流れを促し、主に腹部の膨満感や便秘に用います。
2.木香順気散
木香や香附子などの理気薬を主薬とし、気の流れをスムーズにし、同時に湿邪を解消する作用があります。気の滞りによる聚証に最も適した方剤の一つです。
3.大七気湯
気の滞りを解消する方剤ですが、主に怒りや憂鬱による胸のつかえや腹痛に用います。
4.逍遙散
肝の気の滞りを解消しますが、気の滞りによる聚証に対する作用は主ではありません。
5.甘麦大棗湯
ヒステリーや精神不安に用いる方剤であり、気の滞りによる腹部の聚証には不適切です。
問題 六淫邪の外襲で巓頂を上犯し、清陽の気の受阻により頭痛を引き起こす。主役の外邪はどれか
1.風
2.寒
3.暑
4.湿
5.熱
回答→1
問題 外感頭痛の症状でないのはどれか
1.掣痛
2.跳痛
3.灼痛
4.脹痛
5.空痛
回答→5
【解説】
1.掣痛
引っ張られるような、引きつるような痛み。風邪による頭痛に多いです。
2.跳痛
脈を打つようにズキズキと痛む。熱邪による頭痛に多いです。
3.灼痛
焼けるように熱く痛む。熱邪が盛んである頭痛に多いです。
4.脹痛
頭がパンパンに張って痛む。気の滞りによる頭痛に多いです。
5.空痛
・空痛とは、空っぽのような、またはぼんやりとした痛みを指します。
・これは、体内の気や血が不足して頭部を養うことができない虚証による頭痛に典型的に見られる症状です。
・外感頭痛のような、外邪の侵入による実証の病態には現れません。
問題 内傷頭痛の診断の要点で誤っているのはどれか。
1.痛みの勢いは比較的緩やか
2.発病は比較的緩慢
3.痛みは休むことなく続く
4.隠痛、空痛、昏痛
5.疲労時に痛みが悪化
回答→3
【解説】
内傷頭痛とは、体内の臓腑や気血の失調が原因で起こる慢性的な頭痛です。虚証による慢性的な頭痛であり、痛みの勢いは弱く、休むと痛みが和らぐ傾向があります。「痛みは休むことなく続く」という特徴は、邪気が盛んな実証の頭痛に当てはまるため、内傷頭痛の診断の要点としては誤りです。
問題 厥陰経頭痛の病位はどこか。
1.後頭部および両側
2.後頭部および項部
3.前額部および眉弓
4.頭の両側および耳部
5.巓頂部あるいは目系に連なる
回答→5
問題 血虚頭痛の常用方剤はどれか。
1.八珍湯
2.人参養栄湯
3.加味四物湯
4.帰脾湯
5.杞菊地黄丸
回答→3
【解説】
1.八珍湯
気と血の両方を補う方剤です。血虚頭痛にも使用できますが、血を補う作用は四物湯が主体となります。
2.人参養栄湯
気血を補い、心を安らかにする方剤で、疲労困憊や不眠を伴う場合に適しています。
3.加味四物湯
四物湯を基本に、血を補いながら血行を促す作用があります。血虚頭痛は血の不足が原因であるため、四物湯を基本としたこの方剤が最も中心的に用いられます。
4.帰脾湯
脾と心の機能を高め、気血を補う方剤で、心脾両虚による不眠や健忘に用います。
5.杞菊地黄丸
腎と肝の陰液を補う方剤で、肝腎陰虚による目の疲れやめまいに用います。
問題 眩暈の病機に属さないのはどれか。
1.肝陽上亢
2.気血虧虚
3.腎精不足
4.痰濁中阻
5.寒邪外襲
回答→5
問題 眩暈の本治に属さないのはどれか。
1.健脾
2.養血
3.益腎
4.養肝
5.潜陽
回答→5
【解説】
潜陽とは、盛んに上逆している肝の陽気を、下方に引き下げる治法です。これは、肝陽上亢という、肝の陰液不足から陽気が上方に盛んに昇った病態に現れるめまいを、一時的に抑える標治に属します。潜陽は、あくまで上逆している陽気を抑える対症療法であり、臓腑の機能を根本的に改善する「本治」ではありません。
問題 ぼうっとするような眩暈頭重で、頭目脹痛、心煩口苦、渇不欲飲、舌苔黄膩、脈弦滑。属する証はどれか。
1.痰熱中阻
2.痰濁中阻
3.肝陽上亢
4.腎陰虧虚
5.瘀血化熱
回答→1
【解説】
患者の症状は、痰と熱が結びついて上方に昇ることで引き起こされた病態であり、これは痰熱中阻の典型的な証候です。
・ぼうっとするような眩暈頭重
「眩暈」はめまい、「頭重」は頭が重く感じる症状です。これらは痰濁(が上方に昇り、清陽を塞いでいるために現れます。
・頭目脹痛
頭や目が張って痛む。これは熱が盛んで気が滞っているためです。
・心煩口苦
気持ちが落ち着かずイライラし(心煩)、口が苦く感じる(口苦)。これは熱邪が心神(精神)を乱しているために起こります。
・渇不欲飲
口が渇くが、水分をあまり欲しない。これは湿熱の典型的な症状で、湿邪が水分を阻滞しているため、体内に水分が停滞していることを示します。
・舌苔黄膩
舌苔が黄色く(黄)分厚く脂っぽい(膩)舌象です。熱と湿邪が停滞していることを示します。
・脈弦滑
脈弦は気の滞りや痰飲、脈滑は痰飲や湿熱の停滞を示す脈象です。
痰濁中阻は痰濁が中焦に停滞している状態ですが、熱の症状(心煩、口苦、舌苔黄)がありません。
問題 中風において中経絡と中臓腑の主な鑑別根拠はどれか。
1.口眼歪斜
2.半身不遂
3.語言不利
4.神志がはっきりするかどうか
5.肢体麻木
回答→4
【解説】
中風とは、現代医学の脳卒中に相当する病態です。中医学では、その重症度や病変が及ぶ範囲によって、中経絡と中臓腑に分類されます。
「中経絡」
病邪が体表の経絡に留まっている状態。
・特徴:病変は経絡の範囲にとどまり、神志、つまり意識は比較的はっきりしています。
・主な症状:口眼歪斜、半身不遂、語言不利、肢体麻木など。
「中臓腑」(閉証・脱証に分類)
病邪が五臓六腑にまで及んだ、より重篤な状態。
・特徴:病変が臓腑を侵すため、神志(意識)の障害が起こります。
・主な症状:突然の意識喪失、昏迷、大小便失禁など。
中風の病変が経絡にとどまっているか、それとも臓腑にまで及んでいるかを判断する最も重要な基準は、患者の意識レベルです。意識がはっきりしていれば中経絡、意識障害があれば中臓腑と診断されます。
問題 中風の中臓腑においてまず弁別すべきはどれか
1.陰証 陽証
2.陰閉 陽閉
3.陰蝎 陽脱
4.痰火 痰濁
5.閉証 脱証
回答→5
【解説】
中風・中臓腑は、中風(脳卒中)の中でも重篤な病態で、意識障害を伴います。病邪が五臓六腑にまで侵入し、生命の危機に直面している状態です。この段階では、病態を緊急に鑑別し、適切な治療を行うことが生死を分ける鍵となります。中風・中臓腑は、大きく以下の二つの証に分けられます。
「閉証」(さらに陽閉・陰閉に分けられます)
邪気が盛んで、気の流れや血の運行を閉塞させている状態。
・主な症状:意識喪失、歯を食いしばる、四肢が硬直するなど。邪気が盛んな実証が中心です。
「脱証」
正気が極度に不足し、体から漏れ出している状態。
・主な症状:意識喪失、口を開けて呼吸する、大小便失禁、四肢が冷え冷えとして力が入らないなど。正気が虚している虚証が中心です。
中風・中臓腑では、正気が邪気によって閉塞されている「閉証」か、正気が体から漏れ出している「脱証」かをまず見極めることが、生命を救うための第一歩となります。この弁別が、その後の治療方針を決定する上で最も重要です。
問題 中風閉証の主症でないのはどれか
1.目合口開
2.牙関緊閉
3.両手を固く握る
4.大小便閉
5.肢体強痙
回答→1
問題 中風における陽閉と陰閉を弁別する際に、主に根拠にならない症状はどれか。
1.顔面紅潮か面白唇暗
2.躁動不安か静かつ不煩
3.舌苔白膩か舌苔黄膩
4.脈沈滑緩か脈弦滑数
5.肢体癱用か肢体強痙
回答→5
【解説】
中風の閉証は、邪気によって気の流れが閉塞し、意識障害を伴う重篤な病態です。この閉証は、邪気の性質(熱邪か寒邪か)によって、さらに「陽閉」と「陰閉」に分けられます。
「陽閉」
・病態:痰熱邪が盛んで、気が上逆して閉塞している。
・特徴:熱証が中心。顔が赤く、口が渇き、呼吸が荒い、イライラして落ち着かない、舌苔が黄色い、脈が速いなど。
「陰閉」
・病態:痰湿邪が盛んで、気の流れが停滞して閉塞している。
・特徴:寒証が中心。顔色が白く、寒がり、体が冷たい、静かでイライラしない、舌苔が白い、脈が遅いなど。
・肢体癱用は半身不随など、身体の一部の麻痺を指します。
・肢体強痙は四肢の硬直やひきつけを指します。
これらの症状は、陽閉・陰閉のどちらでも起こりうるもので、病態の性質(熱か寒か)を区別する根拠にはなりません。どちらも邪気が経絡を閉塞した結果生じる症状です。
陽閉と陰閉の鑑別は、熱証か寒証かという病態の性質に基づきます。肢体の麻痺や痙攣はどちらの病態でも起こりうるため、両者を区別する根拠にはなりません。
問題 中風における閉証と脱証を弁別する際に、主に根拠にならない症状はどれか。
1.目合口開か口噤不開
2.手撒肢冷か両手握固
3.二便自遺か大小便閉
4.肢体軟癱か肢体強痙
5.躁動不安か静かつ不煩
回答→5
【解説】
1.目合口開か口噤不開
・脱証は正気が脱出するため、口や目が開いたままになります。
・閉証は邪気によって固く閉塞されるため、口を固く閉じて開けられません。これは重要な鑑別根拠です。
2.手撒肢冷か両手握固
・脱証は正気がなくなり、手足に力が入らずだらりと開き、冷たくなります。
・閉証は邪気の閉塞で体が強直するため、手を固く握りしめます。これは重要な鑑別根拠です。
3.二便自遺か大小便閉
・脱証は正気の不足でコントロールを失うため、大小便を失禁します。
・閉証は気の閉塞で排泄ができなくなり、大小便が閉塞します。これは重要な鑑別根拠です。
4.肢体軟癱か肢体強痙
・脱証は正気がなくなり、手足がだらりと垂れ下がります。
・閉証は邪気の閉塞で手足が硬直します。これは重要な鑑別根拠です。
5.躁動不安か静かつ不煩
・躁動不安(イライラして落ち着かない)は陽閉の症状です。
・静かつ不煩(静かでイライラしない)は陰閉の症状です。
これらの症状は、どちらも閉証の中で、その性質(熱か寒か)を弁別するためのものであり、閉証と脱証を区別する根拠にはなりません。
問題 痰気が咽喉に鬱結して起こる病証はどれか
1.噎膈
2.癭瘤
3.臓躁
4.梅核気
5.癲証
回答→4
【解説】
1.噎膈
食べ物や飲み物が食道を通らずにつかえたり、吐き出されたりする病気です。痰や瘀血、気鬱が食道に停滞することで起こります。
2.癭瘤
甲状腺腫に相当する病気で、首の前方にできるしこりです。気鬱や痰凝が主な原因となります。
3.臓躁
精神的な不安やヒステリー症状を指します。心や脾が虚弱になったり、血が不足したりすることで起こります。
4.梅核気
咽喉部に梅の種(梅核)が詰まったような感覚があり、飲み込もうとしても吐き出そうとしても取れない病証です。精神的なストレスによる気の鬱滞と、それが生み出す痰が咽喉部に結びつくことで発生します。
5.癲証
精神活動が沈滞し、無表情、無気力、意識障害などが現れる病証です。痰濁が心の竅を塞ぐことで起こります。
問題 肝気鬱結の鬱証の症状でないのはどれか。
1.脘悶噯気
2.腹脹納呆
3.女子の月事不行
4.嘈雑呑酸
5.精神抑鬱
回答→4
【解説】
嘈雑呑酸は肝気鬱結が胃に影響してこれらの症状が起こることはありますが、胃酸過多やむかつきは、気の滞りよりも「熱」や「食積」がより直接的な原因となるため、鬱証の主症状とは言えません。
代表方剤は柴胡疏肝散です。
柴胡 白芍 枳穀 炙甘草 川芎 香附子 陳皮
問題 気鬱化火の鬱症における主症はどれか。
1.嘈雑呑酸、口乾いて苦い
2.胸中窒悶、あるいは脇痛を兼ねる
3.胸脇脹痛、痛みは定まらない
4.心神不寧、悲憂善哭
5.心悸少寝、心煩易怒
回答→1
【解説】
気鬱化火は、「気の滞り」と「熱」が結びついた病態です。したがって、気の滞りによる症状に加えて、熱証(口乾、口苦など)と胃の熱証(嘈雑、呑酸)が同時に現れる、「嘈雑呑酸、口乾いて苦い」が最も適切な主症となります。
代表方剤は丹梔逍遙散合左金丸
柴胡 薄荷 生姜 当帰 白朮 白芍 茯苓 炙甘草 牡丹皮 山梔子+黄連 呉茱萸
問題 陽水の特徴でないのはどれか。
1.多くは風邪を挟む
2.発病は急で、病程は短い
3.皮膚色は光亮で薄い
4.押すと凹み回復し難い
5.頭面部が先に浮腫む
回答→4
【解説】
浮腫は水腫と呼ばれ、その性質によって陽水と陰水に大別されます。
「陽水」
・病態:風邪や湿邪といった外邪が原因で、病気が急激に発症します。
・特徴:体表に邪気が停滞するため、浮腫は頭面部や上肢に現れやすく、色が鮮やかで光沢があります。
・浮腫の状態:邪気によって気の巡りが妨げられるため、浮腫は押すとへこみますが、比較的早く回復します。
・病程:急激に発症し、病程は比較的短いのが特徴です。
「陰水」
・病態:脾、腎、肺といった臓腑の機能が低下し、体内の水分代謝が滞ることで生じます。
・特徴:下肢や腹部から浮腫が始まりやすく、色がくすんで光沢がありません。
・浮腫の状態:押すと凹んで回復し難いのが典型的な特徴です。
・病程:徐々に発症し、病程は長く慢性化しやすいです。
問題 陰水の主な治法はどれか。
1.発汗
2.利尿
3.滋陰
4.化瘀
5.温化
回答→5
【解説】
陰水は、陽気不足による冷えが根本原因であるため、陽気を温め、水湿を解消する温化が最も適切な治療大法です。
※陰水でも利尿薬は用いますが、利尿だけでは陽気の不足という根本原因を解決できません。
問題 風水氾濫証の水腫の治療で選ぶべき方剤はどれか。
1.越婢加朮湯
2.防已黄耆湯
3.大青竜湯
4.五皮飲
5.五苓散
回答→1
【解説】
風水氾濫証とは、風邪と湿邪が結びつき、体表から肺に侵入することで、水液代謝が妨げられ、急激に浮腫(水腫)が現れる病態です。
1.越婢加朮湯
麻黄で発汗させて体表の風邪を取り除き、石膏で熱を清し、甘草や生姜で肺の働きを助け、白朮で水湿を取り除きます。風邪と湿邪による水腫の治療に最も適しており、風水氾濫証の代表的な方剤です。
石膏 麻黄 生姜 大棗 甘草+白朮
2.防已黄耆湯
脾の気を補い、利水を行う方剤です。虚弱な体質で汗をかきやすい人の水腫に用いますが、風邪による急性の病態には不向きです。
3.大青竜湯
風寒邪による発熱、悪寒、体が冷え、発汗がない場合に用いる方剤です。浮腫の治療には直接的ではありません。
4.五皮飲
浮腫の治療に広く用いられますが、特に脾虚や湿邪による浮腫に用いられます。風邪による急性の病態には越婢加朮湯の方がより効果的です。
5.五苓散
水分代謝を調整する方剤です。頭痛や嘔吐を伴う水分代謝失調に用いますが、風邪による急性の水腫には越婢加朮湯の方が適しています。
☆問題 水湿浸漬証の水腫の特徴はどれか。
1.まず瞼の浮腫、続いて四肢と全身に広がる。
2.全身水腫、指で按ると陥没する。
3.全身の浮腫、皮膚はパンパンに張って色は光亮としている
4.腰より下の浮腫が甚だしく、指で按ると陥没する。
5.どれもちがう。
回答→2
【解説】
水湿浸漬証とは、脾の運化作用が失調し、体内に水湿が停滞することで生じる浮腫(水腫)です。
1.まず瞼の浮腫、続いて四肢と全身に広がる。
これは、風邪が体表を侵襲する風水氾濫証の特徴です。風邪は体の高い位置(頭や顔)に現れやすいためです。
2.全身水腫、指で按ると陥没する。
脾の機能低下による水湿の停滞が全身に及んでいるため、全身に浮腫が現れます。また、脾虚によって気が不足するため、浮腫は押すとへこみ、回復が遅い(陥没する)のが特徴です。これは水湿浸漬証の最も典型的な特徴です。
3.全身の浮腫、皮膚はパンパンに張って色は光亮としている
これは、湿熱が盛んな湿熱壅盛証の特徴です。熱が盛んなため、皮膚の色が鮮やかになります。
4.腰より下の浮腫が甚だしく、指で按ると陥没する。
これは、腎の陽気不足による陽虚水泛証の特徴です。腎の陽気不足は体の下半身に現れやすいため、下肢の浮腫が特にひどくなります。
問題 湿熱壅盛証の水腫の治療で選ぶべき方剤はどれか。
1.五皮飲
2.越婢加朮湯
3.麻黄連翹赤小豆湯
4.猪苓湯
5.疏鑿飲子
回答→5
【解説】
1.五皮飲
生薬の皮を主とした方剤で、利水作用がありますが、湿熱を清す作用は弱いです。
2.越婢加朮湯
風邪と湿邪による陽水の初期に用いる方剤です。発汗作用が主であり、湿熱壅盛証には不十分です。
3.麻黄連翹赤小豆湯
表証を伴う黄疸や浮腫に用いる方剤です。湿熱が盛んな裏証には不適切です。
4.猪苓湯
利水作用がありますが、湿熱壅盛証ほどの強い熱には対応できません。主に水分の停滞による排尿困難や尿路感染症に用います。
5.疏鑿飲子
疏鑿とは、塞がった水の道を掘り開くという意味です。この方剤は、湿熱が盛んで気の流れが閉塞し、全身に浮腫が及んでいる場合に、強い利水・清熱作用で邪気を取り除きます。湿熱壅盛証の病態に最も適しています。
問題 腎陽虚の水腫の治療に用いる主な方剤はどれか。
1.生脈散
2.八味地黄丸
3.真武湯
4.左帰丸
5.八仙長寿丹
回答→3
【解説】
1.生脈散
心肺の気と陰を補う方剤で、倦怠感や動悸を伴う場合に用います。水腫の治療には直接的ではありません。
2.八味地黄丸
腎の陰陽を補う方剤ですが、温補作用が比較的穏やかで、強い利水作用はありません。浮腫の治療には不向きです。
3.真武湯
附子、生姜などの温陽薬と、茯苓、白朮などの利水薬を配合しており、腎陽虚による水腫に最も適した方剤です。
4.左帰丸
腎の陰液を補う方剤であり、腎の陽気不足による病態には不適切です。
5.八仙長寿丹
腎を補う方剤ですが、強い利水作用はなく、水腫の治療には不向きです。
問題 淋証の最も重要な特徴はどれか。
1.小便渋痛、少腹満痛
2.小便は熱渋し刺痛あり、尿色が深紅
3.小便は熱渋し疼痛あり、米の研ぎ汁のように混濁している
4.小便は淋瀝し止まらない、時作時止
5.小便が頻数短渋、滴瀝刺痛
回答→5
【解説】
淋証とは、排尿に際して熱感や痛み(渋痛)を伴い、尿が頻繁で量が少なく、スムーズに出ない(頻数短渋)、または一滴ずつしか出ない(淋瀝)といった症状を主とする病態の総称です。現代医学の尿路感染症や膀胱炎などに相当します。