問題 呉茱萸湯の構成生薬でないのはどれか。
1.呉茱萸
2.生姜
3.膠飴
4.大棗
回答→ 3
【解説】
呉茱萸湯の効能は温中補虚、降逆止嘔で、肝陽不足で寒凝による胃気上逆の病証を治療する方剤である。病症の部位は陽明、厥陰、少陰でその症状には全て嘔吐が含まれる。
・胃中虚寒であれば食穀欲嘔、胸膈満悶、胃脘痛、呑酸嘈雑
・厥陰頭痛であれば乾嘔し、涎沫を吐く
・少陰吐利であれば手足厥冷、煩躁
呉茱萸湯(温中袪寒剤)
君薬:呉茱萸
臣薬:人参
佐使薬:生姜、大棗
問題 理中丸の構成生薬はどれか。
1.乾姜
2.附子
3.桂枝
4.蜀椒
回答→ 1
【解説】
理中丸(温中袪寒剤)
君薬:乾姜
臣薬:人参
佐薬:白朮
使薬:炙甘草
問題 小建中湯の構成生薬はどれか。
1.芍薬
2.人参
3.乾姜
4.蜀椒
回答→ 1
【解説】
小建中湯の効能は温中補虚、和裏緩急で、虚労裏急の病証の治療方剤である。
症状は、腹中が時々痛むが温めると緩和、舌淡苔白、脈細緩、虚煩不寧、面色無華、四肢痠楚、手足煩熱、咽乾口燥。
※痠楚=筋肉や関節のだるさ
小建中湯(温中虚寒剤)
君薬:膠飴
臣薬:桂枝、芍薬
佐薬:炙甘草
佐使薬:生姜、大棗
☆小建中湯は桂枝湯の芍薬を倍量にして、膠飴を加えたものである。
【桂枝湯】
君薬:桂枝
臣薬:芍薬
佐薬:生姜、大棗
使薬:炙甘草
問題 四逆湯の構成生薬はどれか。
1.柴胡 枳殻 芍薬 甘草
2.附子 乾姜 炙甘草
3.柴胡 枳実 芍薬 炙甘草
4.炮附子 乾姜 甘草
5.炮附子 乾姜 人参 甘草
回答→ 2
【解説】
四逆湯(回陽救逆剤)
| 生薬名 | 分類 | 主な働き |
|---|---|---|
| 附子 | 君薬 | 回陽救逆。陽気を強力に回復させ、虚脱状態を救います。 |
| 乾姜 | 臣薬 | 温中散寒。胃腸の冷えを温め、寒邪を散らします。 |
| 炙甘草 | 佐薬・使薬 | 補中益気。脾胃を補い、附子と乾姜の作用を調和させます。 |
当帰四逆湯は、桂枝湯から生姜を除き、当帰、細辛、通草を加えたもの。
当帰四逆湯(温経散寒剤)
君薬:当帰、桂枝
臣薬:芍薬、細辛
佐薬:通草
使薬:大棗、炙甘草
【傷寒論の四逆と名がつく方剤】
・四逆散ー和解表裏に重点
・四逆湯ー回陽に重点
・当帰四逆湯ー養血通脈に重点
問題 陽和湯の構成生薬はどれか。
1.生地黄・姜炭・鹿角膠
2.塾地黄・姜炭・亀板膠
3.塾地黄・姜炭・鹿角膠
4.塾地黄・姜炭・鹿角霜
回答→ 3
【解説】
陽和湯の効能は温陽補血、散寒通滞で、陽虚寒凝証による陰疽などの治療をする方剤である。例えば慢性骨髄炎、壊疽などがこの病証に属せば使用する。
陽和湯(癰瘍剤)
君薬:塾地黄
臣薬:鹿角膠
佐薬:姜炭、肉桂
使薬:麻黄、白芥子、甘草
問題 患者、平素から陽気不足で、汗出した時に風にあたり肌膚が麻木不仁となった。脈微渋緊。選ぶべき法剤はどれか。
1.陽和湯
2.桂枝湯
3.当帰四逆散
4.黄耆桂枝五物湯
回答→ 4
【解説】
黄耆桂枝五物湯はの効能は温通陽気、調暢営血で、風痹のようで脈微渋・緊を呈する病証の治療に用いる。
黄耆桂枝五物湯は桂枝湯から甘草を除き、生姜を倍増して黄耆を加えた方剤である。
1.陽和湯(癰瘍剤)ー陽虚寒凝証による陰疽などの治療
2.桂枝湯(辛温解表剤)ー外感風寒の表虚証の治療。
3.当帰四逆散(温経散寒剤)ー陽虚と血虚で寒邪が経絡に阻滞する病証の治療。
4.黄耆桂枝五物湯(温経散寒剤)ー風痹のようで脈微渋・緊を呈する病証の治療
問題 陽和湯で最も多く使われる生薬はどれか。
1.塾地黄
2.麻黄
3.鹿角膠
4.肉桂
回答→ 1
問題 患者、倦怠乏力、食少便溏、四肢不温、皮下出血、瘀班の色が淡暗、舌淡、苔薄白、脈沈遅。選ぶべき法剤はどれか。
1.理中丸
2.附子理中丸
3.四逆湯
4.四逆散
回答→1
【解説】
理中丸の効能は温中袪寒、補気健脾で、脾胃陽虚の病証を治療する。
理中丸(温中袪寒剤)
君薬:乾姜
臣薬:人参
佐薬:白朮
使薬:炙甘草
1.理中丸(温中袪寒剤)ー脾胃陽虚の病証の治療。
2.附子理中丸ー理中丸証に心痛、藿乱による吐利・転筋などの治療
3.四逆湯(回陽救逆剤)ー陽衰陰盛による四逆の治療。心不全やショック。
4.四逆散(調和肝脾剤)ー少陰病、肝鬱で陽気鬱滞による四逆証の治療。
問題 理中丸と呉茱萸湯で共通する生薬は?
1.呉茱萸
2.大棗
3.乾姜
4.人参
回答→ 4
問題 大建中湯の効能はどれか。
1.温中袪寒 緩急止痛
2.温中補虚 緩急止痛
3.温中補虚 降逆止嘔
4.温中散寒 益気健脾
5.温中補虚 降逆止痛
回答→ 5
| 生薬名 | 分類 | 主な働き |
|---|---|---|
| 蜀椒 | 君薬 | 温中散寒、行気止痛 |
| 乾姜 | 臣薬 | 温中散寒、回陽通脈 |
| 人参 | 佐薬 | 益気健脾、生津止渇 |
| 膠飴 | 使薬 | 補中益気、緩急止痛 |
大建中湯は、体が冷えてお腹が痛むときに使われる漢方薬です。「お腹を大きく建てて(大建)、冷えをなくす(中湯)」という目的をイメージすると、生薬の組み合わせを理解しやすくなります。
この方剤は、冷えに働く温める生薬(乾姜、蜀椒)と、お腹の緊張を緩めて痛みを和らげる生薬(膠飴)、そしてこれらを助ける生薬(人参)で構成されています。それぞれの生薬がどのような役割を果たしているかを理解することで、より記憶に残りやすくなります。
問題 患者、食穀欲嘔、胸膈満悶、胃脘痛、呑酸嘈雑、四肢不温、舌淡苔白滑、脈沈細遅。選ぶべき法剤はどれか。
1.呉茱萸湯
2.小建中湯
3.左金丸
4.理中丸
回答→1
【解説】
1.呉茱萸湯(温中袪寒剤)ー肝陽不足で寒凝による胃気上逆の病証を治療
2.小建中湯(温中袪寒剤)ー虚労裏急の病証を治療。
3.左金丸(清臓腑熱剤)ー肝鬱化火による肝火犯胃の病証の治療。
4.理中丸(温中袪寒剤)ー脾胃陽虚の病証の治療。
問題 小建中湯は桂枝の何を倍量にしたものか。
1.桂枝
2.大棗
3.炙甘草
4.芍薬
回答→ 4
【解説】
小建中湯は桂枝湯の芍薬を倍量にして、膠飴を加えたものである。
問題 患者、腹中が時々痛むが温めると緩和、舌淡苔白、脈細緩、虚煩不寧、面色無華、四肢痠楚、手足煩熱、咽乾口燥。選ぶべき法剤はどれか。
1.大建中湯
2.小建中湯
3.呉茱萸湯
4.温脾湯
回答→ 2
【解説】
1.大建中湯(温中袪寒剤)ー脾胃陽虚で寒凝気滞と寒凝気逆などの病証の治療。補虚散寒の力が小建中湯よりも強い。
2.小建中湯(温中袪寒剤)ー虚労裏急の病証を治療。
3.呉茱萸湯(温中袪寒剤)ー肝陽不足で寒凝による胃気上逆の病証を治療。
4.温脾湯(温下剤)ー脾陽不足、冷積内生による諸証の治療。
問題 患者、心胸の中に大寒痛があり、嘔吐して食べれない、腹に腸の蠕動も見られる、腹中雷鳴、舌苔白滑、脈細緊。選ぶべき法剤はどれか。
1.呉茱萸湯
2.大建中湯
3.小建中湯
4.厚朴温中湯
回答→ 2
【解説】
1.呉茱萸湯(温中袪寒剤)ー肝陽不足で寒凝による胃気上逆の病証を治療。
2.大建中湯(温中袪寒剤)ー脾胃陽虚で寒凝気滞と寒凝気逆などの病証の治療。補虚散寒の力が小建中湯よりも強い。
3.小建中湯(温中袪寒剤)ー虚労裏急の病証を治療。
4.厚朴温中湯(行気剤)ー寒湿が脾胃を傷つけ、気滞による病証の治療。例えば急性の胃腸の病気が寒湿による脾胃気滞という病証に属せば使用する。
問題 患者、心中悸動、虚煩不寧、面色無華、脈緩。選ぶべき法剤はどれか。
1.当帰四逆湯
2.四逆湯
3.小建中湯
4.帰脾湯
5.炙甘草湯
回答→ 3
【解説】
これらの症状は、中焦虚寒、すなわち脾胃の陽気が不足し、冷えと虚弱があるために生じる病態、あるいはそこから派生した気血不足の状態を示唆している。特に「心中悸動」「面色無華」「脈緩」は、血虚や虚弱体質からくる症状としてよく見られる。
1.当帰四逆湯
主に血虚と寒邪が同時に体表に侵入し、経絡を阻害することで生じる手足の冷えや痛みを治療する。血虚寒凝に特化。
2.四逆湯
回陽救逆、すなわち極度に消耗した陽気を回復させ、危機的な状態から救うための強力な方剤。
3.小建中湯
主に中焦虚寒、つまり脾胃の陽気が不足し、冷えと虚弱があるために生じる腹痛や倦怠感を治療する。
4.帰脾湯
心脾両虚、すなわち心と脾の両方が虚弱になり、気血が不足して生じる様々な症状を治療する。
5.炙甘草湯
復脈湯とも呼ばれます。主に心陰虚、心気虚、心陽虚が同時に存在し、気血陰陽が虚損して脈が不整になる病態を治療する。
問題 患者、四肢厥逆、悪寒踡臥、嘔吐不渇、腹痛下痢、神疲欲寝、脈微細。選ぶべき法剤はどれか。
1.当帰四逆湯
2.四逆湯
3.小建中湯
4.帰脾湯
5.炙甘草湯
回答→ 2
【解説】
これらの症状は、陽気が極度に虚弱になり、生命活動を維持できない危機的な状態、すなわち陽虚欲脱の典型的な病態を示す。特に「四肢厥逆」「悪寒踡臥」「脈微細」は、陽気の深刻な不足と寒邪の盛んさを強く示唆している。
1.当帰四逆湯
主に血虚と寒邪が同時に体表に侵入し、経絡を阻害することで生じる手足の冷えや痛みを治療する。血虚寒凝に特化。
2.四逆湯
回陽救逆、すなわち極度に消耗した陽気を回復させ、危機的な状態から救うための強力な方剤。
3.小建中湯
主に中焦虚寒、つまり脾胃の陽気が不足し、冷えと虚弱があるために生じる腹痛や倦怠感を治療する。
4.帰脾湯
心脾両虚、すなわち心と脾の両方が虚弱になり、気血が不足して生じる様々な症状を治療する。
5.炙甘草湯
復脈湯とも呼ばれます。主に心陰虚、心気虚、心陽虚が同時に存在し、気血陰陽が虚損して脈が不整になる病態を治療する。
問題 当帰四逆湯の効能はどれか。
1.温経散寒 養血袪瘀
2.温経散寒 養血通脈
3.活血化瘀 温経止痛
4.温陽補血 散寒通滞
5.温中散寒 行気止痛
回答→ 2
問題 生化湯の効能はどれか。
1.温経散寒 養血袪瘀
2.温経散寒 養血通脈
3.活血化瘀 温経止痛
4.温陽補血 散寒通滞
5.温中散寒 行気止痛
回答→ 3
問題 小建中湯の効能はどれか。
1.温中袪寒 補気健脾
2.温中補虚 降逆止痛
3.温中補虚 健脾益気
4.温中補虚 降逆止嘔
5.温中補虚 和裏緩急
回答→ 5
問題大建中湯の効能はどれか。
1.温中袪寒 補気健脾
2.温中補虚 降逆止痛
3.温中補虚 健脾益気
4.温中補虚 降逆止嘔
5.温中補虚 和裏緩急
回答→ 2
問題 呉茱萸湯の効能はどれか。
1.温中袪寒 緩急止痛
2.温中補虚 緩急止痛
3.温中補虚 降逆止嘔
4.温中散寒 益気健脾
5.温中補虚 降逆止嘔
回答→ 3
問題 患者、腹中が時々痛み、喜温喜按、面色無華、心悸不寧、手足煩熱、咽乾口燥、舌淡苔白、脈細弦かつ緩。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.大建中湯
2.小建中湯
3.呉茱萸湯
4.理中湯
5.温脾湯
回答→ 2
【解説】
この症例は、脾胃の働きが弱り、体内の陽気と陰液の両方が不足している脾の陰陽両虚という状態です。
・腹中が時々痛み、喜温喜按: これは脾陽虚、つまり脾胃の陽気が不足して冷えが生じている典型的な症状です。温めたり、押さえたりすると痛みが和らぎます。
・面色無華、咽乾口燥: 顔色に艶がなく、喉や口が乾燥するのは、血や津液が不足している陰虚の兆候です。
・心悸不寧、手足煩熱: 動悸や手足のほてりは、陰陽のバランスが崩れ、営衛不和という状態になっていることを示します。
・舌淡苔白、脈細弦かつ緩: 舌が淡く、苔が白いのは陽気不足、脈が細く、弦で緩やかなのは、気血が不足していることを示しています。
これらの症状が組み合わさって、小建中湯の治療対象である「虚労裏急」という病態を形成しています。
1.大建中湯
脾胃の陽虚がさらに進み、激しい腹痛や腸の蠕動が外から見えるほどの重い病態に用います。小建中湯よりも強い痛みや吐き気(気逆)を伴うのが特徴です。
3.呉茱萸湯
肝陽の不足による、胃の冷えと気の逆流が原因の吐き気や酸っぱいゲップなどに用います。
4.理中湯
脾胃の陽虚が原因で、下痢や嘔吐がある場合に用います。口渇や手足のほてりといった陰虚の症状はありません。
5.温脾湯
脾陽不足による強い冷えが原因の便秘や下痢に用います。
| 鑑別点 | 小建中湯 | 大建中湯 |
|---|---|---|
| 病態の要点 | 脾胃の陰陽両虚。慢性的な虚弱や疲労による不調。 | 脾胃の陽虚が極度に進行し、強い冷えと気の滞りがある状態。 |
| 主な腹痛症状 | 腹痛は時々起こり、喜温喜按(温めたり押さえたりすると楽になる)。 | 激しい腹痛で、拒按(押さえると痛みがひどくなる)。腹壁に腸の蠕動が見えることも。 |
| その他の症状 | 心悸不寧(動悸)、手足煩熱(ほてり)、咽乾口燥(口や喉の乾燥)など、陰液不足の症状を伴う。 | 嘔吐、腹部膨満感、著しい寒冷(ひどい冷え)。 |
| 治療の目的 | 脾胃の働きを穏やかに回復させ、陰陽と営衛のバランスを整える。 | 内臓の強い冷えを取り除き、気の滞りを解消して激しい痛みを止める。 |
問題 患者、心胸中大いに寒え痛み、嘔して飲食することあたわず、腹中寒え攻衝し、上下し痛みて触れ近づかず、苔白滑、脈細緊。治療でまず選ぶべきものはどれか?
1.理中丸
2.呉茱萸湯
3.小建中湯
4.大建中湯
5.厚朴温中湯
回答→ 4
【解説】
この症例は、脾胃の陽気が極度に不足し、強い冷えによって寒凝気滞と寒凝気逆という重篤な病態に陥ったものです。
・心胸中大いに寒え痛み、上下し痛みて触れ近づかず(拒按): これは、冷えが強く気の巡りを妨げ、激しい痛みを引き起こしている状態です。特に、「触れ近づかず(拒按)」という表現は、痛みが非常に強いことを示しています。
・腹中寒え攻衝し、嘔して飲食することあたわず: 体内の冷えが激しく、気が上へ逆流していることを表します。これにより、吐き気が止まらず、飲食ができない状態です。
・苔白滑、脈細緊: 舌の苔が白く滑らかで、脈が細く、緊迫しているのは、体内の陽気が不足し、強い冷えと気の滞りがあることを反映しています。
これらの症状は、脾陽虚が重症化した大建中湯の典型的な治療対象です。
1.理中丸
脾陽虚を温めますが、この症例のような激しい腹痛や嘔吐には対応できません。
2.呉茱萸湯
肝陽不足による胃の気の逆流を治療します。
3.小建中湯
脾胃の陰陽両虚を治療するもので、この症例のような強い腹痛や嘔吐の症状には不十分です。
5.厚朴温中湯
寒湿による気の滞りを治療しますが、この症例のような強い「寒凝」には大建中湯の方が適しています。
問題 心中悸動、虚煩不寧、面色無華、脈緩、治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.当帰四逆湯
2.四逆湯
3.小建中湯
4.帰脾湯
5.炙甘草湯
回答→ 3
【解説】
この症例は、心悸不寧(動悸や不安)と虚弱(虚労)の症状が中心です。症状を詳しく分析すると、以下の病理状態が明らかになります。
・面色無華: 顔色に艶がないのは、営血不足、すなわち血液が不足している状態を反映しています。
・心中悸動、虚煩不寧: 血液が不足すると、心を十分に養うことができなくなり(心神失養)、心神が落ち着かず、動悸や煩わしい不安感が生じます。
・脈緩: 脈がゆったりとして力がないのは、脾胃の機能が虚弱になっている(脾胃虚弱)典型的な兆候です。
これらの症状を総合すると、脾胃の虚弱が根本にあり、それが気血不足を引き起こし、最終的に心神に影響を与えている病態であると判断できます。この状態は、中医学で「虚労(虚弱)」と総称されます。
ポイント
本症例で最も重要な鑑別点は、脈緩という脈の特徴です。
心悸不寧を治療する方剤は他にもありますが、脈の特徴を比較することで、最適な方剤を絞り込むことができます。
・小建中湯
虚労裏急の代表方剤で、脾胃を立て直すことで気血を補い、心神を安んじます。脈が緩やかであるこの症例に最も合致します。
・帰脾湯
心脾両虚による動悸を治療しますが、脈は一般的に細く緩やか(脈細緩)で、血虚がより顕著な場合に用います。
・炙甘草湯
気陰両傷による虚労を治療し、脈は結んだり途切れたりする(結代脈)のが特徴です。この脈は本症例の脈とは異なります。
注意点
小建中湯は、その名の通り「中(ちゅう)」(中焦、脾胃を指す)を立て直すことで、後天の根本である脾胃の働きを回復させます。これにより、気血の生成を促進し、心を養うことで動悸や虚煩を根本から改善します。理気薬などを加えず、脾胃の機能を回復させることで、自然に気血が満ちるように導くのがこの方剤の機序です。
問題 患者、胃脘冷痛、胸膈満悶、食後欲嘔、呑酸嘈雑、四肢不温、舌淡苔白滑、脈沈細遅。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.理中湯
2.小建中湯
3.左金丸
4.呉茱萸湯
5.四逆湯
回答→ 4
【解説】
この症例は、肝の陽気が不足して冷えが生じ、その冷えが胃に影響を与えている肝寒犯胃という病態です。
・胃脘冷痛、四肢不温: 胃の冷えによる痛みが顕著で、手足も温かさがありません。これは、体内の陽気が不足し、特に胃に寒が凝り固まっている状態を反映しています。
・食後欲嘔、呑酸嘈雑: 食べた後に吐き気がしたり、酸っぱいものがこみ上げたり、胸焼けがするのは、冷えによって胃の気が上へ逆流している胃気上逆という病理状態を示します。
・舌淡苔白滑、脈沈細遅: 舌が淡く、苔が白く滑らかで、脈が深く、細く、遅いのは、体内の陽気が不足し、冷えが強いことを反映する典型的な症状です。
これらの症状を総合すると、脾胃の陽虚が根底にあり、肝の冷えが胃に波及して、気の逆流を引き起こしていると判断できます。
鑑別のポイント:呉茱萸湯 vs. 左金丸
呉茱萸湯と左金丸は、どちらも「呑酸嘈雑」を治療し、呉茱萸を配合するという共通点がありますが、病態の「熱」か「寒」かによって明確に区別されます。
・呉茱萸湯
肝が冷えを伴って胃を犯す「肝寒犯胃」を治療します。症状は冷えが主体で、舌は淡く、脈は沈細遅です。この方剤では、胃の冷えを散らし、気の逆流を止めるために、呉茱萸を主薬(君薬)とし、その働きを助けるために人参・生姜が多めに配合されます。
・左金丸
肝の熱が胃を犯す「肝火犯胃」を治療します。症状は熱が主体で、舌に黄色い苔(黄苔)が見られ、脈は弦で速い(弦数脈)です。この方剤は熱を冷ます目的で、黄連が主薬となり、呉茱萸より6倍以上多く配合されます。
1.理中湯
脾胃の陽虚による下痢や嘔吐に用いますが、肝寒による呑酸嘈雑は治療対象ではありません。
2.小建中湯
虚労裏急を治療し、腹痛に温按で楽になる特徴がありますが、気の逆流による激しい嘔吐には向きません。
5.四逆湯
陽気の衰退が極度に進行した「陽衰陰盛」による四肢の冷えを治療する、より重篤な病態に用います。
問題 患者、食穀欲嘔、胸膈満悶、胃脘疼痛、呑酸嘈雑。治療でまず選ぶべき方剤はどれか?
1.竹葉石膏湯
2.平胃散
3.小建中湯
4.保和丸
5.呉茱萸湯
回答→ 5
【解説】
この症例は、一見すると「熱」や「冷え」が分かりにくいかもしれませんが、症状の組み合わせと、他の選択肢との比較から、根本的な病因を判断できます。
・食穀欲嘔、呑酸嘈雑
食べた後に吐き気がしたり、酸っぱいものがこみ上げたりするのは、胃の気が上へ逆流している「胃気上逆」という病態を示します。
・胸膈満悶、胃脘疼痛
胸からみぞおちにかけての張りや苦しさ、そして胃の痛みは、気の巡りが滞っている「気滞」を示しています。
これらの症状は、肝の気が胃に影響を与えている「肝犯胃」という病態に共通します。この病態の原因には「肝の熱」と「肝の冷え」の2つがあり、どちらかを鑑別する必要があります。
「冷え」の判断根拠
この問題文には、「熱」を判断する以下の典型的な症状がありません。
口渇、顔面紅潮、脈数、黄苔など。これらの熱の兆候がないため、胃気上逆や気の滞りの根本原因は「熱」ではなく、「冷え」であると判断できます。つまり、肝寒犯胃という病態であり、これは呉茱萸湯が治療するものです。
1.竹葉石膏湯
熱による「欲嘔」を治療しますが、この症例に見られる胃の冷えや痛みには対応できません。
2.平胃散
湿気による消化器の不調に用います。
4.保和丸
食滞を治療する方剤です。
問題 四肢厥逆、悪寒踡臥、嘔吐不渇、腹痛下利、神疲欲寝、脈微細、治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.当帰四逆湯
2.四逆湯
3.小建中湯
4.帰脾湯
5.炙甘草湯
回答→ 2
【解説】
この症例は、体内の陽気が極度に衰退し、陰気が非常に盛んになった、陽衰陰盛という重篤な病態です。
・四肢厥逆、悪寒踡臥
手足が冷え、ひどい悪寒で体を丸めて寝たがります。これは、陽気が体の末端まで届かず、内臓にこもっている寒厥という状態を示しています。
・嘔吐不渇、腹痛下利
嘔吐があるのに喉の渇きはなく、腹痛と下痢を伴います。これは、脾胃に寒邪が盛んで、水分代謝が故障していることを反映しています。
・神疲欲寝
精神的に疲弊し、横になっていたいのは、陽気が不足して心神を養うことができなくなっているためです。
・脈微細
が非常に微かで細いのは、陽虚がかなり進行していることを示します。
これらの症状は、陽気の極度の衰退による回陽救逆が必要な状態であり、四逆湯が最も適しています。
四逆湯は、熱性の生薬である附子、乾姜、甘草で構成され、強力に体を温め、陽気を回復させることで、虚脱状態から救うことを目的とします。
鑑別のポイント:四逆湯 vs. 当帰四逆湯
四肢厥逆を治療する方剤はいくつかありますが、この症例では脈の特徴が重要な鑑別点となります。
・四逆湯
陽衰陰盛による四肢厥逆の代表方剤で、脈は微細です。
・当帰四逆湯
陽虚と血虚が原因で、寒邪が経絡に滞り、手足の冷えが顕著な場合に用います。脈は細欲絶あるいは沈細です。
四逆散vs. 四逆湯
・四逆散は、ストレスなどによる「気の滞り」が原因で手足が冷える、比較的軽度な病態に用います。冷えは末端に限られ、体幹には熱があることもあります。
・四逆湯は、体が冷え切って虚脱状態に陥るような、生命の危機に関わる重篤な病態に用います。内臓まで冷え切っているのが特徴です。
問題 患者、元来の陽気不足で、汗をかく時に風にあたり、肌膚が麻木不仁となる。脈微渋かつ緊。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.陽和湯
2.桂枝湯
3.麻黄細辛附子湯
4.当帰四逆湯
5.黄耆桂枝五物湯
回答→ 5
【解説】
この症例は、患者がもともと持っている陽気不足に、発汗時に風邪が侵入したことによって引き起こされたものです。
1.陽和湯
陽虚による重い冷えが原因で生じる、皮膚の腫れや痛みを伴う慢性的な病態に用います。
2.桂枝湯
風邪による表虚証を治療する代表的な方剤ですが、この症例のような血脈不通による「肌膚不仁」や、元来の「陽気不足」には対応できません。
3.麻黄細辛附子湯
もともと陽虚がある患者が外感風寒を患った場合に用います。発熱は軽いものの悪寒が強く、無汗で、脈は沈であるのが特徴です。
4.当帰四逆湯
陽虚と血虚が原因で、冷えが経絡に滞り、手足の冷えが顕著な場合に用います。
5.黄耆桂枝五物湯
この方剤は、衛気と営陰の不足に風邪が侵入して生じた血脈不通を治療します。特に肌膚不仁(皮膚のしびれや感覚異常)が特徴です。桂枝湯から甘草を除き、黄耆を加えることで、益気作用が強化されています。
問題 患者、倦怠乏力、食少便溏、四肢不温、皮下出血、瘀斑の色が淡暗で、舌淡、苔薄白、脈沈遅。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.理中丸
2.附子理中丸
3.四逆散
4.四逆湯
5.当帰四逆湯
回答→ 1
【解説】
この症例は、脾胃の陽気が不足して冷えが生じ、その結果として様々な症状が現れた状態です。
・倦怠乏力、食少便溏
体がだるく力が入らず、食欲がなく、便が柔らかいのは、脾胃の働きが弱っている(脾陽虚)ことを示しています。
・四肢不温
手足が温かくないのは、脾陽虚によって内臓に冷え(内寒)が生じ、陽気が体の末端まで届いていないことを示唆します。
・皮下出血、瘀斑の色が淡暗
この症状は、脾の重要な働きの一つである統血が失われた(脾不統血)ことを反映しています。
これらの症状を総合すると、脾陽虚が原因で内寒が生じ、統血作用が失われている中焦虚寒による出血という病態であると判断できます。
1.理中丸
脾陽を温めて内寒を散らし、脾の働きを正常に戻します。これにより、脾の統血作用が回復し、出血も改善されます。止血薬を直接用いるのではなく、根本原因である脾陽虚を治療することで出血を止めるのが特徴です。
2.附子理中丸
理中丸に附子を加えたもので、より強い冷え(脾胃虚寒)による腹痛や吐き気、下痢などに用います。この症例はそこまで重篤な症状ではありません。
3.四逆散
気の滞りが原因で手足が冷える病態に用います。
4.四逆湯
陽気の極度の衰退による重篤な冷えに用います。
5.当帰四逆湯
血虚と陽虚が原因で、冷えが経絡に滞り、手足の冷えが顕著な場合に用います。
問題 患者、常に月経量が少なく、周期が延長、時に次の月経まで40~50日かかることもある。冬になると手、足及び耳部等に凍瘡が発生し、肢冷畏寒、舌淡苔薄白、脈細遅。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.四逆湯
2.四逆散
3.小建中湯
4.当帰四逆湯
5.桂枝人参湯
回答→ 4
【解説】
この症例は、もともとの陽気不足と血虚があり、そこに寒邪が侵入して経絡を滞らせたことで引き起こされたものです。血虚と陽虚が同時に存在し、その結果、寒邪が経絡に滞り、血行不良を引き起こしていると判断できます。
ポイント
この症例の鍵は、血虚と陽虚が同時に存在し、それが寒邪の経絡阻滞を引き起こしている点です。当帰四逆湯は、当帰で血を補い、桂枝や細辛で体を温めて冷えを散らし、血脈の滞りを改善します。これにより、根本原因と末梢の症状の両方を治療することができます。
問題 小建中湯の構成生薬はどれか?
1.桂枝湯から芍薬を除き、甘草を倍量にする
2.桂枝湯から芍薬を除き、飴糖を加える
3.桂枝湯の芍薬を倍量にし、飴糖を加える
4.桂枝湯の甘草を倍量にし、飴糖を加える
5.桂枝湯の甘草と芍薬を倍量にする
回答→ 3
温裏剤のまとめ
温中袪寒剤(中焦虚寒証を治療)
・理中丸ー中焦虚寒による腹痛、吐利を治療。
・呉茱萸湯ー胃に重点をおく。陽明、厥陰、少陰の三経虚寒証による陰寒上逆の嘔吐頭痛などを治療。
・小建中湯ー虚労裏急の病証を治療。補虚を主とする。
・大建中湯ー脾胃陽虚で寒凝気滞と寒凝気逆などの病証の治療。補虚散寒の力が小建中湯よりも強い。袪邪を主とする。
回陽救逆剤(陽気微衰、陰寒内盛による四肢厥逆、陽気が絶えそうな危証を治療)
・四逆湯ー陽衰陰盛による四逆の治療。心不全やショック。
・回陽救逆湯ー陰寒内盛・陽微欲脱の危証を治療。
・黒錫丹ー濁陰上逆・腎不納気・陽気が絶えそうな危証及び奔豚気・寒疝の重症を治療。
温経散寒剤(陽虚血弱、経絡有寒による病証の治療)
・当帰四逆湯ー血虚受寒による脈細欲絶・手足厥寒の病証を治療。
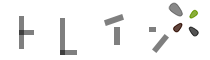




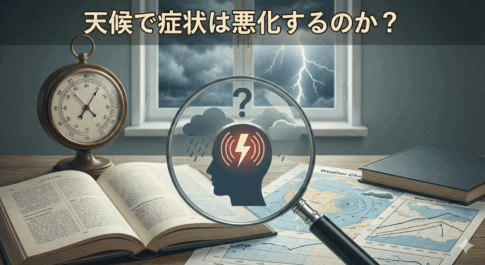


コメントを残す