問題 患者、夏に外出から帰宅すると、軽い身熱と口渇があり、頭目不清、眩暈、舌淡紅、苔薄白。選ぶべき法剤はどれか。
1.香薷散
2.新加香薷飲
3.清絡飲
4.桑菊飲
回答→ 3
【解説】
清絡飲の効能は袪暑清熱で、夏月に暑が肺経を傷つけておきた身熱、口渇、頭目不清(頭がはっきりせず、目もぼんやり)の病証を治療する。ようするに夏バテの治療薬である。
清絡飲(袪暑清熱剤)
君薬:金銀花、扁豆花
臣薬:西瓜翠衣、絲瓜皮
佐薬:荷葉、竹葉
※西瓜翠衣(せいかすいい)=スカイの皮の白い部分
1.香薷散(袪暑解表剤)ー暑に寒邪を感受して湿を挟む病証の治療。温性である。
2.新加香薷飲(袪暑解表剤)ー外寒束表、裏に暑熱がある病証の治療。涼性である。
3.清絡飲(袪暑清熱剤)ー夏バテの治療。
4.桑菊飲ー(辛涼解表剤)ー風熱犯肺の病証の治療。
問題 患者、夏に冷たいものを飲んで、微悪寒発熱をおこし、無汗、身重困倦、胸悶氾嘔、腹痛吐瀉、舌苔白膩、脈浮。選ぶべき法剤は?
1.連朴飲
2.新加香薷飲
3.香薷散
4.清暑益気湯
回答→ 3
【解説】
患者は夏に冷たいものを飲んで、外は寒邪、内は湿の侵襲を受けたとみられる。
香薷散の効能は、袪暑解表、化湿和中で、暑に寒邪を感受して湿を挟む病証の治療に用いる。
香薷散(袪暑解表剤)
君薬:香薷
臣薬:白扁豆
佐薬:厚朴
新加香薷散(袪暑解表剤)
君薬:香薷
臣薬:鮮扁豆花、金銀花、連翹
佐薬:厚朴
【2つの方剤の鑑別】
・香薷散(袪暑解表剤)ー暑に寒邪を感受して湿を挟む病証の治療。温性である。
症状:夏に冷たいものを飲んで、微悪寒発熱をおこし、無汗、身重困倦、胸悶氾嘔、腹痛吐瀉、舌苔白膩、脈浮。
・新加香薷飲(袪暑解表剤)ー外寒束表、裏に暑熱がある病証の治療。涼性である。
症状:発熱、頭痛、悪寒無汗、口渇して面赤、心煩、胸悶不舒、舌苔白膩、脈浮数。夏の風邪の症状である。
問題 患者、発熱、頭痛、悪寒無汗、口渇して面赤、心煩、胸悶不舒、舌苔白膩、脈浮数。選ぶべき法剤は?
1.連朴飲
2.新加香薷飲
3.香薷散
4.清暑益気湯
回答→ 2
問題 患者、暑湿を感受。発熱頭痛、煩渇引飲、小便不利、霍乱吐下がみられる。選ぶべき法剤は?
1.麻杏甘石湯
2.新加香薷飲
3.桂苓甘露飲
4.清暑益気湯
回答→ 3
【解説】
桂苓甘露飲の効能は、袪暑清熱、化気利湿で、暑熱感受+水湿内停による脾胃の昇降失職の治療。
※霍乱吐下ー吐き下しが同時にある。=脾胃昇降失職による清濁不分
※煩渇引飲ー口渇がはなはだしく、いくら飲んでも飲み足りないこと
桂苓甘露飲(袪暑利湿剤)
君薬:滑石
臣薬:寒水石、石膏
佐薬:官桂、猪苓、沢瀉、茯苓、白朮
1.麻杏甘石湯(辛涼解表剤)ー表邪未解、肺熱咳嗽の病証の治療。
2.新加香薷飲(袪暑解表剤)ー外寒束表、裏に暑熱がある病証の治療。
3.桂苓甘露飲(袪暑利湿剤)ー暑熱感受+水湿内停による脾胃の昇降失職の治療。
4.清暑益気湯(清暑益気剤)ー暑熱が気津を傷つける病証の治療
問題 患者、中暑受熱、身熱多汗、心煩口渇、小便短赤、体倦少気、精神不振、脈虚数。選ぶべき法剤は?
1.生脈散
2.六一散
3.清暑益気湯
4.碧玉散
回答→ 3
【解説】
清暑益気湯の効能は清暑益気、養陰生津で、暑熱が気津を傷つける病証の治療に用いる。
清暑益気湯(清暑益気剤)
君薬:西洋人参、西瓜翠衣
臣薬:桔梗、石斛、麦門冬
佐薬:黄連、知母、竹葉
使薬:甘草、粳米
1.生脈散(補気剤)ー肺心の気津不足の病証の治療。
2.六一散(袪暑利湿剤)ー暑熱を感受で、湿熱擾心、気津損傷の病証の治療。
3.清暑益気湯(清暑益気剤)ー暑熱が気津を傷つける病証の治療
4.碧玉散(袪暑利湿剤)ー六一散の病証に肝胆鬱熱が加わった場合の治療。
問題 患者、暑病後で余熱がまだあり、気津両傷の状態。身熱多汗、心煩胸悶、気逆欲嘔、口乾喜飲、虚煩不寐、脈虚数、舌紅苔少。選ぶべき法剤は?
1.竹葉石膏湯
2.清営湯
3.清暑益気湯
4.白虎加人参湯
回答→ 1
【解説】
1.竹葉石膏湯(清気分熱剤)ー暑病後の余熱未清で気津両傷の病証の治療。
2.清営湯(清営涼血剤)ー邪熱が営分に入血しておきる病証の治療。
3.清暑益気湯(清暑益気剤)ー暑熱が気津を傷つける病証の治療。
4.白虎加人参湯(清気分熱剤)ー白虎湯証で、気津両傷の病証の治療。
問題 清暑益気湯の臨床の使用で暑熱が酷くなく津液大傷の場合、取り去るべき生薬はどれか。
1.黄連
2.西洋参
3.荷梗
4.麦門冬
5.竹葉
回答→ 1
【解説】
問題の病態では、熱を清ますよりも陰液を補うことが重要。そのため、最も強力な清熱作用を持ち、胃腸に負担をかける可能性のある黄連が、取り除くべき生薬として最も適切である。
問題 清暑益気湯の臨床の使用で挟湿邪を兼ねる場合、取り去るべき生薬はどれか。
1.黄連
2.西洋参
3.荷梗
4.麦門冬
5.竹葉
回答→ 4
【解説】
清暑益気湯は、夏の暑さ(暑熱)によって気と津液が消耗した状態を治療する方剤です。
麦門冬は、この津液を補うために配合されています。潤いを生み出し、肺や胃を滋養する働きがあります。
しかし、もし患者が「湿邪」、つまり余分な水分が体内にこもった状態を同時に患っている場合、麦門冬は使用すべきではありません。
問題 六一散の効能はどれか。
1.清暑通絡
2.清暑化湿
3.解暑除煩
4.清暑利湿
5.袪暑清熱
回答→ 4
【解説】
六一散は、の名前は、滑石を六の割合で、甘草を一の割合で配合することに由来する。主に、暑邪と湿邪が結びついた病態を治療する。
問題 清絡飲の効能はどれか。
1.清暑通絡
2.清暑化湿
3.解暑除煩
4.清暑利湿
5.袪暑清熱
回答→ 5
【解説】
清絡飲は主に、暑邪が肺経を傷つけた病態を治療します。
問題 中暑受湿により、発熱頭痛、煩渇引飲、小便不利あるいは藿乱吐瀉の症状が現れる。選ぶべき方剤はどれか。
1.藿香正気散
2.香薷飲
3.参苓白朮散
4.六一散
5.桂苓甘露飲
回答→ 5
【解説】
病態の分析:暑熱と水湿の結合
この症例は、夏の暑さ(暑熱)が原因で、体内に余分な水分(水湿)が滞り、体の巡りが悪くなっている状態です。
・発熱頭痛、煩渇引飲: 暑熱が体内にこもっていることを示しています。体が熱をもち、頭が痛み、喉が渇いて水分を欲します。
・小便不利、藿乱吐瀉: 体内に水湿が停滞していることを示しています。余分な水分がうまく排出されないため、尿の出が悪くなり、消化器の機能が乱れて吐き気や下痢を引き起こします。
これらの症状が同時に現れるのは、暑熱と水湿が結びついた複雑な病態であり、桂苓甘露飲が最も適した治療法です。
1.藿香正気散
夏に風邪をひいて、体内に湿気がこもった病態に用います。
2.香薷飲
夏に風邪をひいて、体内に湿気がこもった病態に用います。
3.参苓白朮散
脾胃の働きが弱く、湿気がこもり、下痢をする病態に用います。
4.六一散
暑さによる体内の熱と湿気を同時に取り除く方剤ですが、桂苓甘露飲のように消化器の不調(藿乱)には特化していません。
ポイント
桂苓甘露飲は、石膏や滑石で暑熱を冷まし、猪苓や茯苓で水湿を排出します。さらに、官桂を少量加えることで、体を温めて気の巡りを良くし、水分の排出を助けるという、絶妙なバランスを持っています。
問題 暑湿の感受により、身熱煩渇、小便不利あるいは大便瀉泄の症状が現れる。選ぶべき方剤はどれか。
1.藿香正気散
2.香薷飲
3.参苓白朮散
4.六一散
5.桂苓甘露飲
回答→ 4
問題 香薷散の効能はどれか。
1.散寒解表 化湿和中
2.散寒解表 理気和中
3.袪暑解表 化湿和中
4.袪湿化濁 理気寛中
5.袪暑解表 清熱化湿
回答→ 3
問題 新加香薷散の効能はどれか。
1.散寒解表 化湿和中
2.散寒解表 理気和中
3.袪暑解表 化湿和中
4.袪湿化濁 理気寛中
5.袪暑解表 清熱化湿
回答→ 5
【解説】
・香薷散
夏に冷たいものを飲食したり、冷房の風にあたったりすることで、体表に寒邪、体内に湿邪が停滞した陰暑に用いる。夏の暑さの中で、冷えが原因で起こる感冒に特化している。
・新加香薷散
暑邪と湿邪が同時に体内に侵入し、熱がこもった病態に用いる。
香薷散の処方に、金銀花や連翹といった清熱作用のある生薬が加わる。これにより、暑熱と湿邪が結びついた病態を治療する点が、香薷散との最大の違い。香薷散が「冷え」を原因とするのに対し、新加香薷散は「熱」を原因とする夏の感冒に適す。
問題 患者、夏に外出から帰宅すると、頭がはっきりせず、昏眩、弱い頭脹、胸悶不舒、舌淡紅、苔薄白。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.桑菊飲
2.香薷散
3.新加香薷飲
4.清絡飲
5.竹葉石膏湯
回答→ 4
【解説】
病態の分析:暑熱傷肺
この症例は、夏の暑さ(暑邪)が体に侵入し、肺に影響を与えている病態です。症状から、暑邪はそれほど強くなく、体の表面的な部分に滞り、経絡(エネルギーの通り道)の流れを阻害していることがわかります。
・昏眩、弱い頭脹: 暑熱が頭部に影響し、気の巡りが悪くなっていることを示します。
・胸悶不舒: 熱が肺にこもり、胸が苦しい感じがします。
・舌淡紅、苔薄白: 舌の色は薄く赤く、苔は薄くて白いことから、病邪がまだ浅い部分にあることを示唆しています。
これらの症状は、暑邪が軽度に肺を傷つけ、気の巡りを妨げている「暑熱傷肺、邪在気分」という病態の典型であり、清絡飲が最も適しています。
1.桑菊飲
風熱による初期の風邪を治療する方剤です。
2.香薷散
体表に寒(悪寒)があり、体内に暑湿(胸悶、腹痛、吐瀉)がこもった病態に用います。
3.新加香薷飲
体表に寒(悪寒無汗)があり、体内に暑熱(口渇、心煩)がこもった病態に用います。
5.竹葉石膏湯
熱病の後期に、余熱と気津(潤い)の消耗がある場合に用います。
ポイント
この問題の鍵は、夏の暑さが原因であることと、症状が重くない点です。特に、高熱や激しい口渇、黄膩苔といった強い熱証がないため、軽度の暑邪を治療する清絡飲が最適だと判断できます。清絡飲は、金銀花や扁豆花といった、穏やかな生薬を主とし、暑邪を優しく発散させるのが特徴です。
問題 発熱頭痛、悪寒無汗、口渇面赤、胸悶不舒、苔白膩、脈浮数。治療で選ぶべきものはどれか?
1.香薷散
2.新加香薷飲
3.竹葉石膏湯
4.清絡飲
5.桂苓甘露飲
回答→ 2
【解説】
病態の分析:外寒と裏熱
この症例は、夏の暑い時期に、冷房や風などで体表が冷やされて外寒に侵され、同時に体内に暑熱がこもっている状態です。
・悪寒無汗: これは「外寒」の典型的な症状です。体表が冷やされて毛穴が閉じてしまい、悪寒がし、汗が出ません。
・口渇面赤、胸悶不舒: これは体内の「暑熱」を示しています。熱がこもっているため、喉が渇き、顔が赤くなり、胸が苦しく感じます。
・苔白膩、脈浮数: 舌にねっとりとした白い苔が見られ、脈が速いことから、体内の熱と湿気が同時に存在していることがわかります。
これらの症状が同時に現れるのは、体表の寒邪を追い出すと同時に、体内の熱を冷ます必要のある、新加香薷飲の治療対象です。
1.香薷散
表に「寒」、裏に「暑湿」がある場合に用います。湿気の症状(腹痛、吐瀉)が主体となります。
3.竹葉石膏湯
熱病の後期に用いる方剤で、この症例のような「外寒」の症状には適しません。
4.清絡飲
暑熱が体に浅く侵入した軽症に用いる方剤で、この症例のような「外寒」の症状には適しません。
5.桂苓甘露飲
暑熱と水湿が結びついて、尿の出が悪くなる病態に用います。
ポイント
この問題の鍵は、「悪寒無汗」と「口渇面赤、胸悶」という、矛盾するような症状が同時に現れている点です。これは、体表に寒、体内に熱という、新加香薷飲が治療する特殊な病態であることを示唆しています。
問題 中暑受熱、気津両傷で、身熱汗多、心煩口渇、小便短赤、体倦少気、精神不振、脈虚数の症状が現れた。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.生脈散
2.六一散
3.清暑益気湯
4.竹葉石膏湯
5.白虎加人参湯
回答→ 3
【解説】
病態の分析:夏の暑さと気津の消耗
この症例は、夏の暑さ(暑熱)が原因で、体内の気と津液が著しく消耗した状態です。
・身熱汗多、心煩口渇、小便短赤: これは、暑熱が体内にこもっていることを示しています。熱が盛んで汗が止まらず、喉が渇き、尿の色が濃くなります。
・体倦少気、精神不振、脈虚数: これは、気が不足していることを示しています。体がだるく、やる気が出ず、脈は速いものの力がない状態です。
これらの症状が同時に現れるのは、暑熱が原因で気と津液の両方が傷ついた中暑受熱、気津両傷の病態であり、清暑益気湯が最も適しています。
1.生脈散
熱邪がそれほど強くない、軽度の気陰両虚に用います。この症例のような強い熱の症状には向きません。
2.六一散
暑熱と湿気が同時にある場合に用います。湿気の症状(むくみ、下痢など)が主ではありません。
4.竹葉石膏湯
熱病の後期に体内に残った余熱を冷まし、気津を補います。しかし、この症例のような強い発汗や口渇には、清暑益気湯の方が適しています。
5.白虎加人参湯
非常に盛んな胃熱(陽明熱)を冷ます方剤です。この症例のように気津の消耗を伴う場合でも使えますが、清暑益気湯は「夏」の暑さに特化した処方です。
問題 暑湿の感受により、身熱煩渇、小便不利或いは大便瀉泄の症状が現れる。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.藿香正気散
2.香薷飲
3.参苓白朮散
4.六一散
5.桂苓甘露飲
回答→ 4
【解説】
この症例は、夏の暑さ(暑邪)と、それに伴う余分な水分(湿邪)が同時に体内に侵入し、熱と湿気が結びついた湿熱という病態です。
| 鑑別点 | 六一散 | 桂苓甘露飲 |
|---|---|---|
| 病因・病態 | 暑湿が軽度に体表や臓腑に侵入し、湿熱が心や津液を傷つけた状態。 | 暑熱に傷つけられ、水湿が体内に停滞し、気機の昇降失調をきたした状態。 |
| 代表的な症状 | 身熱煩渇、小便不利、あるいは大便瀉泄。 | 発熱頭痛、煩渇引飲、小便不利、霍乱吐瀉など。 |
| 主薬(君薬) | 滑石 | 石膏、滑石(両方とも君薬) |
| 配合生薬の特徴 | 滑石と甘草のシンプルな配合。 | 石膏、滑石、猪苓、茯苓、沢瀉、白朮、肉桂など、利水作用の生薬がより多く配合される。 |
| 利湿の力 | 穏やかな利尿作用で湿を排出。 | 強力な利水作用と、肉桂による気化作用の補助で、水湿を積極的に排出。 |
問題 患者、暑湿を感受した。発熱頭痛、煩渇引飲、小便不利、嘔吐泄瀉の症状が現れた。治療で選ぶべきものはどれか?
1.新加香薷飲
2.藿香正気散
3.麻杏甘石湯
4.清暑益気湯
5.桂苓甘露飲
回答→ 5
【解説】
この症例は、暑邪と湿邪が同時に体に侵入した病態で、特に湿内停による昇降失職という、水分の停滞によって脾胃(消化器)と膀胱(排泄器)の働きがひどく乱れている状態です。
・煩渇引飲: これは、体内の暑熱が盛んで、水分(津液)をひどく消耗していることを示しています。
・小便不利、嘔吐泄瀉: これらは、湿気が体内に停滞し、水分代謝を司る脾胃(ひい)と膀胱の働きが故障していることを示します。
ポイント
・清熱と利湿: 桂苓甘露飲は、石膏や寒水石で暑熱を冷まし、滑石、猪苓、茯苓などで湿気を排出します。
・理気薬を配合しない理由: 湿邪が排出されれば、気の巡りの故障(昇降失職)は自然に回復します。そのため、理気薬をあえて配合する必要がありません。この点が、桂苓甘露飲の重要な特徴です。
1.新加香薷飲
体表に「寒」があり、体内に「暑熱」がある場合に用います。
2.藿香正気散
外邪が原因の嘔吐や、寒湿による下痢に用います。
3.麻杏甘石湯
熱が肺にこもり、咳や喘息を伴う場合に用います。
4.清暑益気湯
夏の暑さで気と津液が消耗した「気津両傷」に用います。
| 生薬名 | 分類 | 主な働き |
|---|---|---|
| 石膏、滑石、寒水石 | 君薬 | 清解暑熱、利水滲湿。体内の強い熱を冷まし、湿気を排出します。 |
| 茯苓、猪苓、沢瀉 | 臣薬 | 利水滲湿。体内の余分な水分を尿として排出するのを助けます。 |
| 白朮 | 臣薬 | 健脾燥湿。脾胃の働きを助け、湿気を取り除きます。 |
| 肉桂 | 佐薬 | 温陽化気。少量を加えることで、気の巡りを良くし、水分の排出を促進します。 |
| 炙甘草 | 使薬 | 調和諸薬。各生薬の働きを調和させ、胃を保護します。 |
問題 患者、夏に飲冷受寒により発熱頭痛、悪寒無汗、身重困倦、胸悶氾嘔、腹痛吐瀉、舌苔白膩、脈浮。治療で選ぶべき方剤はどれか?
1.竹葉石膏湯
2.連朴飲
3.新加香薷飲
4.香薷散
5.清暑益気湯
回答→ 4
【解説】
この症例は、夏の暑い時期に、冷たい飲み物などで体表が冷やされて外寒に侵され、同時に体内に暑湿がこもっている状態です。
・発熱頭痛、悪寒無汗: 体表が冷え、毛穴が閉じて発熱し、悪寒がしますが、汗が出ません。これは「表寒」の症状です。
・身重困倦、胸悶氾嘔、腹痛吐瀉: これは、体内にこもった「暑湿」が消化器系に影響を与えていることを示します。体が重く、だるさを感じ、胸が苦しく、吐き気や腹痛、下痢を伴います。
・舌苔白膩、脈浮: 舌にねっとりとした白い苔が見られ、脈が浮いていることから、体内に湿気がこもり、邪気が体表にあることがわかります。
1.竹葉石膏湯
熱病の後期に、余熱と気津(潤い)の消耗がある場合に用いる方剤で、この症例のような「外寒」の症状には適しません。
2.連朴飲
湿熱が中焦(消化器系)に停滞し、熱が盛んで、湿熱がひどい場合に用います。
3.新加香薷飲
香薷散と似ていますが、体内に「暑熱」がこもっている場合に用います。この症例のように「口渇面赤」や「脈数」がないため、暑湿と判断します。
5.清暑益気湯
夏の暑さで気と津液が消耗した「気津両傷」に用いる方剤です。
ポイント
香薷飲と新加香薷飲は、どちらも夏の時期に「表寒」を治療しますが、体内の邪気の種類が異なります。
・香薷飲: 体表に寒がある一方で、体内に「暑湿」がこもっている場合に用います。湿気の症状である「身重困倦」や「腹痛吐瀉」が主です。
・新加香薷飲: 体表に寒がある一方で、体内に「暑熱」がこもっている場合に用います。この場合、喉の渇きや顔の赤み、脈が速いなどの「熱」の症状が目立ちます。
袪暑剤のまとめ
袪暑清熱剤
・清絡飲ー肺が暑熱受傷。邪軽病浅の病証を治療。
袪暑解表剤
・新加香薷飲ー暑湿の初めで、表寒を兼ねる病証を治療。
袪暑利湿剤
・六一散ー暑邪挟湿の病証を治療。(暑湿の治療の基礎法剤)
・桂苓甘露飲ーその病状の重い者の治療。
清暑益気剤
・清暑益気湯ー暑傷気津の病証の治療。
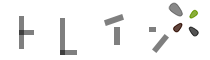




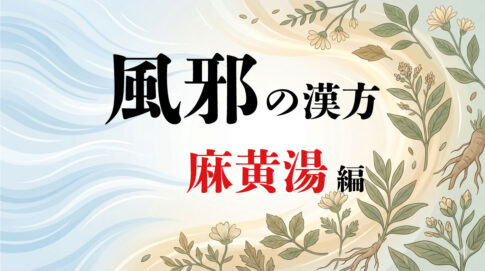
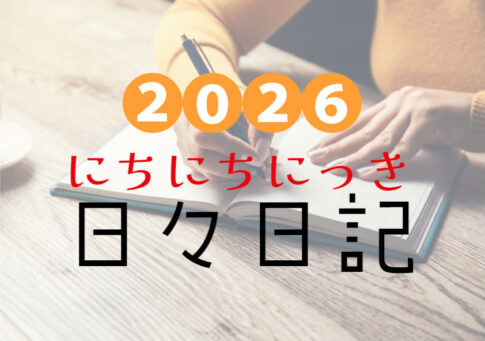

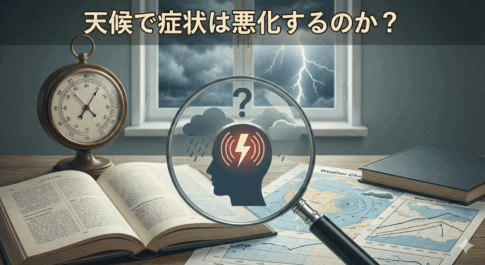
コメントを残す