問題 中医学において人体は一つの有機整体であると考えるが、この整体性の中心とするのはどれか。
1.経絡
2.臓腑
3.神
4.六腑
回答→ 2
【解説】
整体観念と弁証論治は中医学の理論体系の基本的特徴である。 その中の整体観念とは、 人体は有機整体であるということと、人体は自然界の1つに過ぎないという意味である。有機的とは、多くの部分が緊密に繋がり、互いに影響し合いながら全体としてまとまっている状態である。 人体においては当たり前に思うことかもしれないが、例えば咳が出る症状があったとする。 西洋医学では肺の炎症を抑える薬や、咳を沈める薬で治療を行うのことが多いであろう。しかし中医学では、「体の内部の病変が咳という形で外部に現れた」と考える。したがって四診によってさらに情報を収集し、最終的にどのルートで肺系統に影響が出ているのか等を分析するのである。 つまり人体を構成している複数の臓腑、組織、器官などすべてが相互に影響し合っている ということである。
問題 下記で「証候」に属するのはどれか。
1.角弓反張
2.心脈痹阻
3.悪寒発熱
4.痢疾
回答→ 2
【解説】
証候は弁証の結果として得た病理状態の総括である。中医学では「証」ともいう。例えば腎陰虚証や血虚証などある。その他の選択肢は症状である。
問題 次のうち虚を示す証候はどれか。
1.気血虚弱
2.正気不足
3.邪留傷正
4.体質虚衰
回答→ 2
問題 「陰勝れば則ち陽を病み、陽勝れば陰が発病する」は陰陽のどの性質を表しているか。
1.対立制約
2.互根互用
3.消長平衡
4.相互転化
回答→ 1
【解説】
「陰勝れば則ち陽を病み、陽勝れば陰が発病する」は陰陽偏勝(陰陽偏盛ともいう)を表している。これは異常に盛んでいる方が相手に影響を与えてしまう状態で、陰陽学説の対立制約が崩れた状態と言える。
問題 「陰損及陽」、「陽損及陰」は陰陽のどの関係を示したものか。
1.対立制約
2.相互消長
3.相互転化
4.互根互用
回答→ 4
【解説】
「陰損及陽」、「陽損及陰」は、「陰損は陽に及ぶ」、「陽損は陰に及ぶ」という意味で、つまり自分だけでなく相手にも影響を与えるということ。これは陰陽学説の互根互用という関係があるからだ。陰陽互根とは互いに相手に依存している関係をいう。陰陽の双方の根が互いの相手のところにあると考える。他方が相手なしでは存在できない。
問題 「重陰必陽、重陽必陰」はどの陰陽の関係に属するか。
1.対立制約
2.相互消長
3.相互転化
4.互根互用
回答→ 3
【解説】
「重陰必陽(ちょういんひつよう)、重陽必陰(ちょうようひついん)」は陰陽の相互転化の病理変化を表す。「重陰(陽)」とは、2つの陰(陽)が重なることを表現し、陰(陽)が極まることを意味する。陰陽学説では、対立する陰陽が「物極」に達した時、陰陽の相互転化が起こるとされる。例えば昼夜の入れ替わりも陰陽の転化である。
※転化には「重なる」、「極まる」などの「物極」が条件となる。
問題 「寒極生熱、熱極生寒」はどれに属するか。
1.対立制約
2.相互消長
3.相互転化
4.互根互用
回答→ 3
【解説】
「寒極まれば熱を生じ、熱極まれば寒を生ず」は、陽証から陰証又は陽証から陰証へ転化したことを示す。
問題 「心」はどれにあたるか。
1.陽中の陽
2.陽中の陰
3.陰中の陽
4.陰中の陰
回答→ 1
【解説】
五臓の中でも胸部 (上部)にある心肺は陽であり、腹部(下部)にある肝腎は陰である。さらに可分すると、心と肺では心が陽であり(陽中の陽)、肺が陰である(陽中の陰)。また、肝と腎では肝が陽であり(陰中の陽)、 腎は陰である(陰中の陰)である。
問題 治療原則の「益火之源、以消陰翳」(益火の源、以て陰翳を消す)は、次のどれを指すか。
1.寒なれば之を熱す
2.熱なれば之を寒す
3.陽病は陰を治す
4.陰病は陽を治す
回答→ 4
【解説】
「益火之源、以消陰翳」虚寒証の治療方法で、陽の正気が正常よりも不足(陽の偏衰)して起こる状態なので陰病は陽を治す。つまり虚証に対しては補法という治療原則である。
一方、陰陽偏勝(陰陽のいずれか一方が正常より盛んである状態)の治療原則は損気有余と実者瀉之である。損気有余は、あまりの部分を損なう。実者瀉之は、実の病証は瀉法を用いるということである。つまり陽勝則熱(実熱証)なら治療方法は「熱者寒之」(証候が熱に属する場合、寒冷の気味薬で治療する)である。選択肢であれば「熱なれば之を寒す」である。
問題 「陽がなければ陰は生じず、陰がなければ陽は生じない」は陰陽のどの関係を説明したものか。
1.対立制約
2.相互消長
3.相互転化
4.互根互用
回答→ 4
【解説】
「陰陽の互根互用」は陰と陽の依存関係を指す。例えば、上を陽とし下を陰とするなら、上がなければ下は存在せず、下がなければ上と呼べるものは存在しない。他にも男性を陽とし女性を陰とすると、男性がいなければ女性は存在せず、女性がいなければ男性は存在しないということである。
問題 「寒なれば之を熱す」の治療法を行うのはどれか。
1.実寒証
2.実熱証
3.虚寒証
4.虚熱証
回答→ 1
【解説】
「寒なれば之を熱す」は、証候が寒に属する場合、温熱の気味薬で治療するという意味である。これは陰陽偏勝による実寒証に用いる治療法である。
問題 「水を壮健し、陽光を制す」の治法が適用となるのはどれか。
1.実寒証
2.実熱証
3.虚寒証
4.虚熱証
回答→ 4
【解説】
「水を壮健し、陽光を制す」は、陰を滋養することで陽を制約するという意味である。これは陰陽偏衰(この場合は陰虚陽亢)による虚熱証に用いる治療法である。
問題 「陰病は陽を治す」の病理基礎となるのはどれか。
1.陰盛
2.陰虚
3.陽盛
4.陽虚
回答→ 4
【解説】
「陰病は陽を治す」は陽を補って陰病を治すという意味なので、この場合は陽虚によって陰病になっているため、病理は陽虚である。
問題 腎が剋す(所勝)ものはどれか。
1.肝
2.心
3.脾
4.肺
回答→ 2
【解説】
五行には事象間の調和のために相生と相剋いうと関係がある。相剋の「剋」は、拮抗、排斥、克服を意味し、ある事象が別の事象の成長や働きを抑制、制約する作用をいう。正常な相剋関係では「火→金→木→土→水→火」で剋し、剋される状態である。「我を剋す」ものを「所不勝」、「我が剋す」を「所勝」ともいう。
問題 相剋に基づくと、肺が勝てないのはどれか。
1.肝
2.心
3.脾
4.腎
回答→ 2
【解説】
正常な相剋関係では「心→肺→肝→脾→腎→心」で剋し、剋される状態である。
問題 五行学説で、一行が抑えすぎる異常な状態はどれか。
1.相生
2.相剋
3.相侮
4.相乗
回答→ 4
【解説】
相乗は、相剋関係のバランスが崩れた状態をいう。五行間では「剋す」、「剋される」という相剋関係で相手を抑制、制約しているが、剋す側が異常に抑えすぎた状態を相乗という。
臨床では、肝乗脾や肝乗胃などがある。
問題 「肝火犯肺」に属するのはどれか。
1.母病及子
2.相剋
3.相侮
4.相乗
回答→ 3
問題 五臓六腑で「君主の官」はどれか。
1.肝
2.心
3.脾
4.心包
回答→ 2
【解説】
・肝ー将軍の官
・心ー君主の官(皇帝を意味する)
・心包ー臣使の官
・脾胃ー倉廩の官(倉廩とは食料の倉庫)
・肺ー相博の官
・腎ー作強の官
・胆ー中正の官
・小腸ー受盛の官
・大腸ー伝導の官
・膀胱ー洲都の官
・三焦ー決瀆の官
問題 五臓六腑で「作強の官」はどれか。
1.胆
2.膀胱
3.胃
4.腎
回答→ 4
【解説】
・肝ー将軍の官
・心ー君主の官(皇帝を意味する)
・心包ー臣使の官
・脾胃ー倉廩の官(倉廩とは食料の倉庫)
・肺ー相博の官
・腎ー作強の官
・胆ー中正の官
・小腸ー受盛の官
・大腸ー伝導の官
・膀胱ー洲都の官
・三焦ー決瀆の官
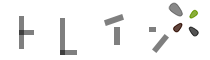




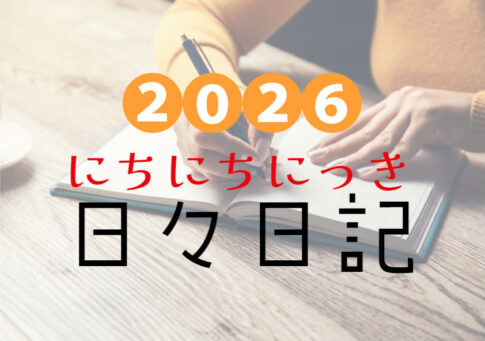
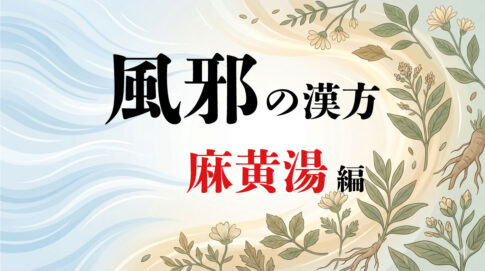
陰陽学説では陰陽には対立、互根 (依存)、制約、消長、転化、可分の関係(法則)があると考える。